

三題噺
――○塾・航空機事故・歌舞伎鑑賞――
われわれが学びつつある○塾の教養課程ではマネジメントの諸相を取り上げているが、それは「組織における認識」問題について議論し理解を深めるためでもある。我々はよく環境の認識が大切だとか、将来に向かっての洞察などという言葉を用いたり聞いたりするけれど、それはどのようなことをいうのであろうか。
認識という問題はその切り口も多様である。組織心理学、認知心理学、大脳生理学、統計学、工学そして哲学などなどの多くの世界で議論されている。アプローチはたしかに多様だが、しかし各分野の研究者の誰もが異口同音のように述べているのは、いわゆる科学の方法論上の有効性を認めながらも「全体の認識」こそが重要だということである。
時は
1966年 2月 4日、19時00分20秒。北海道千歳空港発の全日空第60便のB727が羽田空港を目前にして東京湾に墜落、乗客・乗員の133名全員が死亡するという悲惨な事故が発生した。事故調査団のメンバーであった山名正夫東大教授は、自ら羽田に足を運び、バラバラな残骸から全日空機は急降下からの引き起こしのオクレによる接水であるという初期イメージをもった。そして接水時の状況の再現を事故調査の重要な視点として、膨大な実験を含む調査研究に取り組み、山名レポートとして提出することになる。山名教授の結論をあえて単純化していうなら機体欠陥説である。これに対して木村秀政事故調査団長は始からヒューマン・ファクター(人的要因)に力点を置くという態度で臨んでいた。多分に政治的配慮にもとづく調査視点といえなくはない。
山名教授のレポートとその報告は結果的に全くといえる程無視され、事故調査団としての最終報告書案は原因不明説でまとめられ、またその内容の子細な検討もなされることはなかった。山名教授は事故調査に関する根本理念の相違とずさんな事故調査団の運営のあり方を潔しとせず辞任し単独でこの事故を究明すべく実験研究に打ち込むことになる。
山名教授が心に描いた全日空機の海面への突入角度、そして機体や各部の破壊の進行全過程は模型実験によって再現された。それは実際に海底に散乱している機体、エンジン、主翼あるいは尾翼などの位置と、まさに一致していたのである。
山名教授は後に、事故調査の過程をジグソー・パズルの「絵」の復元になぞらえて説明している。事故調査の最初は、各断片の形や色を調べることから始まる。この時期にはパズルの「絵」全体に占める各断片の位置はまだ明らかではない。次の段階は「全体」と「個」の関係の考察のなかから、いくつかの断片を抽出していく。この全体とは飛行機が接水してからバラバラになるまでの機体の運動および破壊の経過の全体であり、個というはその一瞬の状況に直結する破片の一片一片を指すのである。
絵には、つまり事故の全体には表現しようとする何かがあるはずで、その表現の核心と思われる断片のいくつかを選択すること、そして急所急所が有機的に、かつ矛盾なく統合されたとき、はじめて全貌がわかるという理念である。この実験研究活動を通じて山名教授が常に念頭に置いていたのは事故の全過程の情景であったという。後に『水に打たれて刻々に砕け散る機体の情景を瞼のうちに再現するのが私の仕事であった』という述懐は山名教授の研究方法論を如実に表現しているといえよう。そして『一切の知識は「全形」があって始めて適用されうる。形のないところには、どのような知識も論理も適用のしようがない』と論ずるのであった。
人間の行動の基盤となるのは行動空間であり、換言すれば行動空間として認識された世界の上にわれわれの行動が成り立っているといえる。 「全体」とは、いうなれば行動空間といってよい。それは哲学者の澤田允茂がいう「認識の風景」とか、あるいは心理学者のK.レヴィンのいう「生活空間」とほぼ同じ概念ということができるであろう。そうならば、認識のあり様は、この空間とか風景のひろがりの大小が問われねばならない。そしてこの大きさを規定していくもののひとつに教養があるのではないか。例えば落語を聞く、歌舞伎を観る、映画を楽しむ、小説を読むなども含まれよう。これらすべては、聞き方、観方、読み方、楽しみ方の如何で、ただ目の前を通り過ぎる光や音にしか過ぎないか、行動空間の形成に作用する、あるいは行動空間に出入りする事象の解釈に影響するであろう世界観、人生観を構築することに影響を与える教養となるかに分かれることになるのではないか。
○塾では映画などのヴィジュアル媒体を用いて、楽しみながらマネジメントに関わる諸理論と現象を統合的に議論し、さらには組織の認識という問題に挑戦している。こうした教育環境が存在し得る所以は、構成メンバーのよき相互作用に負うところが大きいと思われる。とにかくも○塾に栄光あれ。
1999
年 5月31日○塾塾頭 加藤 敏雄

目次
巻頭の辞
……加藤 敏雄第一期教養課程プログラム
[教養課程講義概要]
第一回 賢くて愚かな人間
……吉田 真人映画『カンバセーション』
第二回 オーバー・マネジメント
……内山 雅浩映画『北京好日』
第三回 組織の認識
……石森 陽子映画『八甲田山』
第四回 組織の意思決定
……高橋 量一紀行『奥羽会津街道』/ルポ『リストラ』
第五回 創造性
……古川 肇浦達也講師 特別講義「ミクロ・マクロ・ルーズ」
[特別寄稿]
○塾縁起 ……江川 匡子
○塾機関誌創刊号に、
屠蘇の酔いに任せて徒然なるままに
……瀧口 公明「関宿」因田社長より励ましのおことば ……因田 俊一
農村で経営学
……綿引 宣道認知的経済性アプローチによる創造性の分析
……熊谷 智博私が『浮雲』をこよなく愛する3つのわけ
……遠田 雄志
[塾生感想]
[論点]
マネー革命を越えて
……遠田 雄志編集後記
……西本 直人Ⅰ
. ’98.11.14(土)賢くて愚かな人間、映画『カンバセーション』
’73, 110’ ,61
Ⅱ
. ’98.12.12(土)オーバー・マネジメント、映画『北京好日』
第1回 名作鑑賞会 映画『浮雲』
Ⅲ
. ’99. 1. 9(土)組織の認識、映画『八甲田山』
’72, (90’),1
Ⅳ
. ’99. 2.13(土)組織の意思決定、紀行『奥羽会津街道』
’99ルポ『リストラ』’99, 45’, 543
Ⅴ
. ’99. 3.13(土)創造性、特別講義「ミクロ・マクロ・ルーズ」浦達也
第2回 名作鑑賞会 映画『野獣死すべし』
’59, 95’
[教養課程]
![]()
――吉田 真人――
盗聴屋の世界という特殊な設定とシナリオ自体がハードボイルド的だったので大変興味を持てました。ビデオでの主人公ハリーの行動を観ていて以下のような事を感じました。
1.悲惨な結末になったが
主人公ハリーの人物像は「プライドが高く、凄腕で頑固な職人気質の持ち主」で「ある種の正義感もきちんと持ち合わせている」ということがビデオの中から垣間見ることができました。
結局、プライドの高さからくる自分の価値観の中でしか判断できない(個性を強く持ち過ぎている)、ということと正義感が仇となり結局それらが原因でハリー自身は悲惨な結果をまねくことになります。
では、ハリーはどうすればよかったのかということを少し考えてみました。
2.和して同せず
自分の価値観の中でしか判断できないということは、結局自分の知識や能力の限界に気がつかないことになると思います。自分がいるソフトウェア業界の話と関連付けて考えてもビル・ゲーツやジェームス・クラークといった天才が画期的発明を行い企業を飛躍的に発展させた例はありますが、大半の場合、新規技術などは普通の技術者がチーム単位で研究開発を行い、その結果が製品となって世の中に普及していると考えられます。これの例が全てではありませんが、たいていの場合一人ではできることの限界はあると考えられます。やはり組織の中に属したり、業務を行う場合は周囲の人とある程度の協調が必要なのではないかと考えられます。周囲の人の意見や行動を見たり聞いたりすることからそれまでの自身の知識や経験からは考えつかないようなことを発見できたり、自分の能力以上のことを行えるのではないでしょうか。
話がそれましたが、ハリーはプライドが高く一匹狼的で周囲の人間全てに非常に距離を置いていました。もしハリーがもう少し周囲との協調をはかっていれば違う結果になったのではないかと思います。(シナリオとしては面白味に欠けるのは想像できますが…)
ただし、ハリーが持っている能力や個性は否定されるものばかりではなく、また“全てみんなと同じ”というと没個性ということにつながるので、結局のところ周囲の人と協調しながらもキチンとした個を保つという「和して同せず」というのが重要なのではないかと考えられました。
――内山 雅浩――
<映画の要約>
北京市内の京劇団の常設劇場で守衛として住み込む韓老人は、かなり以前に妻を亡くしている。舞台にも時折端役として出演、その長い京劇団での生活からにじみでたアドバイスはしばしば監督よりも効果的でもあり、その点を自負している。彼は気難しく、その仕事ぶりは硬直的でもある。
65歳を機に渋々引退するが、暇を持て余し気味。もとの職場にも顔を出してはみるがしっくりゆかない。ある日、公衆浴場を覗き見している知恵遅れの子供をたしなめたことでその子と友人になり、その子に連れられ公園(屋外)での京劇サークルを目にする。
その京劇サークルは明らかにアマチュアの手になるもので、唄い方も自己流というものだった。「これでも長年京劇団の釜の飯は食ってきた」と自負する韓老人は、一躍アマチュア京劇サークルの「専門家」として脚光を浴びる。
ここから、韓老人の骨折りが始まる。公園ではいかにも寒かろうということで、地域を統括する役所と交渉、公民館の一室を借り老人京劇班を発足させる。京劇の教師を招き、教授をつけてもらう。地域の芸術祭にも参加し、入賞を目指して皆を叱咤激励する。
しかし、韓老人のあまりにも重箱の隅をつつくようなやり方には、もとの公園京劇サークル時代の仲間から反感を買っていた。
ある日の練習中のこと、唄い方について韓老人から注意を受けた董老人は怒りを爆発させる。彼の怒りが契機となって老人京劇班内部に対立が生じ、口論となる。韓老人は「私がこんなに苦労してやっているのになぜ非難されるのか。今日限りで京劇団は解散だ!」と捨て台詞を残し練習を放棄してしまう。
折しも、借りていた公民館に改装計画が持ち上がる。改装後はカラオケ・ボックスに変身する公算が高まり、練習場所が確保できなくなる可能性が高まった。結果的に老人京劇班は解散状態となる。
メンバーの一部はもといた公園に戻り、もとの自己流の唄い方に戻っていった。物影でそれをじっと聴いていた韓老人がその群に向かって歩き出すシーンで映画は幕を閉じる。
この映画は、一つの自然発生的な集団が、部分的に組織化され、急速に崩壊する過程を描いている。以下では、組織化の過程と老人京劇班の崩壊に焦点を当てて、小論を展開したい。
組織化の過程――京劇サークルが老人京劇班に変わる過程で何が起こっていたのだろうか?
1.専門性への指向
変化の過程で、京劇サークルにはなかった「専門性の追求」が生じた。公園で持たれていた京劇サークルはその性質上、京劇を自ら演じること自体を楽しみに来る老人たちの自然発生的な集団であった。そのことは、地域の芸術祭の出演前、テレビカメラの取材に答える老人たちの発言からもうかがえる。「なんといったって、唄うことが気持ちよいのだ。唄わない日は非常にがっかりする」「家では騒々しいといって楽器を弾かせてもらえないが、ここでは存分に弾ける」。こうした発言の共通項は「京劇を自ら演じることが目的」であるということである。そのような集団には、技術・適性を軸にした参加基準は明確には存在しない。そのため、しばしば外野の集団から唄い方が変であるとの指摘を受けるが、それは彼ら集団にとっては特別な意味を持たない――集団の維持・存続に全く影響を持たない――メッセージにすぎない。
韓老人がその京劇サークルに「老人京劇班」という形式的な枠組みを与え(このときから「老人京劇班」とする)、指導講師をつけたときから、「老人京劇班」のなかに専門性の追及が課題として植え付けられた。韓老人は自分がかつて身近に接していた京劇団を前提として、技術にやや偏執的に固執するようになる。それは芸術祭本番で見られたように、実際に高度な技術を持つ講師から見ても明らかに過剰と映った――そのために感情的になり韓老人を制止せざるを得なくなるほどの――重箱の隅をつつくような干渉の数々となって現れた。もちろん、日常の老人京劇班の練習の最中にまで現れたに違いない。
韓老人が生起させたこの変化は京劇サークル時代の人々にとっては受け入れ難いものであった。
2.無意味なルールの強要
老人京劇班発足時に韓老人は「遅刻したものはその日一日唄わせない」という規則を自ら定め京劇団メンバーに強要した。このルールを設定するにあたって、彼は何らその根拠を示さなかった。正確には、京劇団の守衛時代の形式的・硬直化した仕事――わずか
5分の遅刻をわざわざ言いたてるような――の延長だったのだろう。彼はこのルールを形式的に、厳格に適用し続けた。根拠の乏しいルールは容易には受け入れられず、適用するにあたっては摩擦を避けられない。実際に、京劇サークル時代の女形のメンバーとは反目を呼んでいる。
3.メンバーの個人目的と集団の目的の合一性の維持
通常の企業組織のような場合、それが機能体として存在する以上、組織メンバーの目的と組織の目的が乖離することは免れないし、乖離するのが自然といえる。組織自体は組織のなす行為の成長性や収益性に目的を置くかもしれないが、そこに参加しているメンバーは「この会社は良質の仕事が回ってくる。スキルを身につけてもっと自分の市場価値を高めてやるのだ」と考えている場合もある。組織メンバーの行為は組織の行為に包含されていても、目的というベクトルでは異なる。
京劇サークルにあっては、この目的の乖離は生じていない。サークルは自然発生したものであり、「楽しむこと」がサークルメンバーの最大の目的であった。このとき、サークルの目的も「メンバーが楽しめること」になる。技術・適性は二次的な問題になる。
韓老人が京劇サークルを老人京劇班に無理に変質させたときから、劇団の目的として、「技術の追及」と「外部からの評価」が制定されてしまった。しかし、依然メンバーにとっては外部の評価など本来どうでもよいままだった。芸術祭の帰途、「入賞なんてどうだっていいじゃない。楽しければそれでいいじゃないの」という発言はこの現れである(韓老人はこれに対し猛反発している)。京劇サークル時代の仲間の認識に、老人京劇班への改組後も大きな変化はなかった。
老人京劇班への改組は、自然発生的な集団が持つ個人目的と集団の目的の合一性に必ずしも楔を打ち込むものとはならなかった。京劇サークルから老人京劇班への変化は、組織体としては依然不完全なものと位置付けられる。
まとめると、京劇サークルは部分的に組織化された。
それをメンバーは完全に受容できず、その不完全さが崩壊の原因となる。
では、老人京劇班の崩壊について記述してみたい。老人京劇班は、映画中ではわずか
10分足らずのあいだに実質的に機能をとめた。発端は、董老人がその唄い方の欠点を韓老人および演奏にあたっていた老人たちの二者から指摘され、それに立腹したことに始まる。その10分間のあいだに、老人京劇班のなかにフェスティバル型異常組織が生成され、消滅した。生じたフェスティバル型異常状態では、まず、京劇の唄い方に関して共有するものすらない。韓老人がダメだと断言したものを、演奏担当の老人は善しとする。その逆もある。これでは、董老人を非難することはできない。さらに、韓老人の喧嘩騒ぎ(ガラスが割れるなど)に参加しない老人はひたすらテープレコーダーに耳を傾ける、無関心を装う、などとしており、実質的に各人の解釈と判断が優先されていた。
この異常状態は、韓老人が一方的に京劇団の解散を宣言した時点で一応終結する。
老人京劇班の崩壊には、もうひとつ指摘したい点がある。韓老人抜きでも存続は可能だった(彼は結局やかまし屋に過ぎなかった)のに、なぜそのまま自然消滅したのだろうか。理由は、老人京劇班の一見統制が取れた状態(「組織」に見えた状態)は、韓老人が意図的にイナクトした環境に過ぎず、韓老人の脱退とともに元のルースなつながりしかない相互関係に戻ったためであろう。脱退後、夜にもとの練習場所で京劇班の何人かが集まり、韓老人が中の会話を外からそっと聴くシーンがあった。そのメンバーは、もとの京劇サークルのメンバーが大半を占めていた。
折しも、利用していた公民館が改装され、改装後はカラオケ・ボックスになるという外部要因があった。韓老人以外のメンバーが組織を存続させる意志があったならば、ほかの場所を借りるなどできたはずである。その努力が全くなされず、もとの公園に回帰していったのは、緩やかなつながりに戻っていったためである。
この映画では、スピーディーではあるが、組織化のプロセスを描いている。実際のケースでは、もっと時間をかけてすべての過程が完了するであろう。悲喜劇を遥かに超えた、濃い内容の映画であったと思う。
――石森 陽子――
1.はじめに
『八甲田山』は、八甲田山遭難事故の歴史を取材して描いた小説を、映画化したものである。内容は、雪中行軍の2部隊即ち、少数精鋭で全行程を踏破した隊と、
199名の死者を出した大隊の2つの隊を対比させ、自然と人間の闘い、組織の指揮系統、或いは意思決定過程、リスク管理などを示唆するものである。自己を顧みる機会となり印象的だった。そこで、両隊長の仕事の進め方を通し、リーダーシップや意思決定過程などを考察する。
2.『八甲田山』にみる組織活動
日露戦争を控えた明治
35年(1902年)1月、厳寒地での作戦行動の可能性を研究する目的で、弘前歩兵隊(以下①と略)徳島大尉、青森歩兵隊(以下②と略)神田大尉が、八甲田山の雪中行軍を行うことになった(図1(1);文末に掲載)。軍の組織は、以下のようである(師団長は物語に出てこない)。次に、雪中行軍の行動計画などを要約し、比較する(表1;文末に掲載)。
3.考察
組織とは「一定の目的を達成するため、意識的に統括された複数の人間の活動ないし、諸力の体系である」
(2)。言い換えれば、組織には目的があり、統制があり、組織者がいるとう特徴がある。その諸活動での意思決定過程は、目標や問題の明確化、代替案の設計、それら代替案の結果予測、各結果の評価、一つの選択であり、合理モデル(3)と言われる。冬の八甲田山を踏破した①徳島隊は、雪中行軍の研究目標、各人の研究課題を明確にもって活動し、意識的に統括された組織であった。精鋭人選・少数編成、動機づけ、権限と責任などに対する考えを、綿密な計画書で上司に具申し、組織的に合意を得、全てを任されて行動した。そこに、正しく評価しようとする上司の姿勢もあり、相互の信頼関係が伝わる。
さらに、積雪や道案内人や民宿などの調査と分析、それらの結果予測、気候など変化による危機予測、それに対応した装備や携帯品を選択決定し、周知徹底した。これら一連の過程は、合理モデルと一致する。雪中行軍は、極限状態に陥りやすい環境下にあるが、各人の役割認識、研究結果の即応用と評価、道案内人や民宿での人との交流を通して、精神的な充実と安定をも得られていたと推察する。この安定こそが、雪中行軍のエネルギー源になったのではないだろうか。
一方、②神田隊は、収集した情報を活用できず、予行練習では部下の意見を取り込むこともない。目標や課題に対する確認や進言がなく、疑問を抱きながらも上司に従っていた。雪中行軍中、山田少佐の突然の指揮権発動は、組織を混乱させる源になった。ここでも具申することがなかった。時代背景や上司に恵まれなかったとはいえ、日頃から当事者意識が希薄である。②神田上司の曖昧な態度は、部下のやりきれない感情噴出、やる気意欲低下に連動する。三日間という短期計画とはいえ、非常事態発生などの認識、代替案設計、結果予測などが甘かった。
リーダーシップとは、共通の目標達成に向けさせるための対人間の影響力と言われるように、目標達成とチーム維持機能を持ち、リーダーとメンバーと、その時の状況によって決まってくる。リーダーが、権限による指示・命令で部下を動かしても、それは真に動かしたとはいえない。メンバーが自主的、主体的に取り組もうとする姿勢が重要である。そのための働きかけ、即ち動機づけを行う能力が必要である。たとえば、仕事の割り当てを効果的に行って意欲を引き出し、能力開発・学習機会を作り、しっかりした人間観で相手を知り、正しく評価できるか否かだ。①徳島は、隊の編成を行う初期からこうしたことを実践し、余裕をもって準備や雪中行軍を進めた。
また、リーダーには、技術的・専門的能力や人間関係能力に加え、自分たちが置かれている全体的状況の本質を洞察し、論理的思考で将来的な構想を立てる力や、問題を形成する創造力、意思決定能力などの総合判断力が問われる。即ち、統率、判断、実行という個人の力であり、それは信頼関係を生み出していく力ともなる。その信頼関係が、組織を強化していく。原作では、①徳島が、部下から、案内人のことで問われた時「将校たる者は、その人間が信用できるかどうかを見極める能力がなければならない。…中略…他人を信ずることがきない者は、自分自身をも見失ってしまうものだ」
(4)と言っている。この信念が、雪中行軍成功の鍵でもあったと考える。望ましいリーダー像に近づくには、自己概念や感情を客観的にとらえて、自己防衛せず、自分自身が変化、成長への努力をしなければならない。遠田先生が、リーダー要因として挙げられたパフォーマンス、説得力、豊富な語彙、洞察力なども、日頃の鍛えなくして容易に出切るものではない。今回、コミュニケーション問題などには触れなかったが、それらも課題である。
注
1)新田次郎著『八甲田山死の彷徨』新潮社、1991(38版)見返し図
2)遠田雄志著『グッバイ!ミスター・マネジメント』文眞堂、1998、5ページ
3)同上、7ページ
4)前記1)、56ページ
参考資料
1)村上良三著『仕事を推進する』産能大学、1997
2)加藤秀俊著『人間関係 ―理解と誤解―』中公新書、1986
|
小隊編成で先行した①徳島隊 |
大軍団編成の②神田隊 |
|
|
軍隊編成計画 |
雪中行軍経験の隊長がいる |
経験者がいない、情報収集を活かさない |
|
少数編成(少数精鋭;参加条件掲示、募集、履歴や面接調査) |
懐疑心、競争心が強い |
|
|
行軍予定経路調査(道路、積雪、案内人や民宿有無) |
予行練習目標、理解や真剣さが乏しく、吹雪など悪天候に伴う危機検討をしていない |
|
|
計画や役割が早期に決定、周知(12/25編成終了、1/20出発、11日間の行程) |
大隊編成、上部機関随行で、混乱が予測された |
|
|
各人或いは共同研究課題の明確化(気象、雪中行軍法、寒冷に対する疲労度、凍傷予防と処置、装備、携帯食、宿営) |
編成直後決行(1/21計画発表、1/22編成、1/23出発、3日間行程 |
|
|
参加者は各隊で選抜、交流や準備期間がない |
||
|
他者評価 |
磊落な男 |
努力家、仕事に尽瘁、独断先行を特に慎む |
|
中隊長の特性 |
雪中行軍の経験があり、それを活かす |
体験はないが、情報収集をしている |
|
自分の意見をもち、上司にも具申できる |
収集した情報を活かしていない(活用しない) |
|
|
人選を自分の思考、目で行った |
疑問点の確認や、具申もせず、諦めやすい |
|
|
案内人など他者を活用し行動できる |
上司の意見に従う、あるいは受け入れるのみ |
|
|
調査などで事実にもとづいた行動計画 |
部下の意見を取り上げていない |
|
|
余裕がある(資源活用がうまい) |
全て自分で行い余裕がない(気持ち、時間) |
|
|
雪中行軍実施 |
指揮系統が一本化し徹底していた |
大事な時に隊長が意思表示をしていない |
|
各人が課題や役割認識をもって活動した |
委譲業務の権限と責任が曖昧、役割意識が希薄 |
|
|
研究結果を全員に周知、活用した |
突然、指揮系統が変わり、メンバーが混乱 |
|
|
案内人や民宿利用により、余裕がある(歩き方、食事、睡眠、衣類などを吟味、日々、身軽に行動できた) |
さらに天候急変に、各人が対応できず混乱が拡大した(食事、服装、携帯品などの危機管理) |
|
|
32名、約210キロ、11日間、完全踏破 |
組織の統制機能が崩壊した |
|
|
210名中、199名遭難死亡、生存者11名 |
[表2]
第四回講義 組織の意思決定 紀行『街道をゆく 奥州白河、会津のみち』
ルポ『リストラ、サラリーマンの値打ちが問われるとき』
――高橋 量一――
『街道をゆく(司馬遼太郎)・奥州白河・会津のみち』
ビデオは、関東と東北の境界線の、東北側の薄暗い森の中でひっそりと歴史に包まれた「境の明神」から始まる。坂を一歩下れば関東であり、「栃木県那須町」の看板が立っている。司馬遼太郎氏は、「小ぶりな空間のなかに歴史が苔の下にもぐりこんで息づいていて、たとえ北か南へ数メートル行っても、その気分がこわれてしまう。こんないい所へくるというのも、生涯で何度あるかわからない」とその印象を述べてから、本来は軍事的に重要な施設であった白河関の祭神が武神ではなく、美女神である衣通姫(そとおしひめ)であることを、「まことにやさしいことである」と表現した。司馬氏の奥州への深い想いが、この冒頭の場面からすでに溢れ出ているようであった。
続いて司馬氏は、東北がかつて「黄金花咲く陸奥」と呼ばれていたことを示し、古代東北で算出された大量の金が、天平文化のエネルギー源であり、平安期における仏教文化に支えられた独自の日本文化を開花させることができた基本的条件であったと述べる。空海は渡唐前、渡唐後のことを「空しくゆき、満ちて帰る」と言った。空海は手ぶらで行き、あふれるほどの文化を持ち帰ったことを言ったのであろうが、司馬氏はそれにつけ加えるように、「むなしくとは言ったが、無料(ただ)ではない。かれは袋にずっしりと砂金を詰めて唐へ渡ったのである」と述べた。ビデオの最後に司馬氏が「東北はそれだけで独立していて偉大なのである」と述べているが、東北が戊辰戦争において「白河以北、一山百文」などと蔑称され、近代における日本史研究のなかでも、多くの場合、単なる後進地域であったがごとき扱いを受けてきたことを思うとき、司馬氏の言葉は東北にとって最大限の讃辞と感じられるのである。
話題は数世紀を越えて会津藩へと移る。ここでも司馬氏は「なにから書き始めていいかわからないほどに、この藩についての思いが、私の中で濃い」と打ち明けた。会津藩の藩祖は保科正之である。この人が残した家訓十五箇条が、のちのちまで会津藩を性格づけた。中でも第六条の「家中、風儀を励むべし」という部分に司馬氏は注目し、会津藩の性格を読み解いている。風儀とは文化のことである。士風という強固な精神文化の完成を求めたところに会津藩の性格の根本があると言うのであろう。また、正之は「わら束を切りそろえた」ように、百石から四百数十石までの禄高を中心とした、中間層が全体の85%を占める家臣団を編成した。このことは藩士の自立性を高めた。近代社会において中産階級の多い社会が安定度が高いのと共通している。
会津藩にとって最大の難事が、幕末に訪れた。時の藩主松平容保が、幕府より、ほとんど無秩序になっていた京都の治安を回復するための京都守護職に任じられることになったのであった。容保は、再三にわたって断ったが、幕府の執拗な要請に対して、ついに受諾する決意を固めた。この時、家老の西郷頼母はじめ重臣達が容保に対して、「この時勢に、この至難の局にあたるのは、薪を背負って火に入る」ようなものであると強く諫めたが、容保は「自分も当初そのように考えてきた。しかるに台命(将軍命)はしきりである。そのつど固辞してきたために、幕閣のある筋では、会津藩は一身の安全をはかっていると心外なことを言い始めた。いうまでもなく、わが家祖(保科正之)の遺訓に、宗家(将軍家)と存亡をともにすべしとある。もはや遺訓に従って、火中に入るほかはないと決心した」と語り、最後に「君臣唯京師の地を以て死所となすべきなりと、議遂に決す」ということになった。この部分を司馬氏は「会津藩はその後の運命を当初から予想し、承知の上で凶のくじをひいた。史上珍しいことといえるのではないか」と感想を述べている。この時点で完全に会津藩は自らの想造した現実にからめ取られ始めている。自らのあるべき姿(他者からの思われよう)を自らに課して、それを大前提として現実を受け止め、その想造した現実の下で、今度はそれを確固たるものにするべく決断を下しているのである。決議の後に、君臣相擁して泣いたと語られていたが、それは反対した重臣達の中にも、容保と共通の文化的基盤があり、容保が想造しつつあった現実が、彼らによってもまた主観的現実として受け止めることが可能であったからこそ、感極まって涙したのであろう。それは現代人からみれば決して合理的な判断ではなかったと言われるかもしれない。しかし、だからどうしたというのであろうか。現代人が、生き残ることを良しとする現代人に共通の文化の上にたって、それを恰も当然のごとくふりかざして、会津藩の決定を批判することは簡単である。しかし、現代を生きる我々が当然の合理的規準と考えている物差しが、決して絶対の規準ではなく、あくまでも相対的なものであることを知っておくべきであると思う。我々自身、生き残るということを絶対の正しい規準と盲信して、別の決断には目をつぶっている可能性があるのである。
その後の会津藩の歴史は、まさに黙々と定められた運命の上を死地に赴く観がある。しかし定められたというのは、彼らの文化を通して、彼らの内面に想造された現実を事実として受け止めて意志決定を下し続けるかぎりにおいて、定められているのであって、彼らがフィルターを外せば、転換できる可能性のあった時点が数多くあったことを見過ごすことはできない。新撰組が幕府から会津藩の傘下に加えられ、その激しい行為が長州はじめ維新各藩の憎しみの的になっていった時にも、会津藩は、その責任を新撰組に押しつけることを良しとせずにただ黙り続けていたし、明治期に始めて世に出た孝明帝から容保に宛てた二通の書簡についても決して明らかにしようとはしなかったのである。それらの書簡の内容が、会津にとって十分運命を変えうる可能性を秘めたものであったにもかかわらずである。それらの書簡からは、帝がいかにあつく容保を信用していたかを十分伺い知ることができる。帝崩御の後も、容保は生涯、守秘を通した。おそるべきことは、容保は藩士に対しても書簡の存在すら明かさなかったのである。司馬氏は容保を「まことに道理の人というほかはない」と評している。
会津藩の過酷な運命の流れを俯瞰する時、それが美しすぎると感じるのは自分だけであろうか。自分が彼らの行動を美しいと感じるとき、自分はいかなる規準にたって眺めているのであろうか。
意志決定という点に関して眺めてみれば、この事例からは、明確な意志決定がなされる以前に、もっとも重大な選択がすでに終わっていたと考えることができる。すなわち表面に現れている意志決定の場面は、真の決定の氷山の一角であって、現実をどのように受け止めたかによって実は大方針の殆どが決まっているのである。それを決めているのは、文化的土壌であり、またそれを通して現実をいかに受け止めるかという極めて主観的な心情である。分析されるべきであるとされる現実が、すでに想造されているのである。
明治維新は明らかに革命であって、革命である以上、象徴としての総仕上げが必要であり、このため会津はスケープゴートとして凄惨な運命を辿った。明治政府軍に降伏後、会津藩は藩ぐるみ下北半島に流刑され、斗南藩とされ、草根木皮を食する塗炭の苦しみを味わわされた。これについて司馬氏は、「権力の座についた一集団が、敗者にまわった他の集団をこのようにしていじめ、しかも勝利者の側からの心の痛みもみせなかったというのは、時代の精神の腐った部分であったといっていい」と語っているが、正しくその通りであろう。
時代が大きな転換点を迎え、それまでの常識では通じなくなった時、新たな時代を開く精神が生まれ試練に耐えて、やがて常識となっていく。常識という表現に語弊があるのであれば、文化といってもいい。会津藩の士風を尊重する生き方は、おそらく江戸期までの武士階級にかなりの面で共通した常識であったであろう。去りゆく時代の精神の典型として、利害に価値をおかず道理におき、遮二無二筋を通す会津魂は、スケープゴートとしてはおそらく最高の存在であったと思われる。それは、去りゆく時代においてはむしろあるべき姿であった筈だと思われる。維新の志士達の考え方の方が、むしろ異端であり、当時の武士階級からみれば逸脱的であると観られていたであろうと思われる。そう考えると、現在の企業の中で、我々の文化的土壌から受け入れることができないと感じているいくつかの思想が、もしかすると次の時代の常識となるのかも知れないと感じる。また、もし我々が、柔軟に、生まれつつある時代の精神を息することができなければ、仮に去りゆく時代に適応し成功してきた分だけ、次の時代まで生き延びることが困難であることを、会津藩の歴史が語っている。そして、その新しい時代の息吹を感じて決定を下していくことがいかに困難なことであるのか、自分で造っているフィルターを外して現実を眺めることがいかに困難なことであるのか、深く考えさせられる内容であった。
『リストラ、サラリーマンの値打ちが問われるとき』
ビデオには、岐阜県各務原市に本社をおく中日本ダイカスト工業における新たな給料計算体系の導入とその実践の場が克明に描かれていた。ビデオの中では、従業員200名ほどのメーカーと説明されていたが、より具体的に事前知識として同社の概要を把握しておく。中日本ダイカスト工業は、昭和30年1月に創業し、会社組織として設立されたのは昭和34年5月である。一昨年における従業員数は186人で、主にアルミニウム部品、特にアルミニウム合金ダイカストの製造を手掛け、同業種における日本国内の売上高は全国444社中15位、県下10社中2位の実績をあげている。会長は五島昭寿氏、社長は五島正氏である。株式の一部を取引先の親会社が有する他は、大半を経営者一族で有している典型的な同族企業である。(参考までに問い合わせ先、〒5040957、岐阜県各務原市金属団地188、中日本ダイカスト工業株式会社、電話0538-83-7311) 従前から行われていた給料計算の体系は、概ね年功を中心とした基本給と、職務給の合計であったが、同社が新たに導入を図ったのは、基本給を廃止し、職務給(職種別賃金)と職能給(出来高賃金)の合計で計算する体系であった。すなわち、まったくの能力給の導入を目指していたと思われる。しかし、実際には、同社における能力給の体系とは「人質給」と呼ぶ「総合的な人間判断に基づく」給料計算の体系であった。
「人質給」という言い方もすごいが、内容はさらにすごい。まず人間の質を図る基準として、リーダーシップ、表現力など5つの物差しを用意する。さらにそれぞれを5段階評価して、その合計で基本的な給料水準を決定するのである。どこがすごいのかと言えば、それぞれの評価項目に関して、例えば表現力ならば「文章表現の巧みさ及び意見を的確に伝えることができるか」などといった感じで、何を指すのかについて2,3行の短い説明がある他は、評価者の判断にまったくといってよいほど委ねられている点である。このビデオには正直言って驚いた。極めて重要事項である人事問題、さらにはその中でもとびきり大切に扱うべき給料計算の体系について、これほど大ざっぱに、かつ一握りの評価者(実際には一人の評価者と言ってよい)に委ねられているとは、経営者の勇気と決断には頭が下がるが、もし仮に自分が同社に勤務していたらと思うと、そら恐ろしい限りであった。少なくとも、何らかの形での客観性に基づく、どうにかでも納得のできる評価基準が皆無なのである。私の経営している会社で、だいぶ前に、部下から就業規則を見せて欲しいと言われた所長が「俺が就業規則だ」と怒鳴って、大問題となったことを思い出した。
最初に中日本ダイカスト工業の会社概要を述べたが、それには理由がある。私自身が現在経営している(株)三興グループ(参考までに弊社は完全に独立した四つの企業から成り立っている。(株)三興は、傘下に鷹ノ羽運輸(株)、三伸運輸(株)、高大金属(株)を有し、三興は他三社の本社機能などの補完的機能を果たしている。鷹ノ羽運輸は関東甲信越地域の倉庫及び配送を、三伸運輸は関東甲信越地域以外の倉庫及び配送を、高大金属は非鉄金属製品の販売を主力業務としている。すべての管理職は三興に籍を置き、経理・総務などの機能はすべて三興でまとめて行っている。他に、三興では、非鉄金属の加工、ガソリンスタンドなどを手掛けている)と創業・設立の時期、規模、株式の保有形態などでかなり似通っている部分が多いと感じたためである。
弊社は、昭和30年に私の父が創業し、会社組織となったのは昭和33年である。父は終戦後、昭和24年の暮までシベリアに抑留され、帰国後は生家近くの町工場で6年間作業員として勤務し、昭和30年に大型トラック1台の払い下げを買って独立創業した。私が子供の頃は、従業員が我が家に同居しており、それは賑やかであった。経営者も従業員もなく三食同じものを食べ、一緒の風呂に入り、お弁当までみんな同じものを持って出掛けた。従業員の数が増えるに従って、家の隣に社員寮を建設し、大家族的な生活をしていた。そういう環境が続いていたため、昭和58年に父が脳梗塞で倒れ、私が急遽経営を引き継ぐことになった時には、古くからいる方々がみんなで協力して会社を盛り立ててくれたのであった。
しかし、父が築いてきた企業文化は、さらに成長を望むのであれば足枷となる点も多く見受けられた。父が倒れた当初、とにかく毎月の支払いを無事に乗り切る為に、無理矢理でも売上げを伸ばし続ける必要があった。売上げさえ伸びていれば、会社は滅多に潰れるものではない。資金繰りその他の山積みにされていた問題も、急速に売上げを伸ばす中で解決していくべき性格のもので、座して考えていてもどうにもならないことばかりのように思われた。最後まで苦しみぬいたのが、給料体系の変更であった。父の考えは、全員平等といったもので、仕事量に関係なくほぼ一律に年功のみで給料が決定されていた。それでも会社が、殆ど何の支障もなく動き、従業員の士気も今から思えば旺盛であったのは、ひとえに父の個人的魅力と指導力によるものであった。
父の姿が会社から消えて、理科系の学生であった私が経営トップに就いたことで、徐々にではあるが、社内では悪平等が蔓延するようになり、やってもやらなくても同じならやらない方がよいという形で、将に悪貨が良貨を駆逐し始めることとなっていった。給料体系を全面的に改善しようと考えたのは、そういう事情があったからである。
出来る限り客観的に数値で労働量を把握できないものか苦心惨憺した。走行距離(距離歩合)、積み卸し軒数(軒増手当)、手積み手下し作業量、勤務時間などを組み合わせて、誰しもが納得のできる体系を作り出そうと努力した。走行距離と時間の関係を把握するために、地場輸送時の両者の相関係数をとったり、また交通年鑑などの公になっている資料や、時には自分で実際に走行してみるなどして、地域ごとに分けてかなり詳細なデータを収集した。例えば、ゴロがよかったので今でも覚えているが、国道17号線は都内における平日昼間の平均移動速度は時速17キロ前後であるとか、環状八号線は七号線に比較して私鉄の踏切の数だけ移動速度に遅れを生じるなどと真剣に考えて、標準的乗務員が一日に出来る標準的作業量を、数値で把握し、それを基準に給料を計算し、労働意欲をあげようと考えたのであった。最終的には、パソコンにデータを入れて、いくつかの道路とそれぞれの移動速度を入力した平面を構築し、その上でシミュレーションすることで、瞬時にある配達作業の仕事量が計算できる仕組みにしたいと考えた。当然ながら、他の条件も出来る限り忠実に盛り込みたいと願った。
年功をまったく無視するには問題がありすぎた。当時、従業員の中でもオピニオンリーダーとなっていた古参の方々の賃金を、大幅に削ることは、万一の場合、社業の存続を危うくする恐れがあると感じられた。
結果的に完全にパソコンによる処理が導入されるまでには数年を要したが、主要な計算体系の変更は半年あまりで終了させることができた。その際、従業員の給料が落ちないように(つまり常に標準的作業量以上のものが従業員一人一人に割り当てられるように)、いくつかの工夫が行われた。一つ例をあげれば、荷主工場敷地内への車庫移転である。出荷場所と車庫を隣接することで、早く配達から戻った乗務員には、倉庫で翌日の出荷準備を手伝わせることを考えた。それまでは早く帰っても、洗車をする程度の仕事しかなかったのである。それまで荷主企業の出荷準備は、概ねパート労働に頼っていたが、私共が請け負うことで、荷主としても荷扱いに習熟したプロの運送会社が出荷準備を行うことで、出荷数量などの精度が高まる上に、荷物事故なども減少し安心できることになる。乗務員にしても、早く仕事を終えて戻れば、出荷作業に参加して作業量に応じて受け取る給料が増える。
ただし、運送ではある一定以上の成果を望む場合、安易に安全を犠牲にしがちであることには十分留意する必要がある。
中日本ダイカスト工業が、ビデオで見たような強引な給料体系の変更を、一見無事に実施できたのも、カリスマ性に満ちた創業経営者の存在によるところが大きいのであって、それは一見素晴らしいことのように思えるが、危険も孕んでいる。五島会長は、「能力のない必要のない人間が辞めて助かる」などと言っておられたが、それはとんでもない話である。仮にそう思っても、どうして公の場で広言することができようか。おそらく五島会長は本心ではそう思っておられないに違いない。思っておられないと信じたい。なんらかの意図があっての発言なのかもしれないが、経営トップのあのような不用意な発言は、管理職の士気を大幅にそぎ、苦労を倍加させることになるだろう。
経営には、拙速のほうがよい問題と、十分時間をかけて考えて、根回しをして、相談して、意見を聞きすぎるほど聞いてから、更に時間をかけて取り組んだほうがよい問題がある。新しい事業を展開するか否か、などといった問題は、そもそも入ってくる情報が限られていて客観的とか合理的などといっても、結局やってみなければ分からないことが殆どであるから、考えて行動しようなどとばかり呑気なことを言っていたら、永遠に新しい事業など展開できない。ある程度目鼻がついたら、極論すれば、自分の観を信じて踏み切って、やりながら方向を模索し、また修正するのがよいように思われる。やっているうちに、またどんどん新しい情報が入ってきて、目標もどんどん変化して、それこそ生き物のように計画事態が日々進化していくことになる。
反面で、人事に関しては、石橋を叩いても尚渡らないほどの慎重さが要求されると考える。とくに給料に関しては、一生懸命働いている方々の現場の身になって考えるべき問題で、机上で考えてすぐに実施してよいようなものではない。やってみて駄目なら変更するでは、リスクが大きすぎるのである。
何にしろ、時代の流れを汲んで新しいものを吸収しようというのは大切なことで、五島会長の年齢で、旧体制から思い切って新たな大方針を打ち出した勇気と進取の精神には心から敬意を表したい。過去の経験が長ければ長いほど、作り上げてきた自分の世界に対するこだわりはますます強くなるものである。一面で新しいものを導入しながら、その根底では、古い思想が形を変えただけで、もっと言えば、古い思想をますます擁護する為に、新しい概念が導入されるということもあるであろう。中日本ダイカストの試みが新しいものへの挑戦であり、時代を切り開く一歩であると信じたい。
第五回特別講義 創造性 「ミクロ・マクロ・ルーズ」浦達也講師
――古川 肇――

[講義中の浦先生]
前半
ゲストとしてお越しいただいた浦達也さん(元NHKチーフディレクター)に、集団の中でクリエイティブな発想を伸ばすことが(とくに日本で)いかに困難であるか、クリエイティブな発想が皮肉にもクリエイティブな人たちに“出る杭”としてつぶされる現実など、才人たちがいかに嫉妬深い
か、など番組が誕生するまでの様々な人間模様をお話しいただいた。「事実は小説より奇なり」というが、確執の絶えないキー局人事や業界内部の裏話などはドラマ番組以上にドラマティックであった。また
TVスタッフが労多くしていかに報われない仕事かということも驚きだった。浦さんのお話を機にNHKに対する見方が変わった塾生も多いことだろう。氏の塾生一人ひとりに話しかけるような語り口は、講演調を核としながらも上品で温かく、博識とペーソスが入交じったお話の内容、つぎつぎに変化していく理路の愉しさは格別で、塾生は皆氏の人一倍強いパッションに酔った。
【書評】浦さんご紹介の本『孤独について』中島義道著(文春新書)
私は最初、この本は自分のために書かれたものではないかと思った。(自己中心的な奴と思われてもかまわないが)それは“孤独が好き”なゆえに偏見にさらされ、そのことにコンプレックスを抱いてきた人々に、少なからず自信を与えてくれると思ったからだ。
「生きるのが困難な人々へ」という副題のとおり主題は重いが、けっして深刻ぶらず、何より一定の距離を置いて読める点が本書の最大の強みである。本書は哲学者である著者が自分の半生を振り返り、恥をさらけ出しながら読者の考える助けとしており、ニーチェばりの独断と詭弁(とくに序章)ながらも「俺についてこい」的な所がほとんどなく、ユーモアも激情も交えず淡々と語る口調には、かえって温かみを感じる(曲に譬えればブルックナーの8番といったところか)。枯れているといっても底流には“積極的な無常感”といった実存主義的態度があり、冬の日溜まりのように明るい。しかし終章は“人生論”が出すぎて今までの堂々とした孤独論をわずかに減殺している(小さくまとめることもないのに)。が本書の“イブシ銀の昏さ”に読者は圧倒されるだろう。最後に著者は自分の私塾について紹介しているが、われわれ塾生にも関係があるので読んでみてはいかが。
後半
ディプロマ授与をはさみ、映画『野獣死すべし』が上映された。この映画は昭和
30年代前半に作られたため、映像はモノクロで音声も陰影に乏しいが、そのことがかえってこの映画の迫力を増している。主演は仲代達也だが、今のように変化球を自在に投げこなすのではなく、どこにでもいるヤンチャな大学院生を実によく演じていた。この作品ができたのは敗戦後の焼野原からだいぶ復興が進んだ時代で、平和や安全とひきかえに精神的頽廃が進み、再び欺瞞や虚栄が支配しはじめた時代である。このような時代に貧乏だが前途洋々たるエリート大学院生が、正規のルートで出世することが虚しくなり、社会に反発しあるいは精神的枯渇を癒すためにテロリズムに魂を売る、というのがこの映画の下敷きにある。作者は当時のこうした状況を察し、近い将来を先取りするためにこの作品を作ったのではないか。もっとも「野獣死すべし」とは秩序を守る側からの犯人に向けた死刑宣告であるが、犯人の側からすれば権威や腐敗に対する宣戦布告である。作者がどちらの側に立ったか、あるいは客観的に両者の相剋を描きたかったのか定かでないが、それにしても仲代はこうした時代精神と男の暴力願望を見事に代弁していた。
ところでこの映画のエンディングは暗示的だ。放火や強盗殺人などさんざん悪事を働いた主人公はアメリカ留学の夢を実現すべく羽田を飛び発ち、善人だった恋人も悪の誘惑に負け犯罪金で出国を企てるシーンで完結する。観客に手に汗にぎる緊張と不安を強いておきながら、最も期待する犯人逮捕の瞬間前に尻切れトンボに終わっているのだ。その後どうなるかは観客それぞれの想像力に委ねている。これは象徴的である。
江川 匡子
瀧口 公明
因田 俊一
綿引 宣道
熊谷 智博
遠田 雄志

――開塾を祝う――
江川 匡子
○塾と決められ、いよいよ看板を作る、それもどういった○を書いたらと戸惑っているご様子に、従来にも増して○について興味尽きない関心を新たにしておりました。本当はマルコ塾にしたかったのだが一寸・・・という事由も分かります。あなたが「哲学者」と称し愛してやまない老犬マルコのことですね。しかしそのマルコこそあなたの根源の理想だとしたら、マルコのように心無にして自然に○を書けばいいのです。
確かに○は古今東西南北、特に東に於いて様々の意が散在しています。開塾に当り第一日目はその○についての由来、解釈等々で終始するのではないでしょうか?受講される方も何故○なのか、○とは、と自ら深く考える姿勢があるか否かで相当の差異が出て来ると思います。
熊谷守一から『れ』と題する“太陽”を描いた油絵をもらった白洲正子氏の談によれば、熊谷先生曰く「『れ』となっていますが、これは私の自画像です。心象風景というやつです」と言ったそうです。この話は「ものを見る」ということを心掛けている者にとって含蓄のあることばであります。○について先に申した様にあちらこちらに散らばっているのを並べることは大した労を要しません。指二つ曲げておかね、なんていうことも(少々私には好ましくないムードではありますが)、かたや遠大な意味あいがキラ星の如く有るのは、ご存知のことでしょうが、書としての「丸」は狭義には五輪の中の「水輪」にあたるそうで、これを一つの「円」と解すれば、地・水・火・風・空の五大要素に擬することも出来るし、その他大日如来、天照大神でもいい、宇宙や悟りの境地の象徴と見ても差し支えないものではあるまいかと、又晩年の守一に、気負いのない境地から「丸を描いたから『日輪』とでもしておけ」と云わしめた作品もある。いずれにしても書としての「丸」は絵画では表現し切れぬもの、はみ出してしまう意味合いをもって描かれ、絵画としての「丸」も単なる天体の一つである太陽を描いたものではないでしょう。いろいろ思い巡らせば無限が実存しているような感じがします。
あなたがここ何年かの、肉体的、精神的軋轢とも云える中で私はそれこそ「山が動いた」の感動を持って見ています。
「喰う」という人間として最もベーシックな部分を軽視することなく、全てを等価としてとらえているあなたの「生と死」への粛々たる思いが痛い程伝わって来るのです。
凄い底力です!電光石火の早業で惰眠を貪る私を串し刺しにするのです。
あなたは真に「等身大に生きる」ということを悟られ、それはまさしく至福への扉が開かれたということです。
五十六歳、まだまだ全細胞はその情熱のエナジーで起立し揺れ舞うことでしょう。病すら命と同義とし、且つ静かなる風の流れに身を委ね、ゆっくりと純白の花を咲かせて欲しいものです。折角の美しいホワイトのキャンバスに何やら描いて汚さないと気がすまない人間の甘ったるさを残しつつ、茫々たる大洋を出帆なさいませ!!
’98. 2.25
M.E.
ここに励ましのお言葉をいただいたのは、遠田先生の幼い頃よりのご友人にして画家、○塾後援者の江川様でございます。まことにありがとうございました。〔編集者〕
瀧口 公明
謹啓
アメリカ南西部では記録的な寒波だとか。その分日本が暖かいのでしょうか?ずいぶんご無沙汰いたしておりますが、お元気そうでなによりのこととお慶び申し上げます。
新春早々楽しいモノを頂戴いたしました。○塾の講義と内容に非常に興味をもって、「塾機関誌創刊号」を一気に読ませていただきました。
機関誌として素晴らしい出来に仕上がっていました。
前半の講義概要で、第1回から第5回までの内容やテーマと議論された内容までがよくまとめられていました。私自身は教材に利用された映画やビデオはどれも見たことがないようですが、見たことがあるような感じに少なくとも一回は見てみたい気持ちにさせる報告でした。
勿論、レポータ各氏の講義のレポートの纏め方の手腕によるのでしょう。
後半の塾生感想において、塾での雰囲気がよくつかめ愉快でした。別々のキャラクターが垣根のない交流でより高次元のキャラクターに成長していくという、いわば「弁証法的人間育成」――遠田先生得意の教育方法だと心得ています。
ところで、法政大学遠田ゼミナール4期生を代表するキャラクターの持ち主の笠井にして早々に落第したという「○塾」。経済不況の中で企業人のほとんどが不安定な気持ちで目先の経済的な利害関係に右往左往している時代に(遠田先生が一番嫌う世でしょうが…)「○塾」に参加するというだけで「さすが笠井!!」と拍手を送ってやりたくなるのです。わが愛する友をかばうつもりはサラサラありませんが、笠井は0期生として卒業はできなかったかもしれないけど、他の0期生よりも多くのことを吸収しているに違いないと確信しています。
先生が夢見ていた塾の名前を知り感慨深いものがありました。
「○」は…何塾と読むのだろう?「ワ」-「マル」-「無」-「ゼロ」-「円」それとも「輪」」…。
昵懇にしていただいている禅宗の和尚から掛け軸のこの字を見て、読み方にこだわると意味を取り違えてしまうと以前教えていただいた事があります。目先の事にこだわると本質を見失う。無の境地、円想=心、人と人、輪廻または宇宙万象総てのことを表しあるいはそれらに思いを巡らす奥行きの深い形(字)と言われたような気がいたします。悟りの境地といったものでしょうか。
私は先生がまだ若い頃からご指導いただく機会を得、その後もだいたい一年に一回ずつお出会いする機会をいただいています。若い頃の情熱ある姿から、落ち着いた現在の姿にいたるまで表面のお変りは人間として誰でも当たり前のことでしょう。でも、毎回お出会いする度に内面の変化というか先生の新しい魅力、それも必ず前回よりも高まった魅力に触れさせていただくことができます。それはいつも新鮮で人間臭いものです。駆け引きや飾りっけのないものです。
先生を慕っている遠田ゼミの卒業生のほとんどが感じていることでしょう。
学者らしくないといったら失礼ですが、自説にこだわったカチンカチンの自我の強い方ではありません。かといって、あいまいな風来坊のその場的な生き方でもありません。ましてや現在の企業経営者的な生き方である貨幣経済の損得に左右されたり、世間に対する見栄にもまた肩書きやへつらいを意識したそれではサラサラありません。
今回機関誌の表紙を見て、先生はマルクスとか唯物論とか唯心論とかいうのではなく、もっと人間臭い禅宗の高僧の悟りに近い「下町の悟り」を開かれたのかなあと思っています。「あいまい」という概念は混沌という意味ではなく、卓越した無の概念なのでしょうか。少なくとも私にはそう感じて仕方ありません。
最近、私は企業経営は自分自身の修行の場だと考える時があります。
企業経営で自分の力だけではどうしようもない他からの力(=お陰)を感じる時があります。かといって、神とか仏の加護というのではありません。
その他からの力は、人との出会いから始まったり、ちょっとしたきっかけであったりします。まさに「一期一会」によってもたらされるようです。
第4回講義のテーマになっている「人員削減」でも議論されたのでしょう。会社の存続のためには断腸の思いで給与や賞与のカット、あるいは人減らしに及ばざるを得ない局面も出てくるかもしれません。
しかしながら、それらを実行する時、自分の庇護であったり、自分の名誉のためであってはならないと思います。涙して自分を責めながら実行する時にその人は人一倍悲しんでいるのだと思います。また、成功したりチャンスをつかめた時、自分の力だけではない他の人のお陰だと思っている人は、自分を世の一員として捉え日頃人一倍の努力をしている人のようです。
そう考えると、企業経営(家庭での父親としての役割もそうなのかもしれませんが…)を通じて、人は生かされて人間的に成長しているような気がします。
経営学は哲学に構成されていると言及するのは過ぎたことでしょうか。
経営志林『点と線と図』の冒頭で先生がおっしゃっている「環境についての認識が悪しきもとでは、意思決定が「良き」ものであればあるほど悪しきものとなる。」という言葉を、その友を思い浮かべながら反芻しています。バブルという異常な経済社会を経験した経営者の多くが、自分たちのなした意思決定の結果に思惑違いと思っているのかもしれません。環境の変化まで認識し予測する必要があったのでしょうか。
いかんせん意思決定にはそれなりの結果をともないます。不良債権を抱えて苦境に陥った銀行の責任者が「右肩上がりの経済成長がいつまでも続くと思い込む環境認識の下では、格別に悪しき意思決定ではなくむしろ整合的な良き意思決定でさえあった」と言い訳をしても、世間の物笑いの種になるだけなのかもしれません。
しかしそういう結果は一つの事象であって、大事なことは意思決定をした自分に責任をとり、その結果を正面から受け止めることなのかもしれません。そうすることで人間として成長するのかもしれないと思います。そういう意味では結果が明確な経営における意思決定では、決定後の過程は人間成長の修行の場と言えるかもしれません。
こういう時代だからこそ自分が大きなものに生かされていると思って、「○」の境地で今後の経営にあたれればと考えているところです。少なくとも遠田先生から多くのことを学ばせていただいた者として、「下町の悟り」に少しでも近づくようにと思っています。
最後に、愛する笠井のためにもう一度、「○塾」には笠井もいるから○塾」らしいのでしょう。
模範解答の優等生ばかりでない多面的思考のアメーバーのような逞しい人材を育てる場所として、「○塾」のますますのご発展とご盛会を祈念しています。
上京の折、機会があれば是非参加したいと考えています。
屠蘇にて酩酊思考です。どうぞ失礼の段、お許しくださいませ。
敬白
平成
11年1月
㈱武蔵交通社長、遠田ゼミ第四期生
瀧口 公明
遠田先生、このたび遠田塾開設おめでとうございます。
あの
30数年前の美少年の遠田君とはとても思えない程出世なされ、今では大学の教授として御活躍なされているそうです。映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に出ているマイケル・J・フォックスといったイメージの少年でした。上野高校へよく二人で自転車通学していたのを思い出します。先生は現在は経営学の教授、私はその実践者です。若い頃は会社をつぶしたこともあり、色々と苦労もしました。ペイント業、照明器具製作、宅建業、飲食業と色々やってきましたが、今では呑み屋のおやじとなりました。でも、決して後悔していません。色々な職業の人たちと知り合い語らい、金持ちも貧乏人も警察官も共産党の人もやくざ屋さんも皆同じです。それぞれの人たちの人生をうかがい見ることができました。
色々と映画を見ているのと同様ではないかと思っています。遠田塾のご趣旨に私は賛同致します。心から益々のご発展をお願い致します。
居酒屋「関宿」の由来
私の父が千葉県北端五万八千石久世大和守の関宿城のあった地の出身で私自身野田市市川間に小学
2年まで住んでおりました。その後、現在の入谷に出てきまして、昭和41年喫茶ロダンを開業、昭和56年居酒屋関宿を開店しました。関宿店は豊富なメニューと低料金でお客様に御奉仕しております。地下鉄日比谷線「入谷」駅から
2分と近いので「関宿」は入谷の関所です。当店自慢の特性煮込み、ぜひ御賞味下さい。お酒は色々とおいてありますが、当店オリジナル関宿寒梅がお勧めです。なお当店2階はカラオケスナック「ロダン」をやっております。メニューは関宿店と同価格ですので、ごゆっくりとカラオケを楽しんでいただけると思います。
台東区北上野
2-31-6 ℡03-3844-1003 居酒屋 関宿 因田俊一○塾後援者
Ⅰ ――お役人様編――
綿引 宣道
今私が生活している
A県H市は、本州のかなり外れに位置している。ここの地域の特性は、果樹の栽培で日本一を誇る。地平線まで、水田と果樹園が広がる地域である。工業都市に生まれ20年近く、多摩地区とはいえ東京に出て10年近く過ごしてきた私にはどうしても理解できなかった現象がたくさんある。目からうろこが何枚も落ち、もはや再生不能である。その一つが公務員至上主義である。経営学を教える立場としては、少々哀しいものがある。
ここでいう公務員至上主義とは、学生の憧れの職業というだけではなく、公務員が絶対的な影響力を持つのである。公務員=士族、民間=百姓という明治時代の官僚制度であるかのようである。どうやら不景気のせいだけではなく、一度も人気就職先として民間が公務員を追い越したことがないようだ。その一つに給与格差の問題がある。県内では、みち銀、青銀、公務員(韻を踏んでいるところがオシャレ)、放送局の順番で高い。しかし、都市部に住んだことのある人間からは想像がつかないくらい、銀行との給与格差は殆ど無い。実際に、仕事量対賃金を見て、銀行員から公務員になるケースも少なくない。
私がここでアパートを借りるときに勤務先を書いたが、そのとき大家さんから「なあさ、けっぱったなあ(邦訳:あなたは、随分頑張りましたね)」と言われた。勤務時間の話になって(少なくとも私はその話をしたつもり)、どうも会話が成立しないことがかなりの時間が経って分かってきた。その後に続く会話(8割理解不能)から、どうやら私が事務部門に採用されたと思っているらしいことが何となく分かった。現地語があまりにも難しいので、そういう事にしておいた。
翌朝、車を見て驚いた。買ってからはや4年経つが、その間に数えるほどしか洗ったことの無いカローラがベンツのように光り輝いていたのだ。その後も農産物を山ほど貰ったり、食事に誘われたりとお大尽様を満喫できた。
話は変わるが、私には師匠がいっぱいいる。(中には、私が就職してから自称師匠になったのもいる)その自称師匠からの命令で現地の企業を調査することになった。実はこれが困ったことに、我々が習ってきた経営学を活かせる企業が無いのである。
ここでは、「顧客満足」「競争優位」「品質管理」「企業のビジョン」と言う言葉は、遠く彼方の外国語でしかない。まさに、15年前のお役所と何ら変らない。一番愛想がいいのは、いわゆるジャンクフード・チェーン店の高校生のバイトである。
地元資本の企業そのものはあるのだが、中央統制下にある戦時下の企業(または共産主義国家)と同じように、県を中心に市町村の指示で動く企業ばかりなのである。また、企業もそれを強く望むのだ。農村では、地域の人は何代か前にさかのぼればみんな親戚であり、一族の優等生が公務員になるようだ。彼らの指示に従えば、決して儲かりはしないが、企業はなんとか飢えをしのぐことが出来る構造になっている。
このことを皮肉ったものを、地元新聞に投稿してみた。大学の事務官からは煙たがられたものの、実に効果てき面だった。私が事務官ではなく教官である事が、大家に知られるところとなった。大家の接待がぐっと良くなり、回数も増えた。私も、日の丸を背にまだまだお大尽を満喫できるだろう。
弘前大学経済学部専任講師
(〇塾通信受講生)
綿引宣道
『ミクロ・マクロ・ルーズ』
―認知的経済性アプローチによる創造性の分析―
熊谷智博
「一定のワク内の創造性は評価されるが、ワクから出るほどの創造性は周囲から制約を受ける」。浦先生の特別公演の中でも特に印象的であったのはこの一言でした。そしてその実例としていくつかの創造性ある人が足を引っ張られたエピソードをお聞かせして下さり、その時はとても納得していたのですが、しばらくして心情としてはとても良く理解出来る一方で、しかしなぜそういう事を人間は行うのだろうかという事に疑問を持ちました。そしてあれやこれやと想像してみました結果、こと個人の創造性発揮の問題ではなく現代社会の危機的状況へと想像が膨らんでしまったのですが、折角ですからこのことをレポートにしてみました。
なぜ創造性を持っていると制約を受ける対象となってしまうのか。まず嫉妬が考えられます。これは浦先生の公演の中では「男の嫉妬の方がよっぽど恐ろしい」とのこと。これも心情的には良くわかりますが、ここでは男女の性差は別としてもうちょっと穿った見方をすれば、例えば同僚が創造性を発揮して、それが評価された場合、相対的に自分の価値は低下するので、それに伴って自尊心も低下すると考えられます。もし自力で評価を上げることによって自尊心の回復ができないならば、同僚の評価を下げる事によって相対的価値を回復し、自尊心を回復しようという事が考えられます。まさに足を引っ張るということはこれに当たると思います。
そして嫉妬とは別に私が考えたのは認知的経済性が低いから、という考えです。認知的経済性という言葉があるかどうかは分からないのですが、ここでは何かを評価したり解釈したりするのが容易な場合は認知的経済性が高いと考えます。反対に困難な場合や他の人と協力して解釈を行わなくてはならないときは認知的経済性が低いを考えます。
そもそも創造性とは何かと考えると、創造性とは既存のものから逸脱してこそ知覚可能なものではないでしょうか。既存の何かとの対比の結果、何らかのズレや差といったもの、あるいは従来の自分の知識では理解が出来ない部分の存在を感じたとき、私たちは今までとは違った何かに対して創造性と言うものの存在を知る事ができるのだと思います。この差の部分をここでは創造性に限定せずにもっと広い意味で「逸脱」とします。
この逸脱に対して評価なり解釈なりを下すという事は、個人としても集団としても精神的または肉体的な労力を払って何らかのアクションを起こさなくてはならないと考えられます。なぜなら全くの意味不明状態では人は心理的に落着かないので、ともかく何からの理解の範囲内におこうとするために、自力で考えたり、調べたり、人に聞いたりする事が予想されるからです。しかしこういった労力を払わせる存在は、今までの効率的で安定した世界を脅かすのでポジティブな評価を受ける事無く、むしろ人は逸脱に対して何らかの制約を加える事によって従来通りの安定した世界を維持しようとすることが考えられます。これは例えば異文化の流入時や、あるいはもっと身近なものでは、いわゆる「不良」と呼ばれる人達もそうでしょう。
また、浦先生の特別講義では制約の方法として「色々経験させる」という足の引っ張り方が例にあげられましたが、これは逸脱する才能を発揮させないようにすることと同時に、レールの上を走らせておくことによって逸脱者が予測しやすくなり、認知的経済性が高くなるのを目的としている考えられますが、そのままでは露骨なので「あくまでもその人の将来を考えて」という自己正当化をして制約をするときの良心の呵責を低くするというやり方だと思います。
このような認知的経済性の観点からすると、「一定のワクの中の創造性は評価される」ことの理由も推測できます。例えば認知的経済性だけを追求すると世界は安定的ではあるけども、安定しすぎるのもシステムとしては危険な状態とも言えます。この危険を回避する為に刺激となるような創造性を必要としますが、一定の枠内の創造性ならば比較的容易に評価や解釈が可能で(既存の知識を利用しやすいので)、また修正も容易と考えられます。
つまり「毒にも薬にもなるのは飲むが、劇薬は飲まない」ということです。一見これは賢明な判断と思えるかもしれませんが、この事は社会が劇薬に耐えられるだけの体力を持っていないということの表われとも考えられます。即ち、日々の生活において肉体的にも精神的にも多大な労力を払い、その為に認知的労力を節約したいという現代人の実情があるのではないでしょうか。
その上不幸な事は、人の認知的経済性が高くなると、その節約した分だけの労力を社会(例えば会社)つぎ込み、そのつぎ込まれた労力を有効活用しようと社会も効率化を進める。そして今度は効率化された社会が人に更なる認知的経済性を求めるようになると考えられます。これを図にすると
人の認知的経済が高くなる
+↑
↓+社会が効率化
となります。これを社会的進化と見るか社会の悪化と見るかは意見が分かれるかもしれませんが、私は社会の弱体化ではないかと考えます。その理由は先にも述べた様に、この認知的経済性の効率化は劇薬すなわち急速な変化には耐えられず、もしそれでも対応しようとするならば、既存のシステムの一部を停止させなくてはいけないと思うからです。なぜなら処理能力が急速に変化する方法がない限り、変化に対応する分だけの処理能力を他の場所から集めなくてはならないからです。そして世の中には自然災害を始めとして私たちの予想を越えた事態というものが生じる余地は十分にあると言えるでしょう。だから創造性に対して制約を与えてしまうような社会は、個人の創造性発揮という不幸な問題も当然ありますが、同時に社会的状況としても危険な状態の表われなのではないかと思います。
ただし私がここで強調したいのは、私は認知的経済性それ自体が悪いものではないという点です。認知的経済性は人の生活をスムーズにするし、実際にはそれがなくては生活が面倒になるでしょう。私が言いたいのは、役に立つからといってその利用を進化させる事は必ずしもよりよい結果が待っているわけではないということです。むしろその進化が環境によって人間が強制される状況を作り出しかねず、人間の生き方に不幸な影響を及ぼしうるということです。
才能ある人に対するやっかみや妨害、あるいは嫉妬といったものは何も現代に始まった事ではないでしょうし、別に日本人特有の感情でもないでしょう。しかしながら日本がアメリカなどに比べで創造性や独創性を発揮しにくいのもまた事実で、それは現在の日本がまさに経済的発展の過程で必然的に生じた認知的経済性の追求の結果なのではないかと私は思います。
浦先生の特別講義に触発されて、つらつらとこんなことを考えてしまったのですが、私個人としましても、どうでもいいことに頭を悩ませるくらいの時間が持てる生活の方が理想的だと思います。皆さんは如何でしょうか?
さて、あなたのご感想は?
投稿をお待ちしてます。誌上討論をしてみるのもおもしろいのでは・・・。
ちなみに、わたくしの映画ベスト・スリー
――これは、稀少な仏教映画だと思います。
無明長夜をさまよう虚無の剣士・机竜之介。
その姿を通して、「生かされている」ことの喜び(よく聞く坊主の説教だが)なんかではなく、どうしようもない重さが伝わってくる。
――女のやるせなさと高峰秀子の艶が忘れがたい
1999.4.8 遠田 雄志
大谷地 初音
熊谷 智博 品田 貴子 品田 秀樹 平野 由美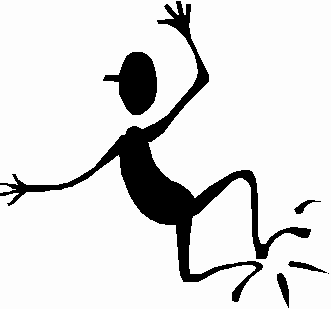
|
1.教養課程で最も印象に残った講義は何でしたか。 2.この塾はあなたにとってどんな意義がありましたか。 |
大谷地さん
1.○塾教養課程で最も印象に残った講義は何でしたか。
A:会津藩いつの時代でも、どこでも、どのような状態でも「組織」は存在することを、とても興味深く拝見しました。
中間管理職の方々に気苦労が耐えないのは、上下に板挟みされているからで、いっそのこともしそれが中間なくして上下だけだったらどうなるのでしょうか
....?上は自分自身で統率しなければならないという責任感が人一倍強くならざるを得ないし、下は自分自身がしっかりして自己管理をせざるを得ない状況になるしで、そんな状況下で、各人が自分より他人を思いやる、また協力的な気持ちを持つ事を忘れなければ、美しいと思うのですが......。しかしながら、それが大きな団体になってしまうと、上が行き過ぎて独善的な指導者になってしまうか、もしくは下が頑張りすぎて共和体制になってしまうのでしょうか。何がよいのかはその組織を構成してい人々の嗜好や、組織内の目標内容にもよるとは思いますが、どのような場合でも、心の片隅においておいた方が良いと思う事は、何にせよ組織は「人」が相手であり「人」には計り知れない「心」や様々な「情感」があることだと思いました。
会津藩の人々は、命は尽きてしまったけれども、自分たちの大きな目標である誇りを守ることに自らの命をたつことにより成功し、また一方で傍観者は「命」という基準で結果をとらえ、○→生きる、×→死ぬという定義を自然につけてしまい、事の顛末を悲劇と認識しているような気がします。
忠臣蔵にしろ今回の会津藩にしろ、本人達は忠誠心
/誇りと命を秤にかけたら前者の方が勝っていて(メンバーの中には、組織に自分の存在価値を見いだす為に無理矢理そう思いこもうとしていた人もいたかもしれませんが。)当の本人達は「志を全うする」事ができて成功だったのかもしれません。今の考えですと、せっかくそこまでして敵を打ったのに(成功したのに)割腹なんて(失敗)悲劇だ、と思ってしまいます。(私も実際そのようなTVを観ると、『かわいそうだ........。何も死ななくても........。』と思ってしまう一人ですが。)また、その際の講義で、先生のおっしゃった『のんびり亭主、しっかり女房』の図式が、事あるごとに頭に浮かび、その状況に当てはめて自分で納得して楽しんでおります。
2.この塾はあなたにとってどんな意義がありましたか。
A:学生時代に「あいまいさ」の利点を充分に学んだはずなのに、実際に組織に入り、様々な形式にがんじがらめになり自分自身も組織の「形式に守れらなければ不安」という状態をいつのまにか作りあげてしまっておりました。そして「組織の形式に守られる」と解釈している時点で自らを鎖で縛り付けていたことに気づかず数年を過ごして参りました。会社では、円滑に合理的に進める為につくられた「規則」がかえって「規則」をがんじがらめにしていたような気がします。
好きな仕事をしているはずなのに最近疲れを生じて、行きづまって、その週の疲れを週末にまとめて癒すという毎日を送っていたと思います。
そんな日々に、歯止めをかけて下さったのが遠田先生の○塾でした。忘れていた事を思い出させて下さったような気がします。(学んだ事は、実践で生かされなくては。)
○塾の講義はもちろんですが、その後の関塾の講義(?)も大変有意義で、命の洗濯をさせて頂きました。今回の講義を、自分自身机上の理論にしないためにも、大きな気持ちで毎日過ごして行きたいと思います。
また、利害関係のない中で、自分の父親や上司先輩後輩同僚と同じ年代の、多岐における年齢層の方々の率直なお話を拝聴できたのも、私にとってはよい経験となりました。このような講義にお誘い頂いて大変感謝しております。ありがとうございました。
熊谷さん
1.○塾教養課程で最も印象に残った講義は何でしたか。
どの講義でも強烈な影響を受けていたので、どれが一番と聞かれると非常に困るのですが、私は○塾に参加させていただいていた時、失業保険をもらっている正真正銘の失業者だったので、第4回の「リストラ」は個人的な事も関係していた分だけとても印象的でした。
もっとも私の場合は自分から辞めたので、一方的に給料を減らされたり、解雇されたり、退職に追い込まれたりする人の気持ちは理解できていないと思います。
ただ人間は集団で自分が適応する環境を自分で形成する能力を持ちながら、作り上げた環境が結局実力主義と言う名の弱肉強食の世界では、人間の能力ってそんなものなの?と悲しくなります。大体弱肉強食だって人間の目から見た理屈に過ぎないのかもしれません。
あるサル学の観察報告によると、サルは仲間に「渋々」食べ物を分け与えるとのことです。この「渋々」というのは今の時代にとても意味深いものではないか思います。
翻って「人間様」はどうかというと、「渋々」どころか、リストラだの実力主義だのという言葉を用いて、分けない事の自己正当化までしています。
「リストラ」というのは人間社会の行いの一つに過ぎないのですが、私は人間もサルの様に「渋々」を許容するような存在であって欲しいと思うし、またどういう存在でありたいかを考え、環境を「想造」できるものと自覚したいと思います。ただこんなことを考えられるのもやっぱり「失業者」だからであり、働いているときはこんなことを考えられなかったかもしれません。人間は自分が思っている以上に環境によって影響されるものですから。人間が自分自身の環境へ目を向けるだけの余力を残せない程働かされた挙げ句、リストラでは全くの悲劇です。歴史的に見てもこのようなことは何度かあったのでしょうが、そんな歴史を知っていながらこのような事をせざるをえないとすると、やっぱり私たちはとんでもない時代に生きているのかもしれないと考えさせられました。
2.この塾はあなたにとってどんな意義がありましたか。
遠田先生には長い間お世話になったので、世の中を面白おかしくみることが出来るようになったつもりだったのですが、いざ社会人となってしまうと、忙しさと、そういった非常識を許さない現実にぶつかってしまい、いつのまにか自分でもつまらない考え方に流されてしまっていた気がします。
そんな自分に不満もあり、その他諸事情から会社を辞めて失業者なったときに、ちょうど遠田先生から○塾からのお誘いがあり、喜んで参加したのですか、遠田先生の「“非”常識」は相変わらずショッキングで、しかもショックを受けてしまっているということもショックだったという有り様でした。
また参加者の多様さもとても刺激的で、なかなか得難い経験が出来たのでは無いかと思います。
その上、なんと○塾には成績が無い!このことが勉強の楽しさを再確認させてくれました。
思考の天秤が停止してしまいそうなときに、激しく揺り動かしてくれたのが○塾での授業だったと思います。これからも天秤はフラフラさせながらバランスをとっていきたいので、時には○塾にお邪魔して大きな重りを乗っけてもらいたいと思います。重りが重すぎて天秤自体がひっくり返るかも知れませんが…。
品田貴子さん
私にとって、この塾に参加することの醍醐味は、多様な職業の方々の話や考え方を聴けたことでした。また、同じ職業の中でも、社会的立場によって正反対の考え方があったりと、学生の私には見えないことがたくさんあることがわかりました。そのような方々の話はリアルで、実感がこもっており、時には生々しいときもありました。しかし、いずれ社会にでる私には、貴重な話が聞ける唯一の場でした。なかでも、インパクトが強かったのは、“リストラ”についてのことでした。“リストラ”のことについては、知った気分になっていましたが、実際の社会で起きていることは、思っていたよりも厳しく、残酷なものでした。その場では難しくて、御指名を受けたときにしか意見を言えませんでした。毎回そんなふうでしたが、とてもたのしく話が聞けました。そして、いつもお茶をいただき、ごちそうさまでした。
品田秀樹さん
○塾に参加させていただきましたことをまず御礼申し上げます。娘と一緒の参加は多少気も引けましたが、遠田先生初め、若い皆様の意見を聞くことができ、又会社以外の方と一時の時間を過ごすことに新鮮さを感じました。
私は現在銀行で支店長をしておりますが、日頃心掛けていることが
3つあります。1つは、「明るく楽しい中に緊張感のある職場をつくる」ということです。これは米国の映画で海軍が出てくる場面でよく出てくるのですが、司令官と隊員とのミーティングの様子です。自由な雰囲気、司令官と隊員との自由な意見交換、しかしミーティングが終りますと、上司と部下がそれぞれにわきまえた敬礼があります。企業の経営はこの様な上司と部下がわきまえた中に自由な雰囲気、自由な意見交換が欲しいものだと思っております。2つ目は行員を教育することです。教育といっても幅が広く、応接室でお客様へのお茶の出し方から、融資案件の取り上げスタンス等色々です。行員をいかに教育するかが、支店の総合力アップに繋がると考えるからです。3つ目は、「部下行員の為に何をしてあげられるか」を考えることです。これは公私にわたります。現在管理は全てコンピューターによってされています。営業の行動管理、顧客管理、事務管理、紙は無くなり通達、資料、報告書等はすべて電子メールです。加えて全く過去にないスピードが要求されています。スピードがこれからの企業が生き残るか否かにかかっていると考えられているからです。しかしそこに忘れてならないものは、我々は「心を持った人間」であるということではないでしょうか。せめて
1支店だけでも「明るく楽しい中に緊張感のある職場」としたいものです。○塾に参加させていただきました感想とかけ離れた内容となりましたことをお詫び申し上げ、最後に、○塾の益々のご発展を心よりお祈り申し上げております。
平野さん
【1】○塾教養課程で最も印象に残った講義(Ⅰ・Ⅲ・Ⅴのみ出席)
Ⅲ.組織の認識、映画『八甲田山』です。二つの部隊を同時期に対比させながら映し出す事によって、それぞれの組織の意思決定の違いが鮮明に分かりました。映画ではあらゆる場面で意思決定を行わなければなりませんでしたが、その時の組織の認識の違いによって最後には二つの部隊の生死を分けた結果となり、改めて意思決定の重要性を考えさせられました。また、この講義ではいくつかのグループに分かれて論じ合いましたが、そういった場が持てた事も良かったと思います。
【2】私にとっての○塾の意義
私にとってはこのような場に参加できただけでも大変有意義なことでした。仕事を辞め家庭に入ってからは日々の雑事に追われ、勉強する時間どころか一人で何かに熱中する時間すら持っていませんでした。でも○塾に参加することによって、そのような時間が持て大変貴重な経験ができました。機会があればまた参加させていただきたいと思っています。
この4月より私もとうとう職場復帰することになりました。と言うのも娘、美月の保育園入園が急遽きまったのです。(キャンセルが出て空きが出たそうです。)職場復帰はしたいものの、まだ子供と一緒にいたい気持ちもいっぱいあってちょっと複雑な心境ですが、とりあえず頑張ってみたいと思います。(まずは職探しから頑張ります。)それでは先生もお体に気を付けて頑張って下さい。
マネー革命を超えて
――遠田 雄志――

遠田 雄志
Ⅰ.マネー革命
1989年以降、60億中55億人が市場経済体制ⅰ.空間:
24時間しかも濃縮された。ⅱ.時間:時間がコンピューター・ネットワークによって、
ⅲ.純度:生産・サービスなどのまだろっこしい手段をカットして、直接マネーがしかもバーチャル・マネーが自己増殖
Ⅱ.その結果
ⅰ.アメリカン・ドリーム、自助努力というものの、アメリカの
ⅱ.勝者は金融のみで、産業は停滞
ⅰ.投機筋や格付会社あるいは無責任なウワサや思惑によって、一国の経済がしかも突然、危機に
ⅱ.バーチャルゆえの制御不能
ⅰ.弱肉強食:弱肉は失業、機会損失の不安に脅かされる――恒産なくして恒心なし――。強食も一夜にして弱肉になる確率高い(LT社)。隣の強食――恒産あっても恒心なし――。
ⅱ.価値あるから生きてよい:無価値はコストでやっかい者
ⅰ.企業は生き残るために浪費の創造:女子児童用化粧品、下着。雇用創造のための電算・通信技術開発も?
ⅱ.静脈産業というものの(例.根来靖)
ⅰ.外的:自然の有限性
需要の無限創造はやがて自然の有限性に
ⅱ.内的:a.秩序破壊――犯罪、学級崩壊.b.アノミー(政治的無関心).c.生命観――価値なき者は無用の存在(だから臓器移植か?).d.如意化(電子熱帯魚)飽食ゆえの生命力の弱化、生命工学による生命のいじくり――.
Ⅲ.大転換
「人は自らが順応する“事実”とみなす現実を創造する」。現在の困難は人が自ら招いたものなのだから、自らが克服することもできる。
理論・モデル・主張の自己成就性
Cf.『熱帯雨林と共生』’97, 90’, 74
ⅰ.合理モデル
vs ゴミ箱モデルⅱ.タイト・カプリング(効率)
vs ルース・カプリングⅲ.マーケット;ネットワーク
vs いち(祝祭)Cf. 『昭和60年時代を読む山崎・中沢』45’
’99, 60’, 547)。センスメーキングにおける語い、イデオロギー。ⅰ.環境をイナクトする:所与・客観的思考からの解放(「太郎・次郎物語」)。他由から自由へ。やってみなはれ(たとえば地球通貨『M.エンデのお金』
ⅱ.損得からの解放
Cf. 渡辺和子.
近ごろ、こんなことを考えているんです。
たとえばこんなものをタタキ台にして、みんなで理論というものをつくってみませんか。興味ある人は、「○塾シンクタンク」(仮称)に集まってやってみましょう。
1999. 5. 5. 遠田
遠田先生、加藤先生の暖かいご指導と適切なご助言をいただき、前号に引きつづき、今回もまた編集に携わらせていただきました。
○塾創設以来、さまざまな方が○塾を訪ねられ学んでゆかれましたが、この第一期は参加者の方々の多様性がたいへん増し、それだけ○塾の土壌はいっそう地味豊かになったのではないかと思います。今号の編集を担当させていただいたことで、その豊かさに再度驚かされ、○塾の多様性を実感し確信に至ることができました。一見多様なものの中に繰り返し現れる一貫したパターンを認識できたときには嬉しさと共に何らかの満足感が得られるものですが、この○塾を構成するさまざまな言葉の中にあえて一貫性を求めてみるのは野暮なだけかもしれません。
○塾という営みそのものである両先生の豊かさと確かさ、質の高い映像群や物語、下町をゆったりと流れてゆく土曜の昼下がり、そうしたものの中にそれぞれが宝物を見つけ、また宝物を持ち寄ってきて下さる、それがいまの○塾の姿なのかもしれません。もともと形なきものに形を与えようとするのは野暮な作業ではありますが、これからもそのときそのときの○塾の姿を記していくこと、この仕事にいっそう励んでいきたいと考えております。
(○塾編集担当 西本直人)
|
○塾機関誌 第1号 (非売品) 1999年 6月 1日発行 発行 遠田雄志 〒111-0031 台東区千束 2-19-2 編集 ○塾機関誌編集委員会 編集責任者 加藤敏雄 印刷・製本 ○塾機関誌編集委員会 |