�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v���_
�@�@�\���@�_�Ɖ\���\
�a�c���F
�@�@�@�ڎ��i�\��j
���́@�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v
�@��P�߁@�@�Ƃ͉����|�u�@�v�̑��l�Ȓ�`
�@��Q�߁@�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_�|�i�������w�E�i���S���w�E�]�Ȋw
�@��R�߁@�i�������w�Ƃ��̋ߔN�̔��W
�@��S�߁@�i���S���w�Ƃ��̋ߔN�̂߂��܂������W
�@��T�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�u�@�Ɛi���S���w�v�����āu�@�Ɛi���w�v�̉\��
��P���@�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_
��P�́@�@�Ƃ͉����|�u�@�v�̑��l�Ȓ�`
�@��P�߁@�u���R�@�v
�@��Q�߁@�u�@���؎�`�v
�@��R�߁@�u�@�v�̐V���Ȓ�`�|��Ɖ���
�@�@�i�P�j�u�@�v�̐V���Ȓ�`
�@�@�i�Q�j�����i���ɎЉ�����j�ɂ�����u�@�v�̑���
�@�@�@�ia�j����P�|�쒷�ނ̎Љ�W�c�ɂ����郋�[���Ɛ���
�@�@�@�ib�j����Q�|�~�c�o�`�̎Љ�W�c�ɂ�����s���p�^�[���i���E����H�j
�@�@�i�R�j�q�g�́u�@�v�Ɠ����́u�@�v�|���ʍ��ƍ���@����ɒ��ڂ���
�i�ȏ�w�@�w�u�сx��107��4���j
�@�@�i�S�j�{�e�ɂ�����ۑ�̊m�F�|�u�@�v�̐V���Ȓ�`�̑Ó���
�@��S�߁@��_�|�u�����v�̐V���Ȓ�`
�@�@�i�P�j�u�����v�̐V���Ȓ�`�|�����l�ފw����̉��
�@�@�i�Q�j�����i���ɎЉ�����j�ɂ�����u�����v�̑���
�@�@�i�R�j�q�g�́u�����v�Ɠ����́u�����v�|���ʍ��ƍ���@����ɒ��ڂ���
��Q�� �u�@�Ɛi�������w�v���_
�@��P�߁@�i�������w�Ƃ��̔��W
�@�@�i�P�j�_�[�E�B���̐i�������w�Ƃ��̔��W�|���R�����i���R�I���j�E�������i���I���j
�@�@�i�Q�j�_�[�E�B���́u�������i�I����j�v�Ɩؑ��������m�́u�������v�i1968�N���\�j
�@��Q�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�̉\��
�@��R�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�̎g���ƌ��E
��R�� �u�@�Ɛi���S���w�v���_
�@��P�߁@�i�������w�Ƃ��̋ߔN�̂߂��܂������W
�@�@�i�P�j�u�S���J�[�h���v�ɂ�����ACosmides�̉���I�Ɛ�
�@�@�i�Q�j���ۂƋ^�`�|2009�N�x��HBES�̑S�̉�c�ł�Stearns�����̔��\
�@�@�i�R�j�u�e�B���o�[�Q���̂S�̂Ȃ��v�Ɛi���S���w�ɒ悳�ꂽ�^��
�@��Q�߁@�u�@�Ɛi���S���w�v�̉\��
�@��R�߁@�u�@�Ɛi���S���w�v�̎g���ƌ��E
��S�́u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƈ�`�w�v
�@��P�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƈ�`�w�v�O�҂̑��݊W
�@��Q�߁@�u�i����̓����i�I���j�͌̂̈�`�q�ɒ��ړ����v
�@�@�i�P�j���`���[�h�E�h�[�L���X���w���ȓI�Ȉ�`�q�x�Ƃ��̉e��
�@�@�i�Q�j��_�@�������Ƃ��Ắugroup
selection���W�c�����i�I���j���v�i�f�B���B�b�h�ES�E�E�B���\��
�i�ȏ�w�@�w�u�сx��108��1���f�ڗ\��j
��R�߁@��`�q�ɂ���ē`��铮���E�q�g�̍s���H�|�u�s����`�w�v
�@�@�i�P�j��`�q�ɂ��`��铮���E�q�g�̍s�����x���鐶���I���J�j�Y��
�@�@�i�Q�j�u�s����`�w�v�E���̉\���E���E
�@�@�@�ia�j�s����`�w�Ƃ͉���
�@�@�@�ib�jPlomin�̍s����`�w�A�������N�̑o��������
�@�@�@�ic�j�u�@�ƍs����`�w�v
�@��S�߁@�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��q�g�̍s��
�@�@�i�P�j�q�g�̍s���͂ǂ��܂Łu���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��̂��H
�@�@�i�Q�j�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��i�H�j�q�g�̍s���̎���
�@�@�ia�j�����ɂ��j���́u��v�̑I�D��
�@�@�ib�j�����ɂ��z������̑I�D�Ɛ�������
�@��T�߁@��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�ɂ���ē`������铮���E�q�g�̍s��
�@�@�i�P�j�����́u����v�s���ɂ��������|�`���p���W�[�ق�
�@�@�i�Q�j�����ƃq�g�ɂ�����u����v�̈ٓ��|�u�i������w�v�̎���
�@�@�i�R�j��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�E����ɂ���Ă��`�������q�g�̍s���i��O��j
��T�́@�u�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�|��_�i�P�j
�@��P�߁@�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�E�i���w�̐ړ_
�@��Q�߁@Oliver
Goodenough�̌���
�@�@�i�P�j�u�@�I���v���v�l���Ă��鎞�Ɏg���Ă���]�̕��ʂɂ��Ă̌���
�@�@�i�Q�j�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw��ʂɂ��Ă̌���
�@��R�߁@�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ɓu�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v
��U�́@�u�@�Ɛi���ϗ��w�v�|��_�i�Q�j
�@��P�߁@�u�i�������w�v�E�u�i���S���w�v�E�u�i���ϗ��w�v�O�҂̑��݊W
�@��Q�߁@�w���ƌ���
�@�i�P�j����P�|����y���w�i���_�Ɨϗ��x�i���E�v�z�ЁA1996�N�j
�@�i�Q�j����Q�|�����~�w�i���ϗ��w����|�u���ȓI�v�Ȃ̂����ǁA�������x�i�����ЁA2009�N�j
�@�i�R�j����R�|�ɐ��c�N���w��������̗ϗ��w����x�i���É���w�o�ʼn�A2008�N�j
��V�́@�����|�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_�i�ȏ�w�@�w�u�сx��108��2���f�ڗ\��j
��Q���@�u�@�Ɛi���w�v
��P�́u�@�Ɛi�������w�v
�@��P�߁@����ƌ���
�@��Q�߁@�\��
�@��R�߁@���E
��Q�́u�@�Ɛi���S���w�v
�@��P�߁@����ƌ���
�@��Q�߁@�\��
�@��R�߁@���E
��R�� ���_�|�u�@�Ɛi���w�v�ƍ���̓W�]
�m�ȏ�ڎ��n
�m�T���ǎ҂̕��ց@����͖������Ă��������n
�m�ȉ��{���n
��P���@�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_
�@��P�́@�@�Ƃ͉����|�u�@�v�̑��l�Ȓ�`
�@�{�͂́A���N�ɂ킽��@�w�j�̒��ł́u�@�v�̒�`��ԗ����悤�Ƃ����Ӑ}�͊F���ł���B�P�ɁA�Ꭶ�I�ɁA�{�e�ł́u�@�v�̋c�_��[�߂邽�߂ɁA2�̖@�̒�`��U��Ԃ��Ē���ɂƂǂ߂�B
�@��P�߁@�u���R�@�v
�@�u���R�@�v�Ƃ́A�Ƃ肠�����ȉ��̂悤�ɒ�`�����F
�l�Ԗ��͐l�ԎЉ�̖{��(nature)�Ɋ�Â��Đ�������Ƃ����K�́B����@���A���̓��e�́A���ՓI�ŁA���̌��͂͐�ΓI�ł���Ƃ���邪�A�����̏��������C������咣������B���R�@�_�̋N���́A�w���j��͎��R�̐��`�Ɛl�ׂ̐��`����ʂ����A�I���O5���I�M���V���̎v�z�Ƃ����ɂ����̂ڂ�A�A���X�g�e���X�y�уX�g�A�w�h�̓N�w�҂����ɂ���āA����@�������R�@�Ƃ����ϔO�͌ÓT�I�ɒ莮�����ꂽ�B���̌ÓT�I���R�@�_�̎��R�ϔO�́A�_�̑n���������R�ƍĉ��߂���Ē����_�w�ɏ��p����A�����̓Z���B���̃C�V�h�[���X(Isidorus de
Sevilla, 560?�`636)�A�₪�Ă̓g�}�X�E�A�N�B�i�X��ɂ���đ̌n�����ꂽ�B�m�����n�m20�n���I�����ɗ��z��`�̕����ƂƂ��Ɏ��R�@�_���������������i�V���R�@�_�j�B���Ƀt�@�V�Y���Ƒ�2�����E���̏Ռ��́A����@���������̋K�͂ɑ���S�����N���A���̋���Ȑ��_�^���ƂȂ������A���_�E�̒��É��ƂƂ��Ɏ��R�@�ւ̉��^�_���䓪�����B���R�@�̑��ݖ��͔F���\����ے肷��v�z�͖@���؎�`�ƌĂ��B([1])
�@�����Ŗ{�e�����ڂ������̂́A�����������R�@�̌×�����̗���̒��ŁA���X�e�B�j�A�k�X1���i���e����: Justinianus I [���邢�͕\�L�Ƃ��Ă�Iustinianus I]483�N - 565�N�j���A�g���{�j�A�k�X�Ƃ���ψ��ɖ@�w�҂̊w�����W�听�����A533�N�Ɍ��z���ꂽ�w�w���b�[�x�ł���B
�@���̒��ɁA�ȉ��̈�����݂���F
��ꊪ
���@���`�y�і@�ɕt��
�m�����n
�O�@���R�@�Ƃ͎��R����̓����ɋ��ւ���@�����ӁA���̂ƂȂ���̖@�͐l�ނ݂̂ɓ��L�Ȃ���̂ɔC���ɐ������̓����y�ы̒��ނɂ����ʂ̂��̂Ȃ�Ȃ�B���Y�̌��������l�ނɉ���������鍥���͎��ɍ��̖@�Ɋ���̂Ƃ��q���̏o�����тɂ��̗{�疒�R��A���̂ƂȂ�Ό�l�̔F�ނ邪�@��������ʎ�ɖ�b��嫂������R�@�̒m�����o�����Ȃ�B([2])
�@�{�e�ł̖@�̒�`�͖{�́E��R�߂Ɍ�q���邪�A�����1500�N�قǂ��O�ƂȂ�A���X�e�B�j�A�k�X�̕Ҏ[�ɂ��w�w���b�[�x�̂��́u���R�@�v�̒�`�ƁA<�q�g�ɂ������ɂ��@������>�Ƃ����_�ɂ����ẮA�@������ɂ��邱�ƂɂȂ�B�����ɖ������Ă��������̂́A���̌�A���R�@���i�M�҂Ɍ��킹��j���ׂ����ƂɂȂ����A�����L���X�g���̃A�E�O�X�e�B�k�X�A�J�g���b�N�̃g�}�X�E�A�N�B�i�X([3])�́A�_�w�Ɋ�b��������`�E�T�O�́A�{�e�́u�@�v�̒�`���e����́A��U�A���S�Ɏ̏ۂ���B
�@��Q�߁@�u�@���؎�`�v
�@���R�@�ɑΒu����A�܂��Ɂu���R�@�̑��ݖ��͔F���\����ے肷��v�z�v���u�@���؎�`�v([4])�ł���B�@���؎�`�́A����������ȉ��̒ʂ��`�����F
����@������@�Ƃ���@�v�z�B�m�c�n���R�@�̖@������r�˂���_�ŋ��ʂ��邪�A���l�ȌX�����܂ށB�i�C�j����@�ȊO�̈�̋K�͂̌��͂�ے肷�闧��i���E�ϓI�@���؎�`�j�A�i���j�@�Ɠ�������ʂ��A�@�w�̑Ώۂ�����@�Ɍ��肷�闧��i�@�w�_��̖@���؎�`�j�A�i�n�j����@�ȊO�̖@����ے肷�闧��i�����@��`�j�ȂǁB�m�c�n([5])
�@�O�߂ł��łɏq�ׂ��Ƃ���A�܂����߂ō�Ɖ��������Ƃ���A�{�e�ł͂��́u�@���؎�`�v�̑ɂƂȂ�u�@�v�̒�`�ɏ]�����ƂɂȂ邱�Ƃ��A�����Ŗ������Ă��������B
�@��R�߁@�u�@�v�̐V���Ȓ�`�|��Ɖ���
�@�i�P�j�@�u�@�v�̐V���Ȓ�`�̎���
�@���łɏ��́E��P�߂ŏq�ׂ����A�{�e�ł́A�{�e�̖ړI��B�����邽�߂ɁA�q�g�̖@���A�����������Ɖ����Ƃ��āA�u�����Ƃ��Ă̓����̈��Ƃ��Ẵq�g�́A�i���Ɋ�Ղ����A�������E�s��������Ȃ��A�L�͈͂̃��[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�Ƃ���B���̒�`�ɂ��A�����݂̂Ȃ炸�A���݂ɂ����Ă��A�u�@�E�@���v�Ƃ�������̂̈ꕔ�����A��`����O��Ă��܂��̂͏\���Ɏ��o���Ă���B�������A�`���ɏq�ׂ��悤�ɁA�c���p�v�����������Ƃ���A�u�@�Ƃ������t��p����ɍۂ��āA������ǂ̂悤�ɒ�`����̂������I���v�����Ȃ̂ł���A�{�e�ł������܂Ŗ@���A�u���͂̓���Ƃ��čł��L���v�ɁA�@�\�I�E�ړI����I�ɒ�`�������Ƃ�͐����Ă��������B
�@�}�P�����Ă������������B�Ƃ肠�����A�����ł̓q�g�̖@�ɋc�_�����肵�悤�B�{�e�̖ړI�́A���݁A�u�@�E�@���v�ƌĂ����́i�W���`�j�̓��A�ǂ̕����܂ł��A�V���Ȓ�`�͈̔́i�W���a�j�ł���u�����Ƃ��Ẵq�g�̐i���Ɋ�Ղ����A�������E�s��������Ȃ��A�L�͈͂̃��[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�ɓ���̂��A���������邱�Ƃł���B���������āA���ړI�I�ɂ��̒�`�̉��ɁA�ȉ��̋c�_��i�߂Ă��������B
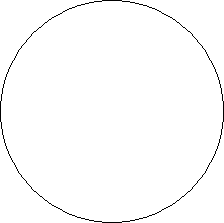
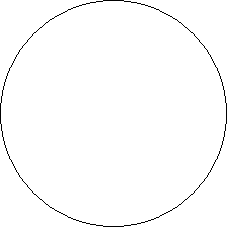 �W���`�������́u�@�v�̒�`�@�@�@�@�@�@�@�W���a���{�e�ł̐V���ȁu�@�v�̒�`
�W���`�������́u�@�v�̒�`�@�@�@�@�@�@�@�W���a���{�e�ł̐V���ȁu�@�v�̒�`
�}�P�@
�@�i�Q�j�����i���ɎЉ�����j�ɂ�����u�@�v�̑���
�@�u�@�v��O�q�̂悤�ɒ�`����ƁA�u�����̖@�v���`���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B���Ȃ킿�A�J��Ԃ��������ꂸ�ɏq�ׂ�A�u���̓����̐i���Ɋ�Ղ����A�������E�s��������Ȃ��A�L�͈͂̃��[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�ł���B
�@�����ł͂Q�̎���Ɍ��肵�āA���̍�Ɖ�������@�̒�`�̉��ł́A�u�q�g�̖@�v�Ɓu�����̖@�v���A�ǂ��܂œ������ɘ_�����邩�A�ǂ�����͏s�ʂ��K�{�����l�@����B
�@�@�ia�j����P�|�쒷�ނ̎Љ�W�c�ɂ����郋�[���Ɛ���
�@�쒷�ނ̎Љ�W�c�ɂ����郋�[���ƁA�ᔽ�����ҁi�����w�ł́u�́v�Ƃ����p���p����j�ɑ��鐧�ق̌����ɂ́A���Ȃ�̒~�ς�����B�{�e�ł́A�Ƃ肠�����A�쒷�ފw�ҁAFrans de Waal�i�t�����X�E�h�D�E���@�[���j��1980�N��Ȍ�̏��_�l�ƁA���{�̏��c���̌����ɒ��ڂ������B�i�Ȃ��A���̑�S�߂ł��_���邪�A�h�D�E���@�[���́A�����A���ɗ쒷�ނɂ��u�����v�����݂���ƍl���Ă���B�j
�@�h�D�E���@�[���͂܂��A1982�N�̒���AChimpanzee Politics: Power and Sex
among Apes([6])�ŁA�`���p���W�[�̎Љ�W�c�̒��ł͘A����g�ނȂǂ́u�����v���s����([7])�݂̂Ȃ炸�A���̃��[���̉��ɍs�����K������A([8])����Ɉᔽ����̂ɂ͐��ق��������([9])���Ƃ��A�ώ@�ɂ��������B
�@����ɁA�h�D�E���@�[���͑ΏƓI�ɁA1989�N�ɂ́APeacemaking
among Primates([10])�̒��ŁA�u�������������邽�߂̎��R�̃��J�j�Y�����A���܁A�^���Ɍ������ׂ��Ƃ��ł���v([11])�Ƃ��āA�`���p���W�[�A�A�J�Q�U���A�x�j�K�I�U���A�{�m�{�A�����čŌ�ɐl�Ԃ��Ƃ肠���āA�����̌�̘a�����ǂ̂悤�ȃ��[���̉��Ŏ�������Ă��邩���ڍׂɘ_�����B
�@�h�D�E���@�[���͂܂��A1992�N�ɂ́A�i�q�g�ȊO����������j�쒷�ފw�҂ƁA�q�g�̎Љ����������w�҂ƂƂ��ɁACoalitions
and Alliances in Humans and Other Animals ([12])��Ғ����A��������Ҏ҂�Alexander H. Harcourt�Ƃ̋�����"Coalitions and alliances: a history of ethological
research" ([13])�Ƃ���������������ŁA�P����"Coalitions as part of reciprocal relations in the Arnhem
chimpanzee colony"([14])�Ƃ����_������e���Ă���B�Ƃ��Ɍ�҂̘_���̒��ŁA�`���p���W�[�ƃq�g�̍s�����r��������([15])�ƁA���̐i���I�w�i���l�@��������([16])�͒��ڂ����B
�@����ɉ����āA�ނ́A1996�N�̒P���AGood Natured: The Origin of Right and
Wrong in Humans and Other Animals([17])�ŁA�q�g�Ɨ쒷�ނ��ɘ_���A�j�z���U���A�`���p���W�[�A�����ăq�g�ɂ�����A�����̑��݂Ƌ@�\�A�������i�����鏔�������w�E�����B([18])
�@�ߔN�A�h�D�E���@�[���́A�q�g�ȊO�̗쒷�ތ�������ՂɁA�q�g�̓����̐i���ɂ��Ē��ژ_�����_�������X�Ɣ��\���Ă���B([19])
�@���ɁA2009�N�̋�����Primates and philosophers : how
morality evolved�̒��́A�h�D�E���@�[���̒��߂̎�_���A"Morally Evolved: Primate Social Instincts,Human Morality, and
the Rise and Fall of 'Veneer Theory' "([20])�́A�ȉ��̓_�Œ��ڂ��ׂ��ł���F����́A�q�g�̒��ōł��d�v�ȓ����Ƃ���Ă��铹�����ɂ��āA�쒷�ނ̓����Ɣ�ׂ邱�ƂŁA�������̐����w�I��Ղ�T�낤�Ƃ������݂ł���A�쒷�ނ̎����I�f�[�^����Ȃ���A<�����I�Ȗ{���ɁA������������Veneer���킹���Ă��邾����>�Ƃ���'Veneer Theory'��ᔻ����iVeneer�Ƃ́A���{�ł����x�j���E���̏�ɒ������㎿�̔����w���j�B���̏�ŁA�����̍s���ƁA�q�g�̍s���̘A�����E�A�Ȑ�����������̂ł���B�{���ł́A���̎�_�����āA�����Ȋw�҂炪�R�����g���A����ɑ��ăh�D�E���@�[��������ɁA"Response to Commentators: The Tower of Morality"([21])�Ƃ������_���ŕԓ�����A�Ƃ����`������Ă���B�R�����g�̒��ɂ́A�i���ɋL�����j�����ȓN�w�҂ɕ���ŁA�L���ȃT�C�G���X�E���C�^�[��Robert Wright�̂���([22])������i�ނ�Moral Animal([23])�Ȃǂ̒���������j�B
�@�ȏ�̂悤�ȃh�D�E���@�[���̌����́A�ނ�����1�l��<�䂪�����s��>�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B�E�e��ɐڂ���2010�N1��19���̍ŐV���̋������AHuman Morality and Sociality : Evolutionary and Comparative
Perspectives ([24])�́AFrans de Waal���܂߂�������10�����A9�̘_���ŁA��Ƃ��āi�q�g�ȊO�́j�쒷�ތ��������2�_���ƁA�q�g�́i�i���j�S���w�A�����w�̕����7�_�������ځE���������邱�Ƃɂ��A�q�g�̓������ƎЉ���A�i���_�Ɓi�q�g�ȊO�́j�쒷�ނ̔�r�����Ɋ�Â������p���番�͂���A�Ƃ�����S�I�Ȏ��݂��s���Ă���̂ł���B����͂܂��ɁAFrans de Waal �����N�������������̌����Ƃ�������A�ނƌ��������i���邢�͋߂��j���錤���Ғ��ԂƂ̋������ƂȂ��Ă���킯�ł���B
�@���Ȃ킿�A�܂��A�{�����̕Ҏ҂ł���A�S���w�҂ł���Henrik Høgh-Olesen���A��1�_��(pp. 1-12)�œ������A�ŏI�E��9�_��(pp. 235-271)�ő������s���Ă���B
�@��2�_���ł́A�S���w�҂�Dennis Krebs��"Born Bad? Evaluating the Case against the Evolution of Morality" (pp. 13-30)�Ƃ����^�C�g���̉��ɁA�������̐i�������邩��_��(pp. 14-15)�A�����Ȑi�������w��George Williams�̒�������̈��p�ɂ��A�������܂��Ɂu��b�I�ȍs��(Beastly
Behaviors)�v������ǖʂ�`���o��(pp. 15-17)�B���������̔��ʁA�u�ꌩ�����Ƃ���ł͖��炩�ɗ����I�ȍs��(Apparently Altruistic Behaviors)�v�ɂ����ڂ�(p. 17)�A�����s�����i�����_�̒��łǂ̂悤�Ɉ����Ă������͂���(pp. 17-20)�B���̏�ŁA���Ȑ��ƁA�Ȑ����A�������Ƃǂ̂悤�ɊW���邩�������������(pp. 20-28)�A�v��Ƃ��āA�u���ȓI�ȁi�����ĔȓI�ȁj�`�̍s�����K�����郁�J�j�Y���́A���������ꂽ���胋�[���Ƃ����`�Ńf�U�C������Ă���B�l�Ԑ�(human nature)�Ƒ��̓����̐���(nature of other
animals)�𗝉����錮�́A�����̌��胋�[����ǂ݉������Ƃɂ���m�c�n�v(p.28)�ƌ��_�Â��Ă���B���Ȃ킿�AKrebs���Ade Waal���l�ɁA�q�g�Ɠ�����̐���ŗ������悤�Ǝ��݂Ă���̂ł���B
�@��3�_���ł́A���悢��Frans de Waal���o�ꂵ�A"Morality and Its Relation to
Primate Social Instincts"(pp. 31-57)�Ƃ����^�C�g���̉��A�������Ƃ��́i�q�g�ȊO�́j�쒷�ނ̎Љ�I�{�\�Ƃ̊W����_����Bde
Waal�́A�u��X�m�a�c���@�Ƃ肠�����q�g���w���n�����܂���P(good)�Ȃ̂��A��(bad)�Ȃ̂��Ƃ����₢�́A�i�v�̖₢�ł���B�v(p. 31)�Ƃ̈ꕶ�Ř_���N�����B�����āA�O�q��"Veneer Theory"��1974�N��Ghiselin�̌����ɂ��Ƃ���܂ők���ď��q�������(pp. 32-34)�A����̉ߋ��̌������u�����̉����v�A�Ȃ���Â��u������v�𒆐S�ɐU��Ԃ�(pp. 34-36)�A����ɂ͓����A���Ƀq�g�ȊO�̗쒷�ނɂ��u����(Empathy)�v������Ƃ��������j��Ȗ��ɏ��q����(pp. 37-45)�B�����āu�b�s��(Reciprocity)�v�̍��ڂł́A�`���p���W�[�Ɓi��Ắj�t�T�I�}�L�U���ł́A��q�W�ȊO�ł��b�s�����s����Ƃ�������̌������ʂ���������(pp. 44-46)�B�����ďd�v�Ȃ̂́u������(Fairness�j�v�̍��ڂł���B������de Waal�͎���̎��������ŁA�t�T�I�}�L�U���ɂ����́u�������v�̊��o�����m�Ɍ��Ď��邱�Ƃ�_����(pp. 46-48�A��q�̏��c�������p��������̌������ʂł���)�B�ȏ��O��ɁAde Waal���_�����ŁA�ڂ��q�g�ɓ]���A�u�������ƃO���[�v���̒����v�Ƒ肳�ꂽ���ŁA���l���̓N�w�҂̘_�����������ɏo������ŁA�����1996�N�̌����ŁA�l�Ԃ̓��������`���s���~�b�h���A��ՂƂȂ���̂��珇�ɁA�u���ȁv���u�Ƒ��E�����v���u�R�~���j�e�B�v���u�ꑰ�A��(nation)�v���u�l�ޑS��(humanity)�v���u���ׂĂ̐����v�Ƃ����\�������Ƌ������A����������������ʂ��Đ����ɕK�v�Ȏ����Ă���̂��Ǝw�E�������(p. 51)�A�u�q�g�̓������̐i���I���[�c��ے肵�A���̗쒷�ނƂ̋��ʂ̊�Ղ�x�O�����邱�Ƃ́A���m�O�q�̃s���~�b�h���w���n�̒���ɂ��ǂ蒅���Ă���A����ȊO�̕����́m����������ɂ��ǂ蒅�������ƂƂ́n���W���Ɛ錾����悤�Ȃ��̂��v(pp. 51-52)�ƁA�Ó����Ȃ��c�_���ƒf���Ă���B�����āA�u�����͓����I�Ȃ̂��H�@�ނ�������̓��m�s���~�b�h�n�̂������̊K�w�ɂ�����ƏZ�ݍ���ł���(occupy several
floors)�ƊȒP�Ɍ��_���悤�B���̍T���߂Ȓ�Ă������ۂ��邱�Ƃ́A�m�������́n�\���̑S�̂̎����A����߂ĒႢ���̂��Ƃ��������������炷�ɉ߂��Ȃ��Ȃ�B�v(p. 52)�Ƙ_��������ł���B
�@��5�_���́A274�łɂ킽��{�������̒��ł��Œ���60�ł̘_���őS�̂�5����1�ȏ���߂�B�܂��A���e����A�{���A�{�e�̑�P���E��R�́u�@�Ɛi���S���w�v���_�A���邢�͂܂��A��Q���E��Q�́u�@�Ɛi���S���w�v�ň����ׂ��_�l�ł���B�����w�҂�Michael Bang Petersen�A�i���S���w�҂�Aaron Sell�A�����Đi���S���w�̑n�n�҂ł����Ƃł�����2�l�AJohn Tooby, Leda
Cosmides�ɂ�� "Evolutionary
Psychology and Criminal Justice: A Recalibrational Theory of Punishment and
Reconciliation"�́A�@�w�A���ɌY���@�E�Y���w�̗��ꂩ��͊ʼn߂ł��Ȃ��^�C�g���ł���(pp. 72-131)�B�������A�{�_���ł́A��{�I�ɑΏۂ̓q�g�ɍi���Ă���B�������A�Ҏ҂�Høgh-Olesen�́A��1�_���̓����ŁA�{�_�����Љ�A���̑�5�_�����A�Ⴆ�u���Ƃ��Ă̍߉�(Crime as Exploitations)�v(pp. 87-91)�̋c�_�ɂ����Ă��A�`���p���W�[�̃R�~���j�e�B�Ԃł̓����ɂ����p�ł��邱�Ƃ��������Ă���悤�ł���(p. 6)�B
�@��6�_���ł́A�Ăї쒷�ފw�҂ł���Christophe Boesch ���A"Pattern of Chimpanzee's Intergroup
Violence"(pp. 132-159)�̃^�C�g���ŁA�R�[�g�E�W���H�A�[���Ŋώ@���ꂽ�`���p���W�[��4�̃R�~���j�e�B�Ԃł́A�E�C���܂ޕ�������̌��������ƍׂ��ɔ�I����(pp. 137-151)�B���̏�ŁA���_�����̋c�_�ł́A�q�g�̕����Ԃ⍑�ƊԂ̐푈�ƃ`���p���W�[�̕������r���āA�u���̂悤�ɁA�q�g�̓`���I�Ȑ퓬�ł̏P���E�}�P(raid)���L�͂Ɍ����邱�Ƃ́A�`���p���W�[�ɂ��ĉ�X���ώ@�����O���[�v�Ԃ̑��ݍ�p�E�s��(interaction)�ƈ�v����ƌ����邵�A���̂��Ƃ́m�q�g�́n�푈���`���p���W�[�ɂ��Ċώ@���ꂽ���ƂƉ��炩�̋��ʂ̏��N�������A�Ɛ�s�����҂�������Ă������R��������Ă���v�Ƃ��āA��s�����҂Ƃ��Ē�����Jane Goodall, Richard Wrangham�����̖��������Ă���(pp. 151-152)�B���Ȃ킿�����ł��A�`���p���W�[�́i�����j�s���̉�����ɁA�q�g�́i�푈�j�s��������A���̂Q�ɂ͋��ʊ�Ղ�����A�Ƃ���������������Ă���̂ł���B
�@�����Ȃ�ƁA��7�_���Ő����w�҂�Azar Gat��"The Causes of War in Natural and Historical Evolution"(pp. 160-186)�̃^�C�g���̉��ɁA�q�g�̐푈�̏������̎��R�ȁA����ɗ��j�I�Ȑi����_���Ă��邱�Ƃ��A��6�_���Ə��ڂ��邱�Ƃ������ƂȂ��Ă��悤�B
�@��8�_���ł́A�ĂсA�푈�Ɠ��������A�i���S���w�҂̑�Ƃ�John Tooby�ALeda Cosmides�ɂ���āA"Groups in Mind: The Coalitional Roots of War and
Morality"(pp. 191-234)�̃^�C�g���̉��ɘ_������B����͂���2�l�̘_�҂́A�q�g�𒆐S�ۑ�ɒu�����A�u�����̘_��(Logic of Conflict)�v�Ƃ������ڂł́A�T���̈��̃n�k�}�������O�[����A�`���p���W�[�ȂǁA�q�g�ȊO�̕������ϋɓI�Ɏ��グ�Ă���B���̏�ŁA�ނ�͑�5�_���ł��p����ꂽ"Welfare
trade-off ratio (WTR)"�Ƃ����T�O���u�i�{�e�ł͏ڏq���Ȃ��j��p���A�����̘_���͂���(pp. 194-197)�B�����ē���(Alliances)�ƘA��(Coaltions)�ɂ��ċc�_���@�艺���Č�A�u�������A�]���A�����ċ������čs������\�́v(pp. 213-)���A�O�q��WTR�̊T�O��p���Ȃ���_����̂ł���B���_�Ƃ��Ĕނ�́A�u�퓬�Ɛ������\�ɂ��A���̌����͂ƂȂ�i����̃v���O�����̏W���̂́A�q�g�̓������̌����͂ƂȂ�i����̃v���O�����̏W���̂ƁA�傢�ɏd���������v(p. 230)�Əq�ׁA����̂��̕���ł̌����̔��W�̉\������������̂ł���B
�@Henrik
Høgh-Olesen�̍ŏI�E��9�_���A"Homo Sapiens �| Homo Socious: A Comparative Analysis of
Human Mind and Kind" (pp. 235-271)�́A�{���̑����ł���B�ނ͖`���ŁA�u�q�g�Ɩ�b�̊Ԃ����r�R����̒n�}����邱�Ƃ́A�i���́A���ʓ|�Ȏd���ł���v(p. 235)�Əq�ׂ���ŁA�q�g�Ɠ������r����肪����Ƃ��āA������܂������A�q�g�݂̂̓������Ƃ���Ă������ꂳ�����A�����ł͂Ȃ������ɂ�����ɋ߂����̂�����Ƃ����c�_�����������Ă��邱�Ƃ��w�E����ipp. 236-239; �{�e�̎��̃~�c�o�`�̍��ڂł́A����ɂ��Ă̘_�q�ƑΗ�������)�B����ɁA�q�g�Ɠ����������N�}�[���Ƃ��āA�|�p�A�M�A�V������������ŁA���ƋZ�p(Technology)�ɂ��ẮA�q�g�ȊO�ɗႦ�C���J��N�W���A�`���p���W�[�ł��Z�p�ƌĂԂɑ������̂������Ƃ������B�����ɂ��Ắi�{�e�ł����߂Ř_����̂ł����ł͏ژ_���Ȃ����j�A�����̒�`���i���Ƃ���de Waal�̂悤�Ɂu��`�q�Ɉ˂�Ȃ��A�K���̍L����v�Ɓj���삷�邱�Ƃɂ���āA���ށA�N�W���A�ہA�i�q�g�ȊO�́j�쒷�ނ����������A�ƌ����ł��邱�Ƃ��w�E����B�Ō�ɁAHøgh-Olesen�́A�Љ�Ɠ������ɂ��ăq�g�Ɠ�����ɘ_���A�Ō�Ƀq�g�ƁA�q�g�ɍł��߂��`���p���W�[�Ƃɂ́A�܂��u�킸���ȍ��v������A�ƒ��߂�����(p.263)�B
�@����ɁA���{�ł��A���Ƃ��Ζ��É��H�Ƒ�w�H�w���y�����̏��c���́A1999�N�̒����A�w�T���̂��ƂF��r�s���w����݂�����̐i���x([25])�̒��ŁA����𑀂铮���E�q�g�̎��ő�̓����͂ǂ����炫���̂��A���n�I�ȃT���̔�����x������R�~���j�P�[�V�����͂��邱�ƂŁA�u�S�̗��_�v([26])�ƌ���̐i���̓���������Ǝ��݂Ă���B�ނ́A�}�_�K�X�J���̃����[�����ɋ����A�T���������ʼn���`���Ă���̂��A�����R�~���j�P�[�V�����̐i���Ɣ��B��_���A�R�~���j�P�[�V�����Ƣ�S��̊W�ɂ��čl�@������ŁA�쒷�ތ������u�V���Ȑl�Ԋw�v�ւƌ��т��悤�Ƃ��Ă���B�܂��A2002�N�ɔ��\���ꂽ�����́w����T���F�i������݂��l�̐S�x([27])�́A�O���̊S�̉�����ɂ���A�i���S���w�̍ŐV�̃f�[�^������g([28])���A�l�Ԃ��u����T���v([29])�ƂƂ炦�Ă���B���c�͂���ɁA2004�N�̒����A�w�q�g�͊��������ł���x�̒��ŁA�h�D�E���@�[���̃t�T�I�}�L�U���Ƃ�����Ă̔�r�I�m�\���������ƂŒm���Ă���T���̎��������̐��ʂ����p���A�u�t�T�I�}�L�U���ɂ������́w�������o�x������A�s�����Ȉ����ɑ���{��������Ă��邱�Ƃ������v���Ă��邱�Ƃ������A�q�g�Ɨ쒷�ނ̓�����([30])�ɂ��āA����ɘ_���悤�Ƃ������݂�������B([31])
�@�h�D�E���@�[���A���c�ȊO�ɂ��A�q�g�Ɨ쒷�ނɂ��āA����ɘ_���鎎�݂͂���B��⋌���͂Ȃ��A�@�ɂȂ��铹�����ɓ������Ę_���Ă���킯�ł͂Ȃ����AJared Diamond�i�W�����h�E�_�C�������h�j�̒����ȏ��AThe Third Chimpanzee ([32]) �́A�q�g���u��3�̃`���p���W�[�v�Ƃ��ĂƂ炦��Ƃ��납��_�������A�u�q�g��l�Ԃɂ������ƂȂ�ق�̂킸���Ȓ����Ƃ͂Ȃ����̂ł��傤���H�@�������̃��j�[�N�ȓ����͔��ɒZ���Ԃ̂����Ɍ���܂������A���̓I�ω��͂قƂ�ǔ����Ă��Ȃ��̂ŁA�l�Ԃ̏������A���邢�͏��Ȃ��Ƃ����̐��́A�����̂����ɂ��łɑ��݂��Ă����ɈႢ����܂���B�|�p�⌴��A�W�F�m�T�C�h��̗��p�Ȃǂɂ��āA���������ɂ͂ǂ̂悤�Ȑ�Ⴊ������̂ł��傤���H�v([33])�ƁA�����Ɛl�Ԑ��̘A�����ɂ��Ė₢�����Ă���B([34])
�@���������_�l�i���Ƀh�D�E���@�[���̏��_�l�j�ɂ���Ă݂�A�����A���Ȃ��Ƃ��쒷�ށi�̈ꕔ�j�ɂ́A�u�����̖@�v�����݂��邱�Ƃ��_����Ă���ƕM�҂͍l����B�ƂȂ�ƁA�i��q�̒ʂ�A�R�~���j�P�[�V�����̎�i�͑��X�����Ă��A�����⌾��������Ȃ������ɂ����āj�i���̉ߒ��łǂ̂悤�Ɂu�����̖@�v�����������̂��A��������A�u�����̖@�v�̐i���I��Ղ͂ǂ��ɂ��邩�A�͋c�_�ɒl����ł��낤�B
�@�@�ib�j����Q�|�~�c�o�`�̎Љ�W�c�ɂ�����s���p�^�[���i���E����H�j
�@�Q�ڂ̎���Ƃ��āA�Љ�����s�������Ƃ��āA�A����V���A���ƕ��я̂����~�c�o�`([35])��������B�O�q�̃`���p���W�[�Ƃ̔�r�Ō����A�~�c�o�`�̎Љ�W�c�̒��ł́A�q�g�ɋ߂��悤�ȁu�����v���s����Ƃ͂����Ȃ����A��O�I���ۂ̉��ł́A�u�����v�Ƃ��Ăт��錻�ۂ��ώ@����Ă���B���̏�ŁA���̃��[���̉��ɍs�����K������邱�Ƃ͍L���m���Ă���B([36])���Ȃ킿�A���X�I�̒��̈�C�݂̂������I�Ƃ��đI��ē��ʂȉh�{��^�����A�Y��������B���̃��X�I�́A�����I�i���[�J�[�Aworkers�j�Ƃ��ĎY���͈�����A�����I�̎q����āA�܂����B([37])
�@�������A�����������[���E�K���Ɉᔽ����A����������u�����v�ϓ����䂫�N�����̂ɐ��ق�������Ƃ��Ƃ����E���Ⴊ�A�~�c�o�`�̏ꍇ�ɂ����݂���̂͒��ڂɒl����B([38])
�@���ڂ����q�ׂ悤�B([39])
�@�@�ɂ��ʂ���u�����v�u�K���v�Ƃ����ϓ_����܂��q�ׂĂ݂悤�B
�@�����I�̗��������B���Ȃ��̂́A�����I�̑��݉����邢�͖I���i�����I�̗c���j�̑��݉��ł���B�i�����I��������Ɨ��������B���ĎY�����J�n���A�S�̂�30���قǂ̓����I���Y������Ƃ����ώ@�������B�j��ʓI�ȃ~�c�o�`�ł́A�����I�͌�����ł��Ȃ��̂ŁA�Y�܂ꂽ���͖������ŁA��������Y���z��B�i������A�t���J�ɂ���P�[�v�~�c�o�`�ł́A�����I�̑r�����ɁA����̓����I���[���������ĎY�����A�P�א��B�ɂ���Ď��Y�ł���G��ʂ̃~�c�o�`�ł͂��̐����͍��ՓI�ŁA����߂ĒႢ�m���ŒP�א��B�ɂ�鎓�����Y�ނ��Ƃ�����j�B
�@�������A����������ʓI�ȏɂ����āA���������B���A�Y�������铭���I������̂ł���B���p��ł́A�A�i�L�X�g�ianarchist�j�ƌĂ�A��`�ŗʓI��`�q�ɂ���Đ��䂳��Ă���\�����w�E����Ă���B�i������u�K���ᔽ�v�Ƃ݂邩�ǂ����́A�ӌ��̕������Ƃ���ł��낤���A�u���E����v�Ƃ�������ł��낤�B�����A�A�i�L�X�g�Ƃ������p�ꂩ����A�u�K���ᔽ�v�ł���u�����v���ۂƂ��đ����邱�Ƃ͉\�ł��낤�B�j
�@�������������I�ւ́u���فv�̑��݂Ɋւ��Ă͈ȉ����w�E�������B�Y�܂ꂽ���́A���̓����I�ɂ���Č��o����ď����i�H���j�����i�������p���worker policing([40])�ƌ���)�̂ŁA�u���E����v�ł͂��낤���A����Ӗ��ł́u���فv�Ƃ������Ƃ͉\�ł��낤�B([41])
�@�Ȃ��A�~�c�o�`�ƃq�g������I�ɋ�ʂ��ׂ��́A�~�c�o�`�͊m���ɁA���ԓ��Ŗ��̂��肩����C���瑼�̕����̌̂ւƓ`�B����A�W�̎��_���X�i��萳�m�ɂ́u�K�U��_���X(waggle dance)�v�Ƃ����j�A([42])�@�H�ׂ̍��Ȑk�킹���̋��([43])�Ȃǂ̕��G�ȃR�~���j�P�[�V�����̎�i��������([44])����A�u���̂悤�ɁA��̓I�ȏ�����������A���ۓI�ȏ��ɓ]���i�L�����j���ē`�B����R�~���j�P�[�V�����l�����w�L���I�R�~���j�P�[�V�����x�ƌĂԂ��A���̔\�͂��������͔��Ɍ����Ă���A�쒷�ނł̓q�g�̌���݂̂�����ɑ������A�����ł̓~�c�o�`���������̔\�͂����B�~�c�o�`�����̂��̂悤�ȋ����ׂ��\�͂��l�������̂��́A���݂̂Ƃ���S���̓�ł���v([45]))���̂́A�q�g�̂���ɕ��G�ȉ����E��������Ƃ͔�ׂ邭���Ȃ��A���́u�R�~���j�P�[�V�����v([46])�͂����Ă��A�u����v�����݂��邩�A�̋�ʂ������A�~�c�o�`([47])�ƃq�g�݂̂Ȃ炸�A���́i�쒷�ނ��܂ށj�����ƁA�q�g����ʂ���傫�Ȏ肪����̈�ƂȂ�A�Ƃ����̂������w�҂����̂قڋ��ʂ����F���ł���A�M�҂̗���ł���B
�@�ȏ�܂�����ŁA�~�c�o�`���m�̃R�~���j�P�[�V�����̔\�͂Ɋւ��āA�ȒP�ɐ������Ă����B
�@�~�c�o�`�́A��q�̂悤�ȃR�~���j�P�[�V�������A�P�ɁA�u��`�q�Ō��肳��Ă���\�́v�݂̂ɗ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�y�ʂȁu�]�v�Ŋw�K���鑤�ʂ����˔����Ă���B([48])��V�I�ɔ�����Ă��镔���ɉ����āA�w�K�ɂ���ďC���A�㏑�����镔���͑傫���̂ł���B�Ⴆ�A���̂��肩��`����~�c�o�`�̃_���X�́A���z�Ƃ̊p�x������ɒ�������A���p��Ō����u���z�R���p�X�v��K�v�Ƃ��邪�A���z�̓����ɍ��킹���s���̏C���ɂ́A��`�I�ɔ�����Ă�����̂����A�w�K�̕����L���ɓ����Ă���A�ƍl�����Ă���B�i��������A���z�^�s�ւ̑S�ʓI�ȓK�������A�~�c�o�`����V�I���Ƃ��Ď����Ƃɂ͈Ӗ�������Ƃ��Ă��A�����W�߂���̑��z�ɂǂ��K�p���邩�́A���̓��̑��z�����Ă���̔��f�̕����A�܂�o���̕����L���ɂȂ�킯�ł���B�j
�@�܂�A�~�c�o�`�̂��������R�~���j�P�[�V�����A�G�T�̂��肩�̓`�B�Ȃǂ́A��q�̂悤�ɁA�w�K�ɂ���Ċ�{���\�̓K�p�A�^�p���������Ă���Ƃ����悤�B
�@�Ȃ��A�~�c�o�`�̃Q�m����͂͊��S�ɏI�����Ă��邪�A��`�q�̉𖾂��܂����S�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂ŁA�X�̈�`�q�̋@�\�Ɋ�Â�����͂͗������Ă���B�i���̓_�A��r�̑ΏۂƂ��āA�V���E�W���E�o�G�ł͓���̈�`�q���m�b�N�A�E�g�����̂���o�ł��A����ɂ���Ɏ������͂��̈�`�q������Z�p���m������Ă���A��`�q�̋@�\��͂��i��ł���B����~�c�o�`�ł́A�m�b�N�A�E�g���������܂��������Ă��Ȃ��B��`�q�̔�������RNA�̓]�ʂ��}�������悤�Ȏ�@�͕����I�ɂ͉\�ŁC����ɂ���ē����`�q�̔�����W���A���̋@�\��ސ�����Ƃ���܂ł͂ł��Ă���B���������āA�Q�m���͓ǂ߂����̂́A�{���ɕK�v�Ȉ�`�q���Q�m����̂ǂ��ɂ���A�ǂ̂悤�ɔ�������̂��A���Ȃ킿�A�ǂ�Ȉ�`�q�Q�Ƃ��ē������Ƃ����ϓ_�ł́A�V���E�W���E�o�G�����ȂǂƔ�ׂė������Ă���B�j
�@�������A�~�c�o�`�̔]�Ȋw�̕���͂��Ȃ�i��ł���A���H������p���������ŁA����(sameness)���قȂ邩�Ƃ����u���̔��f�͊w�K�ɂ���ĉ\�ł��邱�Ƃ������ꂽ��A���Ȃ荂���̔F���\�����邱�Ƃ��킩���Ă��Ă���B�܂��A�~�c�o�`�̍q�s�V�X�e���inavigation system�j�Ɋւ��Ă����Ȃ�̂��Ƃ͖��炩�ɂ���Ă���B
�@�ȏ�̓_�����ׂĊ܂߁A���{�ɂ����ă~�c�o�`�̐��ԁA�u�~�c�o�`�̖@�v�Ƃ��ĂԂׂ��s���p�^�[���i�ᔽ�����ꍇ�̐��ق̗L�����܂ށj�A����Ƀ~�c�o�`�̃R�~���j�P�[�V�����ɂ��Ă̍Ő�[�̌����́A�ʐ��w�̍��X�ؐ��ȋ���([49])�����{�ł̑��l�҂ł��邱�Ƃ����̖{���ŕt�����Ă��������B
�@����ɁA�~�c�o�`�̍s���������ǂ�]�̉Ȋw�A���̐������J�j�Y�����x����s����`�q����͂��镪�q�����w�̑��l�҂Ƃ��ẮA������w��w�@�E���w�n�����ȁE�����Ȋw��U�̋v�ی��Y�����A([50])�����ċʐ��w�_�w���E���������w�Ȃ̍��X�ؓN�F�y����([51])����������B([52])
�@�Ȃ��A�~�c�o�`�̃_���X�ɂ��R�~���j�P�[�V�����́A��e�����~�c�o�`�̑�������𐳊m�ɗ��p���Ă��邱�Ƃ�2004�N�ɏؖ�����ď��߂āu����v�ł͂Ȃ��܂ł��A�����ʂ�u���m�ȃR�~���j�P�[�V�����v�Ƃ��Ẳ��l���F�߂�ꂽ�Ƃ����悤�B���̌�A�_���T�[�i�_���X�����Ă���~�c�o�`�j���������ɂ͂���Ȃ�Ɍ덷�����邱�ƁA��̕��ŁA����̃_���X���ς��Ă��邱�ƂȂǂ��킩���Ă��Ă���B([53])
�@���āA�M�҂������܂ŏW�ς����A�~�c�o�`�ɂ��Ă̐V���Ȓm���������Ă��Ă��A����̉ۑ�Ƃ��Ďc��_�������ŕ⑫���Ă��������B����́A�~�c�o�`�ƃq�g���r���鎞�ɁA�u�@�v�E�u�@���v�E�u�s���p�^�[���v�̋��ʍ��̗����ƁA�s�ʂ����˂Ȃ�Ȃ����Ƃł���B���݂܂łɏW�߂��m���ł́A���̐��m�ȏs�ʂ͂܂��s�����Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA����̉ۑ�Ƃ������B
�@�����ʼn�X�̊S�́A�u�@�v�E�u�@���v�E�u�s���p�^�[���v�̂ǂ��܂ł����ʍ��Ƃ��Ĉ����A�ǂ������ʕ��Ƃ��ďs�ʂ��ׂ����A�ł��낤�B�i�}2���Q�ƁB�j
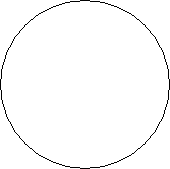 �@
�@
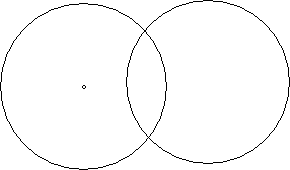
�@��
�s���p�^�[��
�@�@�}�Q
���Ƃ��A�ȉ��� 2�_�͎c���ꂽ�ۑ�Ƃ��A����̃~�c�o�`�����̔��W��҂��āA�𖾂���邱�Ƃ����҂������F
�@(i) �~�c�o�`�̍s���̂ǂ��܂ł́A��`�q�ɑg�ݍ��܂ꂽ�i��������A����������~�c�o�`���z���������̒i�K�ŁA���㑘������ł��낤��ʓI�Ȋ��̍���ɂ͍��E���ꂸ�Ɂj�A�u�{�\�v�ɏ]�����s���ł���A�u�@�v�ƌĂԂ��́A�s���́u�@���v�ƌĂ��̂ɂӂ��킵���̂��B
�@(ii)�ǂ͈̔͂́A�~�c�o�`������A����̊�����K�������u�s���p�^�[���v�ł����āA����ƈٓ��͂���Ȃ���A�ǂ͈̔͂��{�e�́u�@�v�̒�`�F�u�����Ƃ��Ẵ~�c�o�`�̐i���Ɋ�Ղ����A�������E�s��������Ȃ��A�L�͈͂̃��[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�ɏ]���āA�u�@�v�ƌĂт���̂��B�i���̍ۂɁA�~�c�o�`�̍s���́u���[���v��A���[���ᔽ�ւ́u���فv������Ƃ��Ă��A�u�s�K�́v������䂦�Ɂu�@�v������Ƃ܂Ō�������̂��B�j([54])
�@�Ō�ɁA�~�c�o�`�E�A�����܂ގЉ�����ɂ��ẮA�u�������̐i���v���獩���w�̐��Ƃɂ��_�����Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă��������B���Ȃ킿�A�{���ł��łɏq�ׂ��~�c�o�`����уA����workier policing ���܂ށA�u�Љ�����ɂ����鑊�݊Ď��v�ɂ��ẮA2008�N�̍ŋߎ��̌����́A���̂悤�ɁA�Љ�����ɂ����ẮA�u�����I�ȓ��@�ł���w�ǐS�x�w�������x�ށv�Ƃ����\������g���Ă���F
���[�J�[�|���V���O�m�a�c���F�{���Ŋ��o��worker policing�n���̓��[�J�[�̎��ȋ]���͑命���̓��E�����ɂ�苭�����ꂽ�s���ł���Ǝ咣����B����܂Ō��Ă����悤�Ƀ��[�J�[���݂̊Ď��s�����Љ�n�`�ڂɍL�����݂���Ƃ��������́A�u�����A���v�������ɐB�̕����ƎЉ�g�D�ւ̕��]���i���͊w�I�ɂ͎����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ނ��날���́u�������v����������W�c�I�͂̂��߂ł��邱�Ƃ��������Ă���B�������A�����̃��[�J�[�̎Y���̗}�����A�����w�I�Ɂi�i���͊w�I�ł͂Ȃ��j�����I�s�����������ꂽ�s���Ȃ̂��̋�ʂ͓���B�A���̃��[�J�[�̎Y���}���̒��ړI���J�j�Y���́A�r�͂ɗ��������̂ł͂Ȃ��A�������ݏ��i���w�������������ƌĂԁj�ɂ��Y���}���̗U���ł���B�����Ă���͂����炭�啔���͎����I�Ȃ��̂Ǝv����B�Ȃ��Ȃ狭�͂ȃ|���V���O�̑��݉��ł́A�Y���͏�Ɏ��͂���Ď�����Ă���̂ŁA���ʂȗ��ȓI�s�ׂ͍ŏ�����s��Ȃ��Ƃ����A���ȗ}�����I�ɐi������Ƃ����_�I�ɗ\������Ă��邩�炾�B����͊O�����₪�ē����I�ȓ��@�ł���u�ǐS�v�u�������v�ނƌ��������邱�Ƃ��ł��悤�B([55])
�@����̍����w�̂���Ȃ�i�W��҂����Ȃ����A�Љ�����ɂ����ɁA�u�ǐS�v�u�������v�ƌĂԂɑ������̂�����Ƃ���A�ނ�ɂ��u�@�v�����݂��邱�Ƃ��\���\��������A�ƕM�҂͍l����B
�@�i�R�j�q�g�́u�@�v�Ɠ����́u�@�v�|���ʍ��ƍ���@����ɒ��ڂ���
�@�����ŁA�q�g�́u�@�v�Ɠ����́u�@�v�́A���ʕ����ƍ�����b��I�ɂ���A���炩�ɂ��Ă��������B
�@�b�茋�_�����Ɍ����A����͌���̗L���ɐs����B���Ȃ킿�A�{�e�ł́A�u�R�~���j�P�[�V�����v�Ɓu����v���s�ʂ��A��������ߎ�Ƃ������B�����w�҂̊Ԃł́A���Ƃ���1�C�̃~�c�o�`�����̂��肩�������A�����̑��ɖ߂��āA���̂��肩�₻�̕����G�ȃ_���X��H�̐k�킹���œ������̑��̓����I�ɓ`���邱�Ƃ��A�u�R�~���j�P�[�V�����v�Ƃ��Ă͈������A�����܂ł��u����v�Ƃ͔F�߂Ȃ��̂��ʗ�ł���B���_���猾���A�~�c�o�`�݂̂Ȃ炸�A�u�����v�ȗ쒷�ނɂ��u����v�͂Ȃ��A����𑀂铮���̓q�g(Homo sapiens)�����ł���A�Ƃ����̂������w�҂̗���ł���B
�@��������A�q�g�́u�@�v�Ɠ����́u�@�v�̋��ʕ����́A�{�e�A���ɑ�Q���E��P�͂����炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă���A�i���I��Ղ����L����q�g�Ɠ����́u�@�v�ł���B����́A�q�g�̖@���A���������i���I��Ղ�L�����A����������ʂ��Ė��m�����A�T�^�I�ɂ́A�Y���@�́u�ߌY�@���`�v�ɕ\���悤�ɁA���O�Ɏ��m�O�ꂹ���߁A�ᔽ�����҂��������悤�Ƃ���Ƃ������ǖʂɕ\���i���������قȂ�A�����@�ɂ��ގ��̋ǖʂ͑��݂��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��j�B�����̖@�́A�J��Ԃ����A�`���p���W�[�Ȃǂ̗쒷�ނ��܂߁A�R�~���j�P�[�V�����̎�i�͎����̂́A����͎����Ȃ����߁A���������q�g�̖@�̂�����Ƃ͈�����悷���ƂɂȂ�B
�@�i�S�j�{�e�ɂ�����ۑ�̊m�F�|�u�@�v�̐V���Ȓ�`�̑Ó����̘_��
�@�����ŁA�{�e�ɂ�����ۑ������x�A�m�F���Ă��������B�{�e�̖`���i�ƁA�{�߁i�P�j�j�ɂ��q�ׂ��ʂ�A�{�e�ł̓q�g�́u�@�v���F
�u�i�R�j�����Ƃ��Ă̓����̈��Ƃ��Ẵq�g�́A�i���Ɋ�Ղ����A�L�͈͂ŁA���������E�s��������Ȃ��A���[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v
�ƒ�`���Ă���B�u�@�́A�i���Ɋ�Ղ����v�ƒ�`�����ȏ�A���̒�`�̉��ł́A�{�e�̖`���Ɍf�����ʂ�F
�u�i�P�j�m�c�n�@�́u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���B
�@�i�Q�j�u�@���v�́m�c�n���������Ă���������葽�����A�����m�q�g�̐i���I��Ձn�ɋ��߂邱�Ƃ��\�ł���B�v
�ƂȂ�̂́A�P���ɘ_���I�K�R�ł���B�������A�{�e�̉ۑ�́A���́i�u���t�̗V�сv�Ƃ�������悤�ȁj�_���I�K�R�����������Ƃł͂������Ȃ��B�{�e�`���ŁA���Ȃ�ʁi�P�j�i�Q�j�i�R�j�̏����ŁA��L�̘_�|���q�ׂ��Ƃ���A�u�i�P�j�u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���v���ƁA����сu�i�Q�j�u�@���v�́m�c�n���������Ă���������葽�����A�����m�q�g�̐i���I��Ձn�ɋ��߂邱�Ƃ��\�ł���v���Ƃ�{�e�ł͘_�������B��������A�@�̐V���Ȓ�`�A���ƂɁu�@�́A�i���Ɋ�Ղ����v�_��_���邱�Ƃ��ł���A�������s�I�Ɂi�P�j�i�Q�j�̐V���Ȗ@���_���ێ����邱�Ƃ��ł��A���i�R�j�̒�`�̑Ó����𗧏��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����̂��{�e�̊�}�ł���A�V���ȉۑ�ł���B
�@�{�߂ɂ����Ă��������ł��邪�A���߈ȍ~�A�܂����͈ȍ~�ƁA��Q���ɂ����Ă��A�܂��ɂ��̉ۑ�Ɏ��g��ł����B�{�߁i�P�j�A�u�}�P�v�̏W���`���u�m��������_�����Ă����n�@�E�@���v�ƁA�W���a���u�u�@�v�̐V���Ȓ�`�v�̐}��������x�z�N���Ē��������B�{�߁i�P�j�Ŋ��ɏq�ׂ��悤�ɁA�`�̈ꕔ�����a�̒�`����O��Ă��܂��̂͏\���Ɏ��o���Ă���B�������A�W���`���u�m��������_�����Ă����n�@�E�@���v�́A�]���l�����Ă������A�͂邩�ɑ����̕������A�u�i���Ɋ�Ղ����v�̂ł����āA�W���a���u�u�@�v�̐V���Ȓ�`�v�Əd�Ȃ邱�Ƃ��A�{�e�ł͘_�������킯�ł���B���Ȃ킿�A�{�e�̖ړI���B�̐��ۂ́A�W���`�ƏW���a�Ƃ́u�����v�������ɋ߂����A���̓�̏W���́u����v�������ɏ���������_�ł��邩�ۂ��ɂ������Ă���Ƃ����悤�B
�@��S�߁@��_�|�u����(culture)�v�̐V���Ȓ�`
�@�{�e�̎傽��ړI�ł͂Ȃ��̂ŏژ_�͂��Ȃ����A�ߋ��ɂ����ẮA�q�g�Ƃ���ȊO�̓����������N�}�[���Ƃ��āA����g�p�̗L���A�̎g�p�ƃR���g���[���̗L���A�������̗L���A�����̗L���A����̗L���A�@���̗L���A�����Ė@�̗L�����A�i�����܂ŗᎦ�I�ɂł���A�ԗ��I�ɂł͂Ȃ����j�������Ă����B�����̂����A����g�p�ɂ��ẮA�ꕔ�̗쒷��([56])�ƒ���([57])��������g�p���邱�Ƃ����łɔ����Ă���A�����N�}�[���Ƃ��Ă͔ے肳��Ă���B�{�٘_�ł́A����ɐi���_�̊ϓ_����A�������A�����A�����Ė@���A�ꕔ�̓����ɂ͖��炩�ɔ�����Ă���A�����̂��Ƃ��肪����Ƃ��āA�q�g�ƈꕔ�̓����̊Ԃ̋��ʂ̐i���I��Ղ����邱�Ƃ�_���Ă��������B�����Ď��ۂɁA���̒��ł��A�u�����v��u�@�v�ɂ��ẮA�����̊T�O�̂��[���K�ȗ����̂��߂ɂ͂��̒�`��ς��A���������邱�ƂŁA�����ɂ��A������@�����݂��邱�Ƃ��_�ł���ƁA�ꕔ�̗쒷�ފw�҂ƂƂ��ɁA�M�ҁE�a�c�͍l���Ă���B�i���Ȃ݂ɁA�̎g�p�ƃR���g���[���A����A�@���́A���݂ł��q�g�݂̂Ɍ����錻�ۂł���Ɗe����̐��Ƃ̊Ԃł͍l�����Ă��邱�Ƃ�t�����Ă����B�j
�@�{�߂ł��A�ȏ�̃R���e�N�X�g�̒��ŁA�����܂ŕ�_�Ƃ��Ăł��邪�A����(culture)�̐V���ȁi�b��I�j��`�ƁA�q�g�݂̂Ȃ炸�A�����ɂ��u�����v�����邱�Ƃ��A���łɗ쒷�ތ����҂̑唼�ɂ͎�����Ă��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B���̖ړI�́A�ꕔ�̓����ɂ��u�@�v�����邱�Ƃ̂���ΖT�Ƃ��āA�����ɂ��i���łɘ_�����j�������ƕ���ŁA���������݂��邱�Ƃ������Ă������Ƃł���B
�@�i�P�j�u�����v�̐V���Ȓ�`�|�����l�ފw����̉��
�@�u�����v�͉ߋ��ɂ����Ă��l�X�ɒ�`����Ă����B�i�ȉ��A�{�߂͂����܂Łu��_�v�ł���A�{�e�̎�ړI�ł͂Ȃ��̂ŏڍׁE����ɂ킽���Ă͘_���Ȃ����Ƃ����炩���߂��f�肵�Ă��������B�j���ɁA�܂��͕����l�ފw�̕���ɂ����āA�q�g�̕����������ΏۂƂ��ꂽ���߁A���̕���ł̒�`�����R���݂�ꂽ�B([58])���̌�A�����l�ފw�̌������@�_�́A<�ώ@�҂Ƃ��Ă̕����l�ފw�҂��Ώۂ̐l�I�W�c�i�̉��l�̌n�A�s���̌n�A�ے��̌^�Ȃǂɑ�\����镶���j���A��ϓI�Ȋώ@�Ɋ�Â��ď��q���������ł͂Ȃ����H>�ƁA�^�`�������͂��܂��悤�ɂȂ�B�i�ΏƓI�ɁA�Ⴆ�A�Љ�S���w�ł́A���ɑΏۂ�ړI���l�ފw�I�����Ɠ���������ꍇ�ł��A�u�q�ϓI�ȁv�f�[�^�Ƃ��̒~�ςɂ��A�_�����݂Ă���A�Ƃ����_����荂���]�������X���ɂ���A�Ƃ����悤�B�j�������ċ^�`���悳�ꂽ���Ƃƒ��ڂɂ͘A�����Ă��Ȃ��ɂ��Ă��A�ԐړI�ȘA���Ƃ��āA�u�����v�̒�`�������l�ފw�����������([59])�X���݂������B���ɁA�������u�~�[���v�Ƃ��Ē�`����c�_�͋L���ɐV�����Ƃ���ł���B([60])
�@�{�e�ɂ����ďd�v�Ș_�_�́A�����̒�`���A�����l�ފw����������A���u�J���v�I�Ȃ��̂Ƃ��ꂽ���Ƃł���B�b�茋�_���猾���A���݁A�i�������w�E�i���S���w�̕���ł́A�u�����v�Ƃ����p��́A�q�g�⓮���̍s���́u�n�捷�v�������\���ۂɗp�����Ă���B�����āA�i���Ƀq�g�ɂ������ɂ��j��`�q�ɂ��s���̋K�肪����Ƃ��āA���������s���̋K�肩��͎��R�ɁA���Ȃ킿��V�I�ɂł͂Ȃ��A��V�I�ɏK�����ꂽ�s���p�^�[���i���̑����͒n��ɂ���č���������j�Ɍ��y���鎞�ɁA�u�����v�Ƃ����p�ꂪ�g����B([61])([62])
�@�i�Q�j�����i���ɎЉ�����j�ɂ�����u�����v�̑���
�@������A�����A���ɗ쒷�ނ̈ꕔ�i���Ƃ��`���p���W�[�j���n�߂Ƃ���Љ�����A���Ȃ킿�W�c�ŎЉ���`�����A���̏W�c���̃��[���Ɋ�Â��Đ������Ă��铮���ɂ����āA���̃��[����s���p�^�[���ɂ��āA�n�捷���ώ@����鎞�ɂ́A������u�����v�Ƃ��Č����\�����ƂɂȂ�B���ۂɁA�����Ƃ����p��͂��̂悤�Ɏg���Ă���B���̑����Ⴊ�A�n�[���@�[�h��w�̒����ȗ쒷�ތ����ҁi�ߔN�͐l�ԍs���w�ɂ����������Ę_���Ă���([63])�j�ł��� Richard Wrangham �ق��̕ҏW�ɂ��A1994�N�Ɋ��s���ꂽ�AChimpanzee
Cultures ([64])�m�w�`���p���W�[�̏������x�n�Ƃ����_���W�ł���B�{���ł́A�ߋ��ɂ����Ė쐶�̃`���p���W�[���ώ@�E�������ꂽ�ꏊ���A�t���J�嗤���ł�45�J���ɋy�Ԃ��Ƃ��A�܂��`���̒n�}�Ŏ�����Ă���B([65])���̏�ŁA�{���S�ʂ�ʂ��āA�Ⴆ�A�����A�t���J�嗤���ł��A����n��̈قȂ�`���p���W�[�̍s���i�p�^�[���j�ɂ͍��Ⴊ���邱�Ƃ����炩�ɂ���A����́u�����v�̍��ł���A�ƂƂ炦���Ă���B([66])
�@����ɗႦ�A���ɖ{�e�ʼn��x�����O�̋��������h�D�E���@�[���́A����Chimpanzee Cultures �̒��ŁA�܂��A�����҂�Richard W. Wrangham�AW.C. McGrew�i�}�C�A�~��w�����̒����ȗ쒷�ތ����ҁj�ƂƂ��ɁA�u�w�����쒷�ފw�icultural primatology�j�x�Ɩ��Â��悤�Ƃ��Ă��鎎�݂́A�m�����́A�]���n���L����`��v������B����́A�����ގ��́A�O�����I�ȁA�����̌��^�I�Ȕ��������܂ޒ�`�ł���B�v�Ƃ��A�u����������ܓI�Ȓ�`�́A���{�̗쒷�ފw�҂����A�Ⴆ��1952�N�ɂ��łɁw�����x���w�Љ�I�ɓ`�d�����A�����\�ȍs���x�ƒ�`���������m�юi�n���̊Ԃł͍L�܂��Ă����B�v�Ǝw�E����B([67])
�@�i�m���ɁA�����юi�́A�_���ł͂Ȃ����A�w�l�ԁx�Ƃ����������̒��̑��́u�l�Ԑ��̐i���v(1952�N)�ɂ����Ċ��ɁA�l�ԈȊO�̓����́u�J���`���A�v�̑��݂�O��Ƃ��Ă����B([68])�j
�@����ɁA�h�D�E���@�[���́A�͓����������̒��ŁA�P�ƂŒ����������ŁA�u�����^culture�v�̓����Ӗ�(connotation)�Ƃ��āA�u���p�≹�y�v�A�u�ے��⌾��v�����낤�A�Ƃ܂��_����B�����āu�����v�́u���R�v�ƑΒu�������̂ł���A�u�����v�ɂ��u���R�v���R���g���[�����ɂ������ƌ����Ă����A�Ǝw�E����B�������A�u��X�ɂ����Ƃ��߂��쒷�ނ��Ȃ킿�`���p���W�[�ƃ{�m�{���瓾���鎦���́A�����̃��@���G�[�V�����ɗאڂ���s���̑��l���̓x����������̂ŁA�w�l�Ԃ̕����x�Ɓw�����̎��R�x�Ƃ������ꂢ�ȓ@�́A���S�ɂЂ�����Ԃ����v�Ɣނ͌�������B�u�������̍s���̑��l�����A�ے��⌾��ɗ����Ă���Ƃ����̂͂��蓾�Ȃ����낤�Ƃ������_���O��Ƃ��Ă���̂́A�l�Ԃ̑S�Ă̕����I�ȃ��@���G�[�V�����͏ے��ƌ����K�v�Ƃ��A�q�g�ƁA���̌�������ߐl�ށihominoids�j�ɂ͔F�m��̃M���b�v�����݂���Ƃ������Ƃł���B����́i���ʓI�Ɂj��X�i�_�ҁj�ɁA�O���[�v���̃��@���G�[�V�����ɂ��ĈقȂ�������̗p���邱�Ƃ��\�ɂ���B�v�Ǝw�E����B�����āA�u��1�ɁA�m���ɁA�q�g�̕����̃��@���G�[�V�����́A����Ɍ��т����A����ɕ\�킳��Ă���A�q�g�̕����̑����̑��ʂ͂��́i����Ƃ́j���т������ł͍l�����Ȃ��B�������A�i�����́j���@���G�[�V�����̊���̑��ʂ����f���Ă���A�Љ�̎��H(socialization
practices)��A�ώ@�ɂ��w�K�́A�����p���邱�Ƃ͂��邪�A�K���������ꂪ�K�{�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B��2�ɁA�q�g�Ƒ�^�ސl���̊Ԃɂ́A�F�m��́m�V�X�e����\�͂́n�A����������Ƃ����؋��͑��������ł���B�{���I�ȍ��Ⴊ�c���Ă���̂́A�F�߂���Ȃ����A����͒��x���ɉ߂��Ȃ��A�Ɗ�����Ȋw�҂��ǂ�ǂ��Ă���B���������āA�����I�ȓ`�d�̈��̃v���Z�X�͉�X�q�g�ȊO�̎�ł��N�����Ă���\�������O�͏o���Ȃ��̂ł���B�v�ƌ��_�t����B([69])
�@�����ōĊm�F���Ă��������̂́A�h�D�E���@�[�����͂��߂Ƃ��邱�̒����̋����ҒB�i���v35���j([70])���A���������̌�������ƕ��@�_(discipline)�̗L�p���E�L�������咣�����������߂݂̂ɁA�u�����v�̒�`������ɜ��ӓI�ɕς��A�쒷�ނɂ����������݂���A�Ƃނ�݂Ɍ��`���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B���łɏq�ׂ��Ƃ���A�u�����v�i��u�@�v�j�ɂ��Ă��A�����̊T�O�̂��[���K�ȗ����̂��߂����A���̒�`��ς��A���������邱�ƂŁA�����ɂ��A�����i��@�j�����݂��邱�Ƃ��_�ł���ƁA�ނ�쒷�ފw�ҁi�Ɩ@�w�҂Ƃ��Ă̕M�ҁE�a�c�j�͍l���Ă���킯�ł���B
�@����ɁA�ꕔ�̓����ɂ����������݂��邱�Ƃ��A���ڂ����A�L�͂ɘ_�����V���Ș_���W���A2003�N�Ɍ������ꂽ�AFrans de
Waal��Peter L. Tyack�̋��҂ƁA���̕���̐��Ƃ̒��҂�������52��([71])�ɂ��_���W�AAnimal social complexity : intelligence, culture, and individualized
societies([72])�m�w�����̎Љ�I���G���F�m���A�����ƁA���I�ȏ��Љ�x�n�ł���B����́A�O�f��Chimpanzee Cultures ���͂邩�ɐV�����A�����ɂ����݂���u�����v�̐V���Ȓ�`�Ƃ��̊T�O�̉��p�ɂ��āA�ڍׂɘ_�����_���W�ł���B
�@�܂��A�Ҏғ�lFrans
B.M. de Waal��Peter L. Tyack �ɂ��"Preface�m�O�����n"���A�����̐V���Ȓ�`�Ɍy�����y����([73])�B����ɁA���ɒ��ڂ��ׂ��́A��V���A"Cultural
Transmission�m�����̓`�d�n"�ł���B��V���ւ̑O����([74])���A�u�����̓`�d�v�Ɋ֘A���āA�}�b�R�E�N�W���A���N�h���A�z�V���N�h���Ɍ��y���Ă���̂ŁA�Q�Ƃ��ꂽ���B([75])�K���i�������܁j�̃j�z���U���́u��v�����̓`�d�Ƃ����A�쒷�ފw�҂̊Ԃł͂����Ƃ��悭�m���Ă��錻�ۂ̓��{�ł̌����ƁA�{�b�\�E�̃`���p���W�[�Ɋւ��錤�������܂ޘ_�����ATetsuro Matsuzawa, "Koshima Monkeys and Bossou Chimpanzees:
Long-Term Research on Culture in Nonhuman Primates"([76])�m����N�Y�u�K���̃j�z���U���ƃ{�b�\�E�̃`���p���W�[�F�q�g�ȊO�̗쒷�ނ̕����ɂ��Ă̒����I�����v�n�ł���B��蒍�ڂ��ׂ��́AW.C. McGrew�̘_���A"Ten
Dispatches from the Chimpanzee Culture Wars"([77])�mW.C. �}�N�O���[�u�`���p���W�[�̕����푈�����10�̓���v�n�ł���A���ɁAM.C.
McGrew�ɂ��"Culture Has
Escaped from Anthropology"([78])�m�u�����͐l�ފw���瓦�S�����v�n�̍��ڂ��A�������l�ފw����������A�쒷�ފw�ł��d����悤�ɂȂ������Ƃɂ��āA���ɎQ�Ƃ��ꂽ���B����ɁA�N�W���ƃC���J�̕����̑��݂ƁA�����ɂ�����"Culture"�̒�`�Ɍ��y�����̂��AHal Whitehead, "Society and Culture in the Deep and Open Ocean:
The Sperm Whale and Other Cetaceans"([79])�m�n���E�z���C�g�w�b�h�u�[�C�ƌ��C�ɂ�����Љ�ƕ����F�}�b�R�E�N�W���Ƃ��̑��̃N�W���ځv�n�ł���B�Ō�ɁA���ނɂ����镶���̔����ɂ��āAMeredith J. West, Andrew P. King, and David J. White,
"Discovering Culture in Birds: The Role of Learning and Development"�m�����f�B�X�E�i�E�E�F�X�g�A�A���h�����[�E�o�E�L���O�A�f�C���B�b�h�E�i�E�z���C�g�u���ނ̕����̔����F�w�K�Ɣ��B�̖����v�n�A���ł�����"Summary: A Test of Culture as a Social Enterprise"([80])�m�u�T�}���[�F�Љ�I���ƂƂ��Ă̕����̌����v�n�̍��ڂɒ��ڂ��ꂽ���B
�@�i�R�j�q�g�́u�����v�Ɠ����́u�����v�|���ʍ��ƍ���@����ɒ��ڂ���
�@�ƂȂ�ƁA�O�߂́u�@�v�Ɠ��l�ɁA�q�g�́u�����v�Ɠ����́u�����v�̋��ʍ��ƍ���͂ǂ��ɂ���̂��A�ɒ��ڂ��Ă����K�v�����낤�B�����ł��A���ߎ�͌���̗L���ƂȂ�B�q�g�ł������p���Ȃ��Ƃ��`������Ă����i�{�߂ŏq�ׂ��Ӗ��ł́j�u�����v�͓��R���肦�邪�A�����̑����͌����p���邱�Ƃɂ����reinforce�i�⋭�A�����j����A�`������邱�ƂɂȂ�B���̈���ŁA�����̕����́A��S�́E��T�߂ł��_���邪�A�����̎����Ȃ��������邱�Ƃ͂��肦���A��Ɋώ@�Ƃ�����i�ŏK��([81])����A�ێ�����A�ꍇ�ɂ�葼�̒n��ɂ��g�U�E�`�d([82])���Ă������ƂɂȂ�B
�@�i����ɁA�{�e�̎傽��ړI�ł͂Ȃ��̂ŖT�_�Ƃ��ďq�ׂ�ɗ��߂邪�A�q�g�̕����ɂ͏@�����܂߂čl������A���邢�͍l����ׂ��ł������ŁA�q�g�ȊO�̓����̕����ɂ͂���������A�����_�܂ł̐����w�A�Ȃ���Â������s���w�E�������Ԋw�Ȃǂ̌������ʂł́A�@���炵�����͔̂�������Ă��Ȃ��A�Ƃ��������̍��ق�����ł��낤�B�Ȃ��A�E�e��A�ȉ��̏d�v�Ȕ��������V���L���ɐG�ꂽ�F�����V��2010�N4��28���[��4��27���[����10�ʂɁA�u���q�w�����`���p���W�[�@�����̋N���H�v�ł���B���̋L���̓d�q�ł́A�u�`���p���W�[�ɒ����S�H�@��e�A�~�C���������q��w�����v�̌��o����http://www.asahi.com/science/update/0427/OSK201004260182.html�Ō��邱�Ƃ��ł����B�d�q�łɂ����e�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���F
�@�`���p���W�[�̕�e�����q�ǂ����~�C��������܂Ŕw�������������A���s��w�쒷�ތ������̗�
���� �����A����N�Y������̃`�[���������Q��ŕ����ώ@�����B�q�g�����҂��Ƃނ炤�s���̋N���ł͂Ȃ����ƃ`�[���݂͂Ă���B27���t�̕Đ����w���ɔ��\�����B
�@�`�[���́A���A�t���J�E�M�j�A�Ŗ쐶�`���p���W�[�̌Q��̒�����30�N�ȏ㑱���Ă����B�W���Ƃ������O�̃`���p���W�[��1992�N�ɕa������2�Δ��̎q�ǂ���27���Ԉȏ�A2003�N�ɂ��a�������P�̎q�ǂ���68���Ԕw�����������B�����Q��̕ʂ̕�e������2�Δ��̎q�ǂ���19���Ԕw�������B
�@3��Ƃ����̂̓~�C�����������A��e�͐����Ă��鎞�Ɠ����悤�ɖёU����������A�̂ɂ�����n�G��ǂ��������肵�āA�q�ǂ��Ɉ���������Ă���悤�������B�����Ă���Ƃ��Ɣw���������Ⴂ�A�u�����Ƃ͗������Ă���v�ƃ`�[���݂͂�B
�@�u�q�g�����҂��Ƃނ炤�C�������i���̉ߒ��Ő��܂ꂽ�B���q�ǂ��ɂ�肻���`���p���W�[�̍s���ɁA���̋N��������̂ł͂Ȃ����v�Ə����͘b���Ă���B�i����Ύq�j
�m�d�q�ł̕����ɂ��Ɓu����17���A�~�C���������q�ǂ���w�����W�������s��쒷�ތ������v�Ƃ����W���̎ʐ^���A�V���L���A�d�q�ŋL���Ƃ��ɁA�Y�����Ă���B�n
����ɂ��ẮA�������e�́u�����V���v�d�q�ŋL���ɁA���ƁE���J����ꋳ���ɂ��ȉ��̃R�����g�����Ă���i�o�T�́Fhttp://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010042702000034.html�j�F
���J�������勳���i�����s���w�j�̘b�@�����W�c�̒���3�ᑱ���āA�`���p���W�[�̕�e������̎q�ǂ����~�C��������܂ʼn^�Ƃ����͂���܂łȂ��B�������A�~�C���������q�ǂ��̉^���́A�j�z���U���Ȃǂł�����Ă���A���ꂪ�����I�ȍs�����A���邢�͐l�Ԃ̒����ɒʂ���̂��ɂ��ẮA���̗쒷�ނƂ̔�r���܂߂āA�f�[�^�̒~�ς��҂����B
�����ŏs�ʂ��ׂ��́A���ɂ��̃`���p���W�[�̍s�����A�l�Ԃ⓮���́u�����̋N���v�ł���Ƃ��Ă��A����͑����ɂ́A�����ɂ�����u�@���̋N���v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����_�ł���B�����܂ł��Ȃ����A�@����M���Ȃ��B����`�҂̐l�Ԃ��A���@�����ő����������邱�Ƃ͂���B��Ƃ��āu���܂��O�̐��E�v��u����̐��E�v��z�肷��̂��u�@���v���ۂ��̌��ߎ�ƂȂ�����ł���B����̌������ʂ��A�`���p���W�[���u����̐��E�v��z�肵�Ă���_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ȏ�̗��R���ȂāA�����̔����́A�M�ҁE�a�c�̑O�q�́A�����ɂ́u�@���炵�����͔̂�������Ă��Ȃ��v�Ƃ����b�茋�_��h�邪�����̂ł͂Ȃ��A�ƌ��_�Â������B�Ȃ��A����̔��������������`�[����1�l�ŁA�����V���̋L���ɖ����������Ă���� ���� �����́A���܂ł����s��w�쒷�ތ������Ŏ��炳��Ă���`���p���W�[�̍s���ɂ��Ă��A�D�ꂽ�������ʂ\���Ă����r�p�ł���B����̗�
���� �����̂��������ʂɊ��҂������B�j
��Q�� �u�@�Ɛi�������w�v���_
�@�{�E��P���̑�Q�͈ȍ~�ł́A��q�̎��R�Ȋw����ɂ��āA����݂̐ł��낤�@�w�҂̓ǎ҂�O���ɒu���A����u�w�E�W�]�v�Ƃ��āA�u�i�������w�v�u�i���S���w�v�ɏd�_��u���A����ɂ́u�s����`�w�v�u�]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�u�i���ϗ��w�v���ꂼ��̕���ŁA�����Ȃ�V���Ȓm�����܂ތ��������X����Ă��邩���A�܂��Љ��B�����čŌ�ɁA���������V���Ȓm�����X�^�[�e�B���O�E�|�C���g�Ƃ��āA�@�w�Ƃ̃N���X�E�I�[�o�[�̊w�ە���ŁA�ǂ̂悤�ȓW�]���J���Ă��邩���e�Z�N�V�����̖����ɕM�҂��t���I�ɘ_����A�Ƃ����i���̂�B
�@��P�߁@�i�������w�Ƃ��̔��W
�@�i�P�j�_�[�E�B���̐i�������w�Ƃ��̔��W�|���R�����i���R�I���j�E�������i���I���j
�@���́E��R�߂ł��ȒP�ɐG�ꂽ���A�_�[�E�B���������i�������w�́A�ߔN�A���R�I���ɉ����āA���I���̌������i�݁A����w�̔��W���݂Ă���B([83])�i�������w���̂��̂�_����͖̂{�e�̖ړI�ł͂Ȃ��A�����܂Łu�@�Ɛi�������w�v�Ƃ����w�ە���ŁA�����Ȃ�V���ȓW�]���J���邩�����ɂ������߁A�i�������w�̐V���Ȕ��W([84])�ɂ��Ă����L����ɂƂǂ߂邪�A���I���ɂ��Ă����ł��A1930�N�Ɂu�����E�A�E�F�C�����v([85])�����\����ĈȌ���A1975�N����1984�N�̂킸��10�N���炸�̊ԂɁA�u�n���f�B�L���b�v���_�v([86])�E�u���X�ɂ��I��D�݁v([87])�E�u���q�ԋ����v([88])�Ƃ������V���ȗ��_�≼�������X�Ɣ��\����Ă���B�����������ł��A�{�e�̎��ł���u�@�Ɛi�������w�v�̊ϓ_����́A���R�I���E���I��o���̓_�ŁA�i�������w�̊�b���Ȃ��u�����x�v�u�K���x�v�u��K���x�v([89])�͂����܂ł��Ȃ��A����ɁA�u�b�I�����s���v�u�ߐe���̉���v�u�z��Җh�q�v�u�����̊m�M�E�m�F�v�Ȃǂ��d�v�ƂȂ�B([90])
�@����ɁA���́E��R�߂̒�(11)�ł��łɏq�ׂĂ��������A�i�������w�ł��A���߂ɂȂ��āA1970�N��O���William
Hamilton, Robert Trivers��ɂ���Ēz���ꂽ��ՂɈ��̋^�`���悳���ȂǁA�V���Ȑi�W��������B�Ⴆ�A�n�~���g�������������x�E�K���x�E��K���x�͗����s������������ł͏d�v�ł������B�������A2009�N�ɓ����āA�C�M���X��Ratnieks
& Wenseleers���ȉ��̒��ڂ��ׂ��_�����厏Trends in Ecology & Evolution�i����TREE�j�ɏ����Ă���F"Altruism
in insect societies and beyond: voluntary or enforced?"([91])�m�u�����Ƃ���ȊO�̏��Љ�ɂ����闘���s���F�����I���A�������ꂽ���̂��H�v�n�B����͒[�I�Ɍ����A���܂Ŏ����I���Ƃ���Ă����u�����s���v���u�����v����Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^���悵�����̂ł���B���́E��R�߂̒�(10)�Ŋ��q�̒ʂ�A"enforced"�ƂȂ�ƁA�u�@�v�Ƃ����ϓ_������ʼn߂ł��Ȃ��B����݂̂Ȃ炸�A���̘_���́A�Ғœ����́A����ɂ̓q�g�̎Љ�ɂ����闘���s���̋����ɂ��Ă��_���Ă���B����̐i�������w�̐V���Ȕ��W��肤��ł��A����Ratnieks & Wenseleers�̌����́A���ڂ��ׂ������ł���A����Ȍ�̂��̐�������ڂ������Ȃ��_�_������Ƃ����悤�B
�@�i�Q�j�_�[�E�B���́u���R�����_�i�I��_�j�v�Ɩؑ��������m�́u�����i���_�v�i1968�N���\�j——�������A�Η����H
�@�����ň�_���ۂ��Ă��������B�i�������w�͊m���ɔ��W���Ă���̂����A���̒��ŁA�_�[�E�B���̗��_�Ɉق���������ǖʂ��\��Ă��Ă���B
�@���̈��Ƃ��āA�ؑ������i���ނ�E���Ƃ��j���m�̐i���́u�������v�i1968�N��Nature���ɔ��\�j([92])�̈ʒu�Â��ɂ��āA�����P�Ƀ_�[�E�B���̐i�������w��⋭���闝�_�ł͂Ȃ��A�_�[�E�B�����������������_�i�I��_�G���{��̗p��͈قȂ���̂́A�����"selection"�œ����ł���A���{��ł��Ӗ�����Ƃ���͌��Ǔ����ł���j�ɑΗ����闝�_�Ƃ��Ē��ڂ���A�֓����狳���ɂ��咣([93])�������Ă��������B([94])
�@�����v����A<�i�_�[�E�B���͂��̑��݂�m��Ȃ������j��`�q�̕ψق́A�I�����̉��ŁA�I������Đi������i�܂藧������āA�c��j���A��������ď�����>�Ƃ���_�[�E�B���̑I��_�i�����_�j�ɑ��āA�ؑ������̗��_�́A�P��<��`�q�̕ψق͈��̕������������Ƃ͂Ȃ��A�i����������j��������A�c��A���Ȃ킿�i�����邩�ǂ����Ƃ͖��W�ɁA�N����>�Ƃ����ɂƂǂ܂炸�A<���ۂɂ݂����`�q�̕ψق̑唼�́A�I�����i�������j�Ƃ͖��W�ɁA�I��������������邱�Ƃ͂Ȃ��A�����I�ɑ�������>�Ƃ������̂ł���B
�@�_�[�E�B���̎��R�����_����b�ɐ������i���_�̗L�������������ŁA����A���̌����ɒ��ڂ��ׂ��_�_�ł��낤�B
�@��Q�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�̉\��
�@�ڂ����́A��Q���E��P�͂ŁA�u�@�Ɛi�������w�v�̎���ƌ��A���̉\���A���̌��E�ɂ��ďq�ׂ邱�ƂɂȂ邪�A�����ł͏��_�Ƃ��āA�ȒP�ɂ��̉\���ɐG��Ă��������B
�@�i���w�̊�b�́A�Ȃ�ƌ����Ă��i�������w�ɂ���B�����āA�{�e�ɂ�����u�q�g�̖@�v�̒�`�́A�u�����Ƃ��Ă̓����̈��Ƃ��Ẵq�g�́A�i���Ɋ�Ղ����A�L�͈͂ŁA���������E�s��������Ȃ��A���[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�ł���B�ƂȂ�A�q�g�́u�����Ƃ��Ă̐i���Ɋ�Ղ����m�c�n���[���E�s�K�́v���A������𖾂����i�Ƃ��Ă����Ƃ����҂����̂́A��͂�i�������w�ł���B�����Č����A�u�@�Ɛi���S���w�v�́u�@�Ɛi�������w�v�̉�����ɂ��鉞�p�҂ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B
�@�����Ŋ��҂����\���Ƃ��ẮA�܂������3�i�K�ɕ����邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�i�P�j1960�N�ォ��1970�N��ɂ����Ċm�����ꂽ�A�u�i�������w�v�̊�b���_�̉��p�Ƃ��āA�u�q�g�̖@�v�̖@����T��B
�@��̓I���������AWilliam
Hamilton�i�E�B���A���E�n�~���g���j�ARobert
Trivers�i���o�[�g�E�g�����@�[�X([95])�j��ɂ��A�u�����x�v�u�i��j�K���x�v�̗��_�Ɋ�Â��A�u�b�I�����s���v���q�g�̍s���Ɍ�����悤�ɂ��������i���I��Ղ��𖾂��A���ꂪ�u�q�g�̖@�v�ɂ����ɔ��f����Ă��邩���������邱�Ƃł���B
�@�i�Q�j�i�P�j�̊�b���_�̉��ɍ\�z���ꂽ�A���p���_��p���āA���ۂɁu�q�g�̖@�v�E�@���ɏo�����Ă���u�ߐe���̉���v�u�z��Җh�q�v�u�����̊m�M�E�m�F�v�Ȃǁi��P�ߎQ�Ɓj�̖@�����A�q�g�̐i���I��ՂɒT�邱�ƂɂȂ�B
�@�i�R�j����ɁA�i�P�j�i�Q�j�̉��p�Ƃ��āA���ۂɁA���{�̉Ƒ��@������ɂ����A����@�ɂ������̓I�ȉ��ߘ_�ɁA�u�@�Ɛi�������w�v�������ɉ��p�ł��邩�������Ă��������B��̓I�ɂ́A��Q���E��P�͂ł����邪�A�Ⴆ�A�u������}�{�v�̍����t��([96])�ɂ��āA�u�@�Ɛi�������w�v�̎�@��p���āA�V���Ȑ������B
�@��R�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�̎g���ƌ��E
�@�u�@�Ɛi�������w�v�̎g���́A�{�e�̖`���ɏq�ׂ��Ƃ���A�@�́u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ��邱�ƁA�u�@���v�̋��������Ă���������葽�����u�q�g�̐i���I��Ձv�ɋ��߂���������邱�Ƃɂ���B
�@�����ɁA���̌��E�Ƃ��ẮA�{��P���E��P�́E��R�߁E�i�P�j�̐}�P��z�N���Ă������������B���̐}�Ŏ������Ƃ���A����̖@�w�Œʗ�Ƃ��Ę_������u�@�E�@���v�ƁA�{�e�́u�i�q�g�́j�@�v�̒�`���e�́A���S�ɂ͈�v���Ȃ��B���̂��Ƃ�������炩�ȂƂ���A���݁A�u�@�E�@���v�ƌĂ����́i�W���`�j�̓��A�V���ȁu�q�g�̖@�v�̒�`�͈̔́i�W���a�j���珜����镔���i�̖@���j�ɂ��ẮA����_�����݂邱�Ƃ͂��Ȃ����A�ł��Ȃ��B
�@����͗Ⴆ�A�悭���y������ł��邪�A�u�Ԃ͉E���ʍs���A�����ʍs���v�ɂ��āA�u�ǂ��瑤�ʍs�������߂āA�^�]�ҁE�ʍs�l�ɋy�ԃ��X�N���ŏ����ɂ���v���Ƃ́A�{�e�́u�q�g�̖@�v�̒�`���ɓ���B�������A���ꂪ�u�E���v�Ȃ̂��u�����v���Ȃ̂��́u�@���v�Ō��߂�ׂ��d�v�����ł��邪�A�{�e�́u�q�g�̖@�v�̒�`����͊O���B
�@�u�@�Ɛi�������w�v�̎g���ƌ��E�́A�����ނˁA�����������_�ɂ���Ɩ{�e�̂��̎��_�ł͗������Ă���������悢�B�ڍׂ́A��Q���E��P�͂ɏ���B
��R�� �u�@�Ɛi���S���w�v���_
�@��P�߁@�i�������w�Ƃ��̋ߔN�̂߂��܂������W
�@�i�P�j�u�S���J�[�h���v�ɂ�����ACosmides�̉���I�Ɛ�
�@�i�������w�Ƃ��̋ߔN�̂߂��܂������W���ے����錤�����ʂ��A�����ŋ�����B�i���S���w�ł͂��łɂ��܂�ɂ悭�m��ꂽ��肩�Ɛтł��邪�A�@�E�@�w�Ƃ��[���W��L���邪�䂦�ɁA�܂��́A������u�S���J�[�h���v�i�����ɂ�"The Wason Card Problem"�A���{��ł́u�E�F�C�\���I���ۑ�v�Ƃ��Ă��j�ɂ�����ACosmides�̉���I�Ɛтɂ��āA�ȒP�ɉ�����Ă��������B([97])
�@���̌���([98])�ɂ����āA�[�I�Ɍ����ACosmides�́A�q�g��<���[���i�Ⴆ�Ζ@�I�j�ɑ��郋�[���ᔽ�ҁA�w����ҁx���m�ɂ����āA���ʂɗD�ꂽ�\�͂�����>���Ƃ��������̂ł���B
�@�n�[���@�[�h��w�̉@���ł������R�~�X�f�X�́A����w�̐�y�ł��郍�o�[�g�E�g�����@�[�Y(Robert Trivers)([99])�̗��_�ɑ傫�ȉe�����A�q�g�̎Љ�_��́i�i���j�����w�I��ՂƂ���ɓK�������S�����J�j�Y���ɂ��čl�@�����B�g�����@�[�Y���_�����u�b�I�����s��(reciprocal
altruism)�v�̐��������Ŕ��ɏd�v�Ȃ̂́A���b�������ŁA���Ԃ������Ȃ��̂����������Ƃ��ł���A�����Ă��̂悤�Ȍ̂�r���ł���Ƃ������Ƃł���B�����s���݂̑���W������������ƁA�R�X�g�����҂�������v�҂ɂȂ�邱�Ƃł���B�R�X�~�f�X�͂��ꂱ�����Љ�_��̊�{�������Ƙ_�����B�ޏ��̌��������j�[�N�ł������̂́A�Љ�_�ێ�����邽�߂ɂ́A������������҂�����������������悤�ȁu�S�����J�j�Y���v�����悤�ɁA�����I���i�����j�������Ă����ƍl�������Ƃł���B�q�g���b�I�ȎЉ�I�����ł���ȏ�A�q�g�ɂ͎Љ�_������Ȃ��u����ҁv���s�q�Ɍ��m����K���@�\��������Ă���͂����Ƃ����\����ޏ��͗��Ă��̂ł���B
�@"The Wason
Card Problem"�Ƃ́A�u�o�ł���p�ł���v�Ƃ�������̐^�U���m���߂邽�߂ɁA���ׂ�ꂽ�S���̃J�[�h�̂ǂ�𗠕Ԃ�����悢����₤�A��㈓I���_�̉ۑ�ł���B���_���猾���A�o�i�^�j�ƁAnot-�p�i��j��I�����邱�Ƃ����߂���B�܂�A�u�o�ł���p�ł��邱�Ɓv���m�F���邱�Ƃɉ����āA�u�p�łȂ����̂��o�ƑΉ����Ă��Ȃ����Ɓv�ׂ�K�v������B
�@�R�X�~�f�X�͊T���A���̂悤�Ȏ������s�����B�i�}�R�Q�Ɓj
�@�@(a) �܂��A�\�E���̂���S���̃J�[�h����ׂāA�\�ʂɂ͂`�a�b�c�̃A���t�@�x�b�g���A���ʂɂ͂P�C�Q�C�R�̐������L����Ă��邱�Ƃ�팱�҂ɐ������A�u�J�[�h�̕\���ꉹ�Ȃ�A���͋����ł���v�Ƃ�������̐^�U���m���߂������B�����ŁA�Ⴆ�F�u�`�v�u�j�v�u�S�v�u�V�v�Ƃ����S���̃J�[�h����ׂāA�ǂ̃J�[�h���߂���A����̐^�U���m���߂��邩�����������B�����́A�u�`�v�Ɓu�V�v���߂��邱�Ƃł���B�������A���ʂ́A��w���ɂ����Ă��A���ϐ�������10�����ł������B
�@�@(b) ���ɁA�u�r�[��������ł��邪�N�������Ȃ��ҁv�A�u�R�[��������ł��邪�N�������Ȃ��ҁv�A�u24������������ł��邩������Ȃ��ҁv�A�u16������������ł��邩������Ȃ��ҁv�A�S�҂���ׂāA�u�r�[���i�Ȃǂ̃A���R�[�������j������ł���Ȃ�A20�Έȏ�ł���v�Ƃ�������̐^�U���m���߂邽�߂ɂ́A�����`�F�b�N������悢�������݂������B�����́A�u�r�[��������ł��邪�N�������Ȃ��ҁv�̔N��ׂ邱�ƁA����сu16������������ł��邩������Ȃ��ҁv����������ł��邩���ׂ邱�Ƃł���B���̖₢�ł́A�������́i������w���Łj�ꋓ��60-70���܂ŋ}�㏸�����B
�@���ڂ��ׂ��́A�_���I�Ȗ��Ƃ��ẮA(a)��(b)�͑S���������ł���A�_���I�v�l�݂̂��K�v�Ƃ����Ȃ�A�������͓����ƂȂ�͂����A�Ƃ����_�ł���B�R�X�~�f�X�́A����ɂ�������炸�������ɑ傫�ȍ����o��_�ɒ��ڂ����̂ł���B
�@�]���A���̕����E���ۂ́A���ւ̂Ȃ��ݐ[���i���Ƃ��A���R�[�������ނ��ƂƔN��̃��[���j���邢�͎��p�I���̕����ɂ���Đ�����Ɛ�������Ă����B����ɑ��ăR�X�~�f�X�́A���������オ��̂́A���ꂪ�u�Љ�_��ۑ�v������ł���A�Ƃ�킯�q�g������҂��s�q�Ɍ��m����S�����J�j�Y��������Ă��邩�炾�ƍl�����B�ژ_([100])�͔����邪�A�ޏ��́A�҂�����݂̔������ł��A�Љ�_��̕�����t������Ɛ������������Ȃ邱�Ƃ�A�O��Ƌ�����Ȃ�ۑ�ł��A�Љ�I�������^����ꂽ�ꍇ�̂݁A�������������Ȃ邱�Ƃ��������B([101])
�o not-�o �p
not-�p
(a)�@�`�@�@�@�j�@�@�@�S�@�@�@�@�V�@
(b) �r�[���@�R�[���@24�@�@�@16�@
�}�R
�@���̌�A�I�[�X�g���A�̃U���c�u���N��w�����̔F�m�Ȋw��Gerd Gigerenzer�i�Q���g�E�M�Q�����c�@�j��́A����̂S���J�[�h���ɂ����āA�N����v�҂ƂȂ邩��ω������邱�Ƃɂ���āA�R�X�~�f�X��̎Љ�_������x������������s�����B�܂��A����݂̔����Љ�_��ɂ��Ă̒ǎ������s���A���̏�ŁA�u��Ђ���A�ߋ��̔�ٗp�҂��N������邽�߂ɂ́A���Ȃ��Ƃ����̉�Ђ�10�N�ԓ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ�������ɂ��āA�����҂��Љ�_�������Ă��邩�ǂ����i�����Ă��Ȃ����ǂ����j���m�F����Ƃ����_�ł́A�R�X�~�f�X�̌������ʂƊ�{�I�Ɉ�v���錋�_���o�����B([102])
�@����ɁA���{�̑�w����Ώۂɒ����ɒǎ����ꂽ���ʂ́A�R�X�~�f�X�̎������ʂ������ނˎx��������̂ł������B([103])
�@�����ŋ����������̂́A�i���̉ߒ��ɂ����āA<�q�g�ɂ͎Љ�_������Ȃ��u����ҁv���s�q�Ɍ��m����K���@�\���S�����J�j�Y���������>�Ƃ������Ƃ́A�q�g�ɂ�����@�̐����ɂ����āA�d�v�ȕK�v�����ł��������Ƃ��������A�Ƃ������Ƃł���B���̈Ӗ��ŁA�R�X�~�f�X�̎����Ƃ��̌��ʂ́A�u�@�Ɛi���S���w�v�ɂƂ��Ă��d�v�ȈӋ`�������̂ł���B([104])
�@�i�Q�j���ۂƋ^�`�|2009�N�x��HBES�̑S�̉�c�ł�Stearns�����̔��\
�@�����Ƃ��A�����ŁA�i���S���w�̐��ʂɂ��āA�^�`���Ȃ��킯�ł͂Ȃ����Ƃɂ����y���Ă��������B�M�҂��Q�������A2009�N�x�̍��ۊw��Human
Behavior & Evolution Society (HBES)([105])�̑S�̉�c(Plenary)�ł�Stephen Stearns�����iEdward P.
Bass Professor of Ecology and Evolutionary Biology, Yale University�j�ɂ��gAre We Stuck in a Major Transition and
Feeling the Pain?�h([106])�m�u��X�͎�v�ȓ]�����ɂ����Ēɂ݂������Ă���̂��H�v�n�Ƒ肳�ꂽ��u��(key note
address)�ŁASterns�����́A�u�i���S���w���咣����w��I���ʂɂ��ẮA���܂�ɉ����I�Ȃ��̂������A�^�`�������͂��ޗ]�n������v�Ɩ������Ă���B
�@�m���ɁASterns�����̋^��̂Ƃ���A�R�X�~�f�X��̋c�_�́A�ꉞ�����I�ł��邪�A�]�Ȋw�̗��ꂩ�炢���A�]�̂ǂ̋@�\���ޏ��������咣����i���Ƃ��j���m�\�͂�⍲���Ă���̂��A�Ƃ����Ƃ���܂ł͕������Ă��Ȃ��B�܂��A�����������m�\�͂́A���ߓI�����Ƌ��ɓI�����̗��҂̉𖾂��\���A�Ƃ����^����c��B���̓_�ɂ��ẮA�R�X�~�f�X�́A����HBES�̌ʃZ�b�V�����ł̔��\���܂߂āA�ŋߎ��ɂ́A�]�̓������u���W���[��(module)�v�Ƃ��āi��������̔�g�Ɨ������邩�A�����I�ɔ]�Ȋw�I�Ɏ��؉\�Ȕ]�̃��J�j�Y���Ƃ��ė������ׂ����͈�U�[���Ƃ��āj�������邱�ƂŁA������A�i���S���w�S�ʂ̐M�ߐ��̗��ł��A����w�������邱�Ƃ����݂Ă���B�i�ڍׂ́A������q����B�j([107])
�@�i�R�j�u�e�B���o�[�Q���̂S�̂Ȃ��v�Ɛi���S���w�ɒ悳�ꂽ�^��
�@�i���S���w�ɒ悳�ꂽ�ŋߎ��̋^�`���m�F���邽�߂ɁA�{�e�ł͂��̒i�K�ŁA�i���_�̔��W��A����߂ďd�v�ł������A������u�e�B���o�[�Q��(Niko Tingerben)([108])�̎l�̂Ȃ��v�ɂ��Ċm�F���A�����O��ɁA��L�̋^�`�̈Ӗ��ɂ��čl���Ă݂����B
�@�u�e�B���o�[�Q���̎l�̂Ȃ��v([109])�Ƃ́A1973�N�ɓ����s���w�̑c��1�l�Ƃ��āA�R�����[�g�E���[�����c(Konrad Lorenz)�A�J�[���E�t�H���E�t���b�V��(Karl von Frisch)�ƂƂ��ɁA�m�[�x���E��w�E�����w�܂���܂����A�I�����_���܂�̐i�������w�҃j�R�E�e�B���o�[�Q�����咣�������ƂŁA�����̍s���ɂ��ẮA4�̈قȂ�u�Ȃ��H�v�����݂��A�����̍s����^�ɉ𖾂���ɂ́A����4�̑��قȂ�u�Ȃ��H�v�̂��ׂĂ͉𖾂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�������Ƃł���B
�@����4�Ƃ́F
1�D���ߗv���m���ڗv���Ƃ����Gimmediate cause�n�F���̍s���������N������Ă��钼�ڂ̗v���͂Ȃ낤���m�����I�A�S���I�A�Љ�I���J�j�Y�� �n
2�D���ɗv���m�i���v���Ƃ����Gultimate cause�n�F���̍s���́A�ǂ�ȋ@�\�����邩��i�����ė����̂��낤���B�i���I�ɂǂ̂悤�ȈӖ����������̂��B�m�ǂ̂悤�ɓK���I�������̂��B�n
3�D���B�v���F���̍s���́A�����̌̂̈ꐶ�̊ԂɁA���̂悤�Ȕ��B�����ǂ��Ċ��������̂��낤���B�m�ǂ̂悤�ɂ��ďK������Ă������B�n
4�D�n�������v���F���̍s���́A���̓����̐i���̉ߒ��ŁA�ǂ̑c��^����ǂ̂悤�ȓ������Ƃ��ďo�����Ă����̂��낤���B([110])
�@������́A�����_�ł͂܂����肵���Ȃ����A�O�q��Stearns�������ŋߎ��̍��ۊw��ŁA�i���S���w�ɑ��Ē悵���^����A�{�e�Łu�i���S���w�v��傫�����グ�Ă���M�҂Ƃ��Ă͐^���Ɏ~�߁A���̋^��̈ʒu�Â����s�������B�Ȍ��Ɍ����ASterns�����̋^��́A<�i���S���w�́u���W�v�̖��̉��ɘ_�����Ă���ŋ߂̑����̖��ƁA������������o����Ă��邩�Ɍ�����u���_�v�́A�܂����n(premature)�ł���>�Ƃ������Ƃł���A���̎咣�̍�����T��A<�i���S���w���A��L�́u4�̂Ȃ��v�̂����A�u2. ���ɗv���v�Ɓu4�D�n�������v���v�m����2���L�`�́u���ɗv���v�Ƃ܂Ƃ߂ČĂԂ��Ƃ�����n�Ƃ������Ƃ��āA���R�Â����A���_���o���Ă���̂ɑ��A�u1�D���ߗv���v����сu3�D���B�v���v�m����2���L�`�́u���ߗv���v�Ƃ܂Ƃ߂ČĂԂ��Ƃ�����n�ɂ�闝�R�t���A��������A�������Ŏ�ɐG�����(tangible)�f�[�^�E���R�������ɘ_����Ă��镔�������܂�ɏ��Ȃ�>�Ƃ������Ƃɐs���邩�Ǝv����B
�@����ɑ���A�i���S���w�҂̑�����̒��ځE�Ԑڂ̔����E���_�Ƃ��ẮA�܂���Stearns�������w�E����Ƃ���A����́A�L�`�́u���ɗv���v�݂̂Ȃ炸�A�L�`�́u���ߗv���v��tangible�ȃf�[�^�̗��t������ɁA�i���S���w�̐��ʂ𗝘_�I�ɂ������Â��A�_���Ă������Ƃ����������ł���Ƃ݂���B
�@����Ƃ��ẮA���łɑO���́i�Q�j�ŊȒP�Ɍ��y�������A�ߔN�ALeda Cosmides�����߂Ƃ���i���S���w�҂́A�l�Ԃ̐S���E�s���Ɍ��т��]�̓������A���́u���W���[��(module)�v�Ƃ��ĂƂ炦�A��̉ۑ�ɑ��ăq�g�i���̑��̐����j���̂锽�������߂�ۂ̔]�̓����́A�����������W���[���������A�����I�ɋ@�\���āA�������o���A�s���Ɍ��т��Ă���A�Ƃ����l��������Ă���B�����ɁA�܂�premature�Ȓi�K�ł͂��낤�Ƃ��A�]�Ȋw�̐V���Ȓm�����������A�L�`�́u���ߗv���v��tangible�ȃf�[�^�̒~�ς�ڎw���A�i���S���w�̐��ʂ������Â��A�_���悤�Ƃ������݂�����B
�@����Ƃ��ẮAJulian
Lim, Daniel Sznycer, Andrew W. Delton, Theresa E. Robertson, John Tooby, Leda
Cosmides�ɂ��Stearns�����̋^�`�Ɠ���HBES 2009�ł̌������\�A"The role of welfare tradeoff
ratios in reciprocity"([111])�m�u�b���ɂ�����welfare tradeoff ratios�̖����v�n�ŁA�M�҂̎茳�T��([112])�ł́A���\����Leda Cosimides�́A�l�̔]���̃��W���[���̍�p�Ƃ��đ����A�u���ߗv���v��tangible�ȃf�[�^�̒~�ςɂ��A���̔��\���e��_���悤�Ƃ������݂Ă���ƌ���ꂽ�B
�@��Q�߁@�u�@�Ɛi���S���w�v�̉\��
�@�O�߂ŏq�ׂ��A�u�i�������w�Ƃ��̋ߔN�̂߂��܂������W�v�������Ă݂�A���̋^�`�͒悳��Ă͂�����̂́A�u�@�Ɛi���S���w�v�̐V���ȉ\���Ƃ��Ă͈ȉ������łɖ����ƂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�O�߁E�i�P�j�u�S���J�[�h���v�Ŏ������Ƃ���A���[���ɑ���u����Ҍ��m�v�̒m�\���A�q�g�ł͓��ɐi�������ƍl������̂ł���Ȃ�A���̐i���I��Ղ́A�l�ގЉ�ɂ�����u�@�v�E�@���x�̐����ƁA���̎�e�A���m�O��Ǝ{�s(enforcement)�ɍۂ��ẮA���ɗL���Ɂi�v���X�Ɂj�������ƍl���邱�Ƃ��ł���B��������A�q�g�̖@�̖@���̈ꕔ���A�i���S���w�Ŏ����ꂽ�q�g�̐i���I��Ղɋ��߂邱�Ƃ͏\���ɉ\�ł��낤�B
�@��R�߁@�u�@�Ɛi���S���w�v�̎g���ƌ��E
�@���łɑ�Q�́E��R�߂ŁA�u�@�Ɛi�������w�v�̎g���ƌ��E�ɂ��ďq�ׂ����A���̘g�g�݂́A��{�I�Ɂu�@�Ɛi���S���w�v�ɂ����Ă͂܂�B���Ȃ킿�A�u�@�Ɛi���S���w�v�̎g�����A�@�́u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���A�u�@���v�̋��������Ă���������葽�����u�q�g�̐i���I��Ձv�ɋ��߂���������邱�Ƃɂ���B���̌��E�Ƃ��ẮA�{��P���E��P�́E��R�߁E�i�P�j�̐}�P�̂Ƃ���A�u�@�E�@���v�i�W���`�j�ƁA�{�e�́u�i�q�g�́j�@�v�̒�`���e�i�W���a�j�́A��v���Ȃ��B���������āA�u�@�E�@���v�ƌĂ����̂̓��A�V���ȁu�q�g�̖@�v�̒�`�͈̔͂��珜����镔���ɂ��ẮA�u�@�Ɛi���S���w�v�̎�@�������Ă��Ă��A�_�����݂邱�Ƃ͂��Ȃ��B�ڍׂ́A��Q���E��Q�͂ɏ���B
��S�́u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v
�@��P�߁@�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v�O�҂̑��݊W
�@�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v�O�҂̑��݊W�́A�[�I�Ɍ����Ύ��̂悤�ɂȂ�B
�@���q�̒ʂ�A�i�������w�̓_�[�E�B���̊�b���_�̏�ɁA�Ꭶ�I�ɂ�1970�N��O��̃n�~���g���A�g�����@�[�Y�̗��_�I�\�z�Ĕ��W�����w��ł���B�i���S���w�́A���̐i�������w�̊�Ղ̏�ɁA����u�V���ȏ�v���\�z���悤�Ƃ������݂ł���A�i���Ɛl�ԍs�����A�i�������w�Ɠ��l�ɁA�q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��ՂɊ�Â��A�����Ȃ�u�S���v��i�������Ă������Ƃ��i���I�ɗL���������̂��A���������悤�Ƃ��Ă���B���̈Ӗ��ŁA�i�������w�E�i���S���w�̗��҂́A�q�g�̐����Ƃ��Ă�700���N�̐i���I��ՂɊ�Â��A�i���Ɛl�ԍs���E�S���̊W���𖾂��悤�A�Ƃ����_�ɂ����Đ헪��������B��������A����2�̊w��́A��R�́E��P�߁i�R�j�ɑO�q�����u�e�B���o�[�Q���̎l�̂Ȃ��v�̂����A���ߗv���ɋ����S�����A���ɗv�����������悤�A�Ƃ����������S�����݂���B
�@����ɑ��āA�s����`�w�́A�{�́E��R�߁A���Ɂi�Q�j�́ia�j�ł���q����Ƃ���A���ɗv���ɊS���Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A����������ߗv���ɋ���ȊS�̏œ_�𒆂ĂĂ���B�Ȍ��Ɍ����A�ߔN�̍s����`�w�̒��S�I���S�́A<��`�q�ɂ���č\�z���ꂽ�����̂̐����I���J�j�Y�����A���̌̂́i�o���O���܂߂āj�A�o����̊��̉e�����A���݂̍�p�Ƃ��āu�n���I(emergenic)�v�ɂ����Ȃ�s���ݏo���̂�>�ɂ���B��������A���̏d�_�́A�i�i�����ӎ�����Ƃ��Ă��A���́j���ߗv���ɂ���A���ɗv���ɂ͂قƂ�ǂȂ��B�܂��ɁA�e�B���o�[�Q���́u4�̂Ȃ��v�́u���ߗv���v�̂����ȉ��̓�_�ɊS���i���Ă���̂��s����`�w�Ȃ̂ł���F
1�D���ߗv���F���̍s���ڈ����N���������I���J�j�Y���B�i�S���I�A�Љ�I���J�j�Y���ɂ���S���قƂ�ǎ����Ȃ��B�j
2�D���B�v���F���̍s���͂ǂ̂悤�ɂ��ďK������Ă������B�i���̓T�^���A�s����`�w�̒��ł��A��q����o���������̎�@�ł���B�j
�@�ƂȂ�ƁA�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v�̑��݊W�́A���̂悤������B
�@�{�e�`���ɒ����Ƃ���A�u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���A�u�q�g�́v�@�̒�`���A�u�����Ƃ��Ă̓����̈��Ƃ��Ẵq�g�́A�i���Ɋ�Ղ����A�L�͈͂ŁA���������E�s��������Ȃ��A���[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�Ƃ��Ă���B�ł���ȏ�A�O�҂̘_�ƁA��҂̑Ó����́A�܂��́A�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi�������w�v�̊w�ۓI��@��p���A�q�g�̍s���́u���ɗv���v�Ɗ֘A�����Ę_���邱�ƂɂȂ�B
�@�������Ȃ��瓯���ɁA�s����`�w�́A�J��Ԃ����A�{�́E��R�߁i�Q�j�ia�j�Ō�q����悤�ɁA�q�g��700���N�̐i���̉ߒ��ŏW�ς��Ă����A���ݕۗL���Ă����`�q�Q���A�i���Ƒ��ݍ�p�������A�n���I�Ɂj�ǂ̂悤�Ȑl�ԍs���ݏo���̂��A���̎��ߗv�����𖾂��Ă������҂����Ă�w��ł���B�@���A�u�i���Ɋ�Ղ����m�c�n�������E�s��������Ȃ��A���[���E�s�K�́v�ƒ�`�����ȏ�A��`�q�Q���A���ꂪ���ݏo���l�ԍs���ɁA���́u���[���E�s���K�́v��^���Ă���i�\��������j�Ƃ�����A�u�@�ƈ�`�w�v�́A�u�@�ƍs����`�w�v�̊w�ۓI��@��p����A�u���ɗv���v��������ł���q�g�́i�@�̒�`�̈ꕔ�ł���j�s���K�͂́u���ߗv���v���𖾂���\�����߂Ă���B
�@��q���邪�A���܂ŁA�w��E�ł́A����ł͐i�������w�E�i���S���w���A�����ōs����`�w�̌������A�i�߂��Ă���A����2�̕���̋����W�͂قƂ�ǂ݂��Ȃ������B�{�e�ł́A�u�@�v���肪����ɁA�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v�O�҂𑊌݂Ɍ��т��A�u�@�v�����������i����̋��ɗv���ƁA���ߗv���o���̉𖾂ɖ𗧂Ă悤�A�Ƃ�����]�������Ă���̂ł���B([113])
�@��Q�߁@�u�i����̓����i�I���j�͌̂̈�`�q�ɒ��ړ����v
�@�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v�̑��݊W��������邽�߂ɁA�O�߂ł́A�i�������w�E�i���S���w�ƁA�s����`�w�̊W����������B�{�߂ł́A���������ɐ[�߁A�����O��҂ƌ�҂͎��́A�w�E�ň����Ă��������w���ڂȊW�ɂ���̂��A�Ƃ������Ƃ�_�������B
�@�i�P�j���`���[�h�E�h�[�L���X���w���ȓI�Ȉ�`�q�x�Ƃ��̉e��
�@Richard Dawkins
�i���`���[�h�E�h�[�L���X�j��1976�N�̒����AThe Selfish Gene([114])(�a��^�C�g���w���ȓI�Ȉ�`�q�x�j([115])�ŁA<selection�i�I���j�͌̂̈�`�q�ɒ��ړ���>�Ƃ���������f�����̂͂��܂�ɗL���ł���B���̖���́A����嗬�̐i�������w�҂ɂƂ��Ắu�^���p���_�C���v�ƌĂ�ł��悢�Ӗ��������Ă���B����ɂ͏��Ȃ��Ƃ�2�̈Ӌ`������B
�@��1�ɁA�_�[�E�B����selection�i�I���j�̊T�O�́A�u��̕ۑ��v�Ɋ�^������̂ł͌����Ė����A�����܂Ō̈��̈�`�q�ɒ��ړ����A<���̌̂̈�`�q���ǂꂾ���c���Ă�����>�Ƃ����c�_�ɏW���A�Ƃ������Ƃł���B�i�i�Q�j�Ō�q���邪�A�u��̕ۑ��v�Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A"group selection"�m�W�c�I���E�W�c�����n�̊T�O�ƑÓ������咣����A�����h��David Wilson�̐��͑Ó����Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B�j
�@��2�ɁA�_�[�E�B�����咣����selection�i�I���j�̌��ʂ́A�����̊e�̒��̈�`�q�ɂ����W�ς��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B�����ɁA�O�߂ŏq�ׂ��A�i�������w�E�i���S���w�ƁA�s����`�w�̐ړ_������B�i�������w�������͂��������̂́A��`�q�̑��݂���m��ꂸ�A�܂��Ă�1953�N��James Watson �i�W�F�C���Y�E���g�\���j��Francis Crick �i�t�����V�X�E�N���b�N�j�ɂ��悤�₭�������ꂽ�A��`�q��S��DNA�̓�d�点��\������m���Ȃ��������ォ��A�I���A�ψفA�i���A�Ƃ����T�O����A���̑Ó�����_�ł������Ƃɂ���B�������A��`�q��S��DNA�̓�d�点��̔����́A�_�[�E�B���̗��_���u��`�q�v�Ƃ�������u����v�Ō�����\���������炵���B���̌����͍������W�r��ɂ���B��X�́A�q�g�A�`���p���W�[�A�~�c�o�`�A�V���E�W���E�o�G�A��A���̑������̐����̃Q�m����ǂ����������Ă��邪�A�Q�m����̈�`�q�Ƃ��̋@�\�̉𖾂́A���i�����Ƃ͂����A�܂��܂��u�����ē������v�ł���B�Ƃ͂����A�I���̌��ʂ��A�����̒��̈�`�q�ɏW�ς��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�����Ă��̈�`�q���̂Ƌ@�\�̉𖾂́A�i�������w�E�i���S���w���i�����ɋ��ɗv���ɂ��āj�𖾂��悤�Ɛs�͂��Ă����A�q�g�̍s���̎��ߗv���̉𖾂ɂ����ځE�ԐڂɘA������B�h�[�L���X�̎咣�́A�������āA�i�������w�E�i���S���w�E�s����`�w�̋�������C�ɏk�߂邱�ƂɂȂ����A�Ƃ����̂��M�҂̌����ł���i���̂��Ƃ��A�������ʂƂ��Č�������̂ɂ͂܂��܂����\�N�������낤�Ƃ��A�������k�߂��̂͊ԈႢ�Ȃ��j�B
�@�i�Q�j��_�@�������Ƃ��Ắugroup
selection���W�c�����i�I���j���v�i�f�B���B�b�h�ES�E�E�B���\���j
�@�h�[�L���X��<�^���p���_�C��>�ɑ��āA�^��������_����ł���̂��AState University of New York, Binghamton �i���́FBinghamton University, �A�����J�E�j���[�E���[�N�B�j, Department of Biological
Sciences (Joint appointment with Anthropology)��Professor�ł���ADavid Sloan
Wilson�i�f�B���B�b�h�E�X���[���E�E�B���\���j����([116])�ł���B
�@�ނ́A�h�[�L���X��<selection�i�I���j�͌̂̈�`�q�ɒ��ړ����̂ŁA����group�i�W�c�j����̂Ƃ��đI������邱�Ƃ͂Ȃ�>�Ƃ����߂Ɉًc�������Agroup selection �i�W�c�I���j�_�A([117])��萳�m�ɂ�multi-level selection�_����Ă���B�������Ȃ���A���ڂ��Ă��������B
�m�ȏ�F�Q�O�P�O�N�U���P�S���܂łɏ����Č��\���Ă��������ł��B�a�c���F�n
�@��R�߁@��`�q�ɂ���ē`��铮���E�q�g�̍s���H�|�u�s����`�w�v
�@�u�s����`�w(behavioral genetics)�v�Ƃ́A���������A��`�q�ɂ���ē`��铮���E�q�g�̍s���A��������A��`�q�ƍs���̊W����������w��ł������B�������A�ŋߎ��̌����́A�����Ђƌ��ł͌�����Ȃ��ǖʂ𑽁X�܂�ł���B�{�߂ł́A�s����`�w�Ƃ͉������܂߂āA�u�@�ƍs����`�w�v�Ƃ����V���Ȋw�ە���ŁA�����Ȃ鐬�ʂ����҂ł��邩���ȒP�ɏ��q����B
�@�_�[�E�B���́A��`�q�̑��݂̉𖾂�҂����ɁA�����́u�`���v���A���R�I���E���I���ɂ���`����邱�Ƃ�O��ɁA�ނ̐i���_���������Ă��B�������A�i�������w���傫�ȉۑ�Ƃ��鐶���́u�s���v�i�̐i���j���A���R�I���E���I���ɂ���`����邱�Ƃ́A���N�A�i�������w�҂̊Ԃł�����u�����v�Ƃ��đO��Ƃ���Ă������A���́u�����E�d�g�݁E�@�\�v�͕�����Ȃ��܂܁A���Ȃ킿�u���b�N�{�b�N�X�ƂȂ�����Ԃł������B
�@���̋ǖʂɍI����^���Ă������̂Ƃ��Ċ��҂���Ă���̂��A�s����`�w�ł���B
�@�������Ȃ���A20���I�̈ꎞ���ɎU�����ꂽ�A��`�q���l�ԑ��̓����̍s�������肷��Ƃ����u��`�q����_�v�A�t�ɁA���������s�������肷��Ƃ����u������_�v�A������������S�Ȑ����͂������Ȃ��܂܁A��X��21���I�ɓ˓������B�Ȍ��Ɍ����A���݂̍s����`�w�ł́ANature vs. Nurture �i���܂ꂩ�炿���G��`�q�������j�Ƃ������c�_�͂��͂⎞��x��Ƃ���ANature AND Nurture�A([118])���Ȃ킿���܂�ƈ炿�A��`�q�Ɗ����u�n���I(emergenic)�ɑ��݂ɍ�p���A�q�g�E�����̍s���ݏo���A�ƍl�����Ă���B
�@�i�P�j��`�q�ɂ��`��铮���E�q�g�̍s�����x���鐶���I���J�j�Y��
�@�����������ł��A�ȉ��̑O��͊m�F���Ă��������B
�@�@�ia�j���̓������ʏ퐱���������O��ɁA���̈�`�q�̃Z�b�g�������������́A�o���O��̊��Ƒ��ݍ�p���A���̌`�������B
�@�@�ib�j���́ia�j��O��ɁA��`�q�ɂ��K�肳��铮���E�q�g�̐����I���J�j�Y���́A�n���I�ɂ���A���̍s�����x����Ɛ��������i�܂��A���̎��ؗ�([119])�����X����j�B
�@�@�ic�j�ȏ�ia�j�ib�j��O��Ƃ���A���̊����ŁA���̈�`�q�������Ƃ́A���̍s���ݏo���P�[�X�����X����Ɛ��������B
�@�M�҂Ƃ��ẮA�ib�j�̑O�A��`�q�ɂ��K�肳��铮���E�q�g�̐����I���J�j�Y�����A���̍s�����x����Ƃ������ؗ���d�����A���̌�̘_�|��W�J���Ă��������B
�@�i�Q�j�u�s����`�w�v�E���̉\���E���E
�@�{�Z�N�V�����ł́A�s����`�w�Ƃ͉���������x�m�F���A���̉\���ƌ��E��T���Ă݂����B
�@�@�ia�j�s����`�w�Ƃ͉���
�@�s����`�w�Ƃ͉����A��`�͉��ʂ肩������B�����Ƃ��ȒP�Ȃ��̂ł́A<�Љ�A�U�����A���_�I�\�͂Ƃ������S���I�ȓ�������`�����x�����̌����ł���>�Ƃ������̂���n�܂�A<��`�Ɗ��̊W���A�l�̍s���̍��������Ɍ��肷�邩�̌���>�Ƃ������̂�����A<��`�w�̈ꕪ��ŁA��`�I�X���ƁA�ώ@�����s���Ƃ̊Ԃ̊W�����錤��>�Ƃ������̂�����B([120])�Ƃ肠�����A�����ł͈�U�A�������N�Ƒ�؏G��ɂ��A�ȉ��̒�`�ɏ]���Ă��������F�u�l�ԍs���Ƃ�������߂č����ȁA�����w�I�V�X�e���ƎЉ�I�V�X�e���̃C���^�[�t�F�C�X�̒��ɑn�o�����w��`�x���ۂ������w��v�ł���A�u���Ƃ��ƐS���w�������Ă����`����ʓI��`�w(Quantative
Genetics)�̃��f���ɓ��Ă͂߂��A����Ίw��I�G��v([121])�ł���A�Ƃ������̂ł���B
�@�Ȃ��A�������N��������A�M�ҁE�a�c���̃��[���ɂ�邲�����ɂ��A�s����`�w�̕�I�Ȓ�`�Ƃ��ẮA�u�s���̌l���ɋy�ڂ���`�Ɗ��̉e���𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ���Ȋw�v�ƌ����\�����Ƃ��\�ł���A���ɗ��ӂ��ׂ��_�́u�s���̕��Ր��ł͂Ȃ��l�����Ƃ������ƂƁA��`�����łȂ����̉e�����ΏۂƂ��Ă���v�Ƃ��Ƃ������Ƃł���B([122])
�@����ɁA�s����`�w�҂Ƃ��Ē�����Robert Plomin�̕�����������A�����ɏq�ׂ�ꂽ�A�u�s����`�w�v�̃A�v���[�`���A���̃A�v���[�`�ɑ��Ď��D�ʂȓ_�̊T��([123])�ƁA����Plomin�������҂ɓ����Ă��镶���ɂ�����A�s����`�w�̖ڎw�����ڕW([124])�𒍋L���Ă����B
�@�@�ib�jRobert Plomin�̍s����`�w�A�������N�̑o��������
�@�s����`�w�E�ŁA���ɉp�ꌗ�ŁA�s����`�w�̂�����u���ȏ��v�^�C�v�̊w�p���͂��łɉ������o����Ă���B�����ł͗Ꭶ�I�ɁA���̒��̂��������Љ�A�s����`�w�ɂ����āA��`�q��������A����������x������Ă��Ȃ����Ƃ��Ċm�F�������B
�@�����ł���͂�K��I�ȋ��ȏ��I�������ʂ����Ă��鏑�Ђ́A�܂���1980�N����Robert Plomin���n�߁A���̋�����J.C. DeFries, G.E. McClearn��3�l�ɂ��Behavioral genetics : a primer([125])�m�w�s����`�w�F���发�x�n�ł���B���̒��͔ł��d�ˁA���Ƃ��Α�2�ł�1990�N([126])�A��4�ł��O�L��3�l�̒��҂�Peter McGuffin��������2000�N�ɏo�ł���A([127])����ɑ�5�ł͓���4�����҂ɂ��2008�N�ɏo�ł���Ă���B([128])
�@����ɁA���łɏq�ׂ��Ƃ���A"Nature
vs. Nurture"�ł͂Ȃ��A"Nature
and Nurture"�̊ϓ_���珑���ꂽ�w�p���Ƃ��āA�܂��A�܂��ɂ��̂��̂����C���^�C�g���ƂȂ��Ă���ARobert Plomin�ɂ��1990�N�̒��ANature and nurture : an introduction to
human behavioral genetics([129])�������Ă����B���̒�����R. �v���~�����^�������N�A��؏G�ꋤ��w��`�Ɗ��F�l�ԍs����`�w����x�Ƃ��Ęa�������Ă���B([130])���ɁA2006�N��Sir Michael
Rutter���AGenes and Behavior:
Nature-Nurture Interplay Explained ([131])�ɂ����ڂ��ׂ��ł��낤�iM. ���^�[���^�������N��w��`�q�͍s���������Ɍ�邩�x�Ƃ����a�������Ă���B([132])�j
�@���āA���{�ɖڂ�]���悤�B�c���w���w�������̈������N�́A�s����`�w�����̈�Ƃ��āA�u��s���ӂ����v���W�F�N�g�v�iTokyo Twin Cohort Project ; ����ToTCoP�F�Ȋw�Z�p�U���@�\�ɂ��j�ƁA���l�o������ΏۂƂ����u�c��`�m�o���������v�iKeio Twin Studies �G����KTS�F�Ȍ���E���B�ɂ��j�𒆐S�Ƃ������������𐄐i���Ă���B������2�Ƃ��i���ɑO�ҁj�A���܂œ��{�ɗ�����Ȃ���K�͂̑o���������v���W�F�N�g�ł���B�s����`�w�ɂ�����o���������̗L�����́A���ł�Plomin�������i�O�q�̋��ȏ��j�ł��ɂƂ肠���Ă��邪�A�������N�̌����`�[���̕\������Ē[�I�Ɍ����Έȉ��̂Ƃ���ł���F
�ꗑ���o�����͈�`�q��100�����L���Ă��邪�A���o������50%�������L���Ă��Ȃ��B��������������͂ǂ�����قړ����ł���B���������āA�����ꗑ���o�����ǂ����̕����A���o�����ǂ�����莗�Ă���Ƃ�����A�����ɂ͈�`�̉e��������ƍl�����B�܂��A�ꗑ���o�����ɈႢ������A����͂��傤�������ꂼ��ɓƎ��̊��̉e�����A����ɓ��o�����ł��悭���Ă���A�ꏏ�Ɉ�������̉e�����������ƍl���邱�Ƃ��ł���B���̂悤�Ȍ������@��o�����@�ƌ����A���R�Ȋw��Љ�Ȋw�̂ЂƂ̃A�v���[�`�Ƃ��Đ��E�I�ɉ��p����Ă���B([133])
�@��������������@���̂�A�������N�́A�܂��u�c��`�m�o���������v�ł�1998�N�����ȗ��A��s���ݏZ�̂��悻1000�g�̐N���A���l���̑o������ΏۂɌ����v���W�F�N�g�����{���A����œ����Ă��炤���⎆�����A([134])���邢�͌c��`�m��w�܂ŗ��Ă��炤���Z�����ɋ��͂����߁A����܂ő����̌������ʂ������Ă����B([135])
�@����ƕ��s���A�������N�́A�u��s���ӂ����v���W�F�N�g�iTokyo Twin Cohort Project; ���́uTOTCOP�v�j�v��2004�N12���ɃX�^�[�g�����A2009�N11���܂ł�5�N�ԂɊ����������B����͓Ɨ��s���@�l�E�Ȋw�Z�p�U���@�\�u�]�Ȋw�Ƌ���v�Ƃ��������v���O�����̈�тƂ��čs��ꂽ�u�o�����@�ɂ������E�c���̔���c�f�����v�Ƃ������������ƂȂ��Ă���B([136])
�@���̃v���W�F�N�g�́A�u���2005�N�Ɏ�s��(�����s�A��t���A��ʌ��A�_�ސ쌧)�Ő��܂��o�����̎��F�I���W�X�g���[���쐬���A���̂�����2000�g�̋��͂āA�A���P�[�g��ʖʐڒ����A�����Č��g�|�O���t�B�[�ɂ�钲���Ȃǂɂ���āA�S�g�̔��B�ߒ���5�N�Ԃɂ킽��c�f�I�ɒ����v([137])���s���Ă���B���̌��ʁA�u���̌�������A�C����^���\�́A�F�m�E����\�́A���s���Ȃǂ��A��`�A�Ƒ������L������A��l��l�ɓƎ��ȔL������A���B�ߒ��̂ǂ̎��_�ŁA���ꂼ��ǂ̒��x�̉e�����Ă��邩���킩��A�q�ǂ��̌��₩�Ȕ��B���x���邽�߂̋�������l�����ł̊�b����v([138])���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B��̓I�ɂ́F
�@���u�A���P�[�g�ǁi���⎆�����j�v([139])
�@���u�j���X��(���g�|�O���t�B����)�v�i�u���̋߂��̐_�o�����𑪒肵�āA���Ƃ�Љ�̋@�\����`����̉e�����ǂ̂悤�ɎĂ��邩�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��������v�j([140])
�@���u�ƒ�K��ǁi�ƒ�K�⒲���j�v�i�u�ӂ����̐e�q�W�₫�傤�����W���A�����ɔ����Ăǂ̂悤�ɕω����Ă��������A���ƒ�ōs�����B������V�т̊ώ@�Ȃǂ�ʂ��Ė��炩�ɂ��Ă������Ƃ��������m�c�n�B�C�ӂł����͂������������ƒ�ɁA���q���܂�����1����5�܂ł̊Ԃɍő���5��K�₳���āv������Ă���j([141])
�@���u�Ȃ��ܔǁi���t�ƎЉ�̒����j�v�i�u�����͂���������ꕔ�̂��ƒ�ɁA���ƂƎЉ�̔��B�Ɋւ��钲�������肢���āv����A�o�������u�C���X�g�₨������ŗV�ԂȂ��ŁA���Ƃ�Љ�̔��B���ώ@���钲���v�ł���A�u����������ɕۂ��߂ƏW�c�`���ł̒����̂��߁A�c��`�m��w���̎{�݂܂ł����J�����肢���m�c�n�����N��̂ӂ����̂��q���܂������ƒ�ƌ𗬂ł����v�ɂ��Ȃ��Ă���j([142])
�c�̂S�̒����ǂ��琬�藧���Ă���B���̋K�͂́A��萸�m�ɂ́A�����Ƃ��傫���u�A���P�[�g�ǁv�ɂ����ẮA���9��������14�����̑o����1700�g�ɑ��čs���Ă���B�u�A���P�[�g�ǁv�͎Q���ґS�Ă̐l�ɁA�����āu�j���X�ǁv�A�u�ƒ�K��ǁv�A�u�Ȃ��ܔǁv�́A���̒��ł���ɂ���ɎQ�����悤�Ƃ����ĉ��������ƒ��ΏۂƂ��Ă���Ƃ����`������Ă���B�܂��A1��݂̂�3�˂���26�˂܂ł̓����ɂ�鉡�f������4000�g�ŁA���Ƃ��Ă͈�ԑ傫���Ȃ��Ă���B([143])�ȏ�̂悤�ɁA���̃v���W�F�N�g�́A���{�ōs��ꂽ���̎�̑o���������̒��ł͍ł��K�͂��傫���A���̌�������([144])�͍�������ڂ����ׂ����̂ł���B
�@����Ɉ����́A�Ȋw��������擾���A2009�N�x����2011�N�x�ɂ킽��A�u�Љ�ƃ����^���w���X�̑o���������F��`�q�Ɣ]�������Ȃ��v�Ƃ��������������グ�Ă���A���̌����̖ړI�́F
�����A���E�I�ɂ́A�u��`�q�|�]�|�s���v�������I�Ɍ��ѕt����s���_�o�Q�m�~�N�X�̋������ɍ����|���낤�Ƃ��������ɂ��邪�A�����ł͖����G��I�Ȓi�K�ɉ߂����A�Ƃ�킯�A�o�����Ƃ�����`����̌n�I�ɓ����ł���T���v���Ɋ�Â������Ɍ���ƁA����͐��E�I�ɂ��ł���B�����ŁA�{�����́A����܂łɒ~�ς��Ă����o�����@�ɂ��l�ԍs����`�w�I�����̒m�����A�]�Ȋw�E���q�����w�ƗZ�������A�Љ�Ȋw�Ɛ����Ȋw�̋��E�̈�ɂ����āA�l�Ԃ̐����E�Љ�I�ȓK���s���̃��J�j�Y�����w��`�Ɗ��x�Ƃ������ʂ���T������B���̂��߂ɑ��ʓI�ȃA�v���[�`(i.e., ��`�q�����f�[�^�A�]�摜�f�[�^�A�S���E�s���f�[�^)�ɂ���āA���ݍ�p�I���ʃl�b�g���[�N���\�z���邱�Ƃ�ʂ��A���Ɋ�Â��Љ�I�K��(e.g., �����K���C�w�Z�K���C�E��K��)�̉ߒ��𖾂炩�ɂ��A�V����������ƎЉ���̃��f���̒T�����s�Ȃ��B
�Ƃ������̂ł���B���̑Ώۂ́A�u�c���E�������o�����R�z�[�g(12 �����`5��)1500 �g�ƐN���l���o�����R�z�[�g(20 �`35 ��)1500 �g�B����܂łɋ��͂̓����Ă���ƒ�ɉ����A�V���ȋ��͉ƒ���W����B����2�R�z�[�g���A3�N�Ԃɂ킽��v�����Ώۂɂ��Ă����A�Ƃ������̂ł���A�u�������@�Ɠ��e�v�́A��͂�u(1)�X���Eweb �`���ɂ��A���P�[�g�����@(2) �ƒ�K��E���Z�`���ɂ��ʍs�������@(3) NIRS, MRI �ɂ��]�\���E�@�\�����@(4) SNP �̑S�Q�m���X�L�����ɂ���`�q�����v�Ƃ���Ă���B����̐��ʂ����҂����B([145])
�@�@�ic�j�u�@�ƍs����`�w�v
�@�s����`�w�̒�`�ɂ́A<��`�Ɗ��̊W���A�l�̍s���̍��������Ɍ��肷�邩�̌���>�Ƃ������̂�����A<��`�w�̈ꕪ��ŁA��`�I�X���ƁA�ώ@�����s���Ƃ̊Ԃ̊W�����錤��>�Ƃ������̂����邱�Ƃ͊��ɂ݂��B������ɂ���A�s����`�w�́A<��`�Ɗ����l�Ԃ̍s���������ɋK�����Ă��邩>�������Ώۂɂ��Ă���킯�ł���B���āA��������̖@�E�@���̒�`�͈�U�����āA�{�e�̖`���ł́u�@�v�̒�`������x�v���������Ă������������F�u�����Ƃ��Ă̓����i�̈��Ƃ��Ẵq�g�j�́A�i���Ɋ�Ղ����A�L�͈͂ŁA���������E�s��������Ȃ��A���[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�ł���B�u���[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɐ��ق��v�̂ł��邩��A�����ł��@���l�Ԃ̍s�����K�����Ă��邱�Ƃ͎����ł���B
�@�ȏ��O��ɂ���A�s����`�w�̍���̔��W�ɂ��A�u�@�ƍs����`�w�v�̑��݊W�A��������A�s����`�w�ɂ���Ė@�E�@���ۂ���葽�������\�ƂȂ邱�Ƃ����҂����A�Ƃ����̂��M�ҁE�a�c�̗\���ł���B
�@��S�߁@�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��q�g�̍s��
�@�i�P�j�q�g�̍s���͂ǂ��܂Łu���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��̂��H
�@<�q�g�̍s���͂ǂ��܂Łu���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��̂��H>�Ƃ����̂́A�×�����N�w�҂�Y�܂��Ă������ł���B��O���ł���M�҂ɂ́A�c�O�Ȃ���A�����Ă����ŌÍ������̕�������������A�������j�̒��Œ~�ς���Ă����������ʂ��܂Ƃ߂��肷��\�͂͂Ȃ��B�������A��T�́E��R�߂ŏЉ��A�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ƃ����V���ȕ���ŁABrent Garland �i�u�����g�E�K�[�����h�j���ҏW���A�����̊w�҂ƈꏏ�ɋ������Ƃ���2004�N�Ɍ�������Neuroscience
and the Law: Brain, Mind, and the Scales of Justice([146])�̃u�����g�E�K�[�����h�ҏW�^�ÒJ�a�m�E�v���T�q��w�]�Ȋw�Ɨϗ��Ɩ@�|�_�o�ϗ��w����x([147])�Ƃ����a���o�Ă��钘���ɁA�܂��͒��ڂ��Ă����Ă������������B���ɂ��̒��ł��A���T��Part II��"Comissioned
Papers"�̂����AMichael S. Gazzaniga
& Megan S. Steven�ɂ��"6. Free
Will in the Twenty-first Ceuntury: A Discussion of Neuroscience and the
Law"(pp. 51-70)�ɒ��ڂ��ꂽ���B�i�a���ł́A�u��II�� ���_���v�̂����́u��́@��ꐢ�I�ɂ����鎩�R�ӎv�v56-78�łł���B�j
�@�i�Q�j�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��i�H�j�q�g�̍s���̎���
�@���łɏq�ׂ��Ƃ���A�{���̖ړI�́A<�q�g�̍s���͂ǂ��܂Łu���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��̂��H>�̂��ׂĂ��𖾂��邱�Ƃɂ͂Ȃ��B�����A�i�������w�E�i���S���w�Ƃ������삩��A<�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��q�g�̍s���̎��Ⴊ����̂ł͂Ȃ����H>�Ƃ����Ƃ����₢�����ɉ����A�����x�̘_���Ȃ���Ă��邱�Ƃ��A�Ꭶ����ɂƂǂ߂����B����ɂ��A��Q���̑�P�́E��P�߁A��Q�́E��P�߂ւ̓����Ƃ������B
�@���̍��ŏЉ�����̂́A2009�N�Ɋ��s���ꂽ�A����e�b���w�i���p���Ȋw����x([148])�Ƃ������Ђł���B�����ǂ���u��h�v�ȃ^�C�g���ɂ�������炸�A�{���͊���274-303�ł�30�łɂ킽���ĕt���ꂽ409�_�̘_�����f�����Q�l�������X�g�i����9���ȏ�́A�e����̍Ő�[���s���_�l����̂Ƃ����p��̘_���ł���j�ƁA��������R���݂Ɉ��p�����{��������Δ���Ƃ���A��������w��I�ɍ����t�����ꂽ���e�����P�s���ł���B�{���ł́A���̒�����A�ȉ���2�_����Ɏ�肾���āA�`���I�ȈӖ��Łu��̓I�E�ϋɓI�Ɏv�l���ꂽ��ł̔��f�A���Ȃ킿���R�ӎu�E���R�ȑI���Ɋ�Â��q�g�̍s���v�̗�O�����݂���A�Ƃ������Ƃ����������B
�@�@�ia�j�����ɂ��j���́u��v�̑I�D��
�@�܂��́A�����̑�4�́u�����j�����e��킯�v�̑�2�Z�N�V�����u�w�D�݂̊�x�͕ω�����v�ɒ��ڂ��ꂽ���B�����ɂ��j���́u��v�̑I�D���́A�D�P�\���̍���̎����ɂ���ĕω�����A�Ƃ����咣�Ƙ_���ł���B���p����ƁF
�m�C�M���X�̔F�m�S���Ȋw�҂ł���f���B�b�h�E�n�y���b�g�ƁA��q�̃y���g��=�{�[�N��́A�����ɔD�P�\�����Ⴂ�����i�����O�̓�T�ԂƐ������j�ƍ��������̓�x�ɂ킽���āA�j���̊�̍D�݂������˂�([149])�B��������ƁA�����͔D�P�\�����Ⴂ�����͂�͂肩�Ȃ菗���������j������D�ނ��A�D�P�\�������������͂��j���I�Ȋ���D�ނ悤�ɂȂ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�m�c�n�����ł͈ӎ����Ă��Ȃ��Ƃ͂����A�����͖{���ɂ���ȁm�c�n�헪�������Ă���̂��낤���H�@������m���߂邽�߂ɁA�m�c�ʂ̎������s��ꂽ�c�n���ʂ͉������w��������̂������B�w�����I�ȊW�����Ώہx�ɑ���D�݂͔D�P�\�����Ⴂ�����������������ς��Ȃ������B����ɑ��A�w�Z���I�Ȑ��I�W�����Ώہx�ɑ���D�݂͐���������̎����ɂ���ĈقȂ��Ă����i�}4�E3�j([150])�B�D�P�\�����Ⴂ�����ɂ͏����I�Ȓj���炪�A�����ĔD�P�\�������������͂��j���I�Ȋ���D�܂ꂽ�̂ł���B
�@�m�c�n�ŋ߂̌����ł́A�m�c�n�����̓G�X�g���W�I�[���Z�x�|�����z�������ł���A�D�P�\���̍����Ƃ����l�������|�̏㏸�ɂƂ��Ȃ��Ēj���z�������Z�x�̍����j���̊���D�ނ悤�ɂȂ邱�Ƃ�����Ă���([151])�B([152])
�@���ڂ��ė~�����̂́A�u�����ł͈ӎ����Ă��Ȃ��Ƃ͂����A�����͖{���ɂ���ȁm�c�n�헪�������Ă���v�Ƃ������q�ƁA���̂������肵���_���ł���B�܂��ɁA�u���R�ӎu�E���R�ȑI���Ɋ�Â��Ȃ��q�g�̍s���v�͑��݂���̂ł���B
�@�@�ib�j�����ɂ��z������̑I�D�Ɛ�������
�@���ɒ��ڂ������̂́A��͂����̓�������A�����ɂ��z������̑I�D�Ɛ��������ɂ͐[���W������A�Ƃ��������Ƃ��̘_���ł���B�ia�j�ň��p���������ƂȂ镔��������Ɉ��p���悤�F
�����̎����ɂƂ��Ȃ��ď����̔z���헪���ω�����Ƃ������Ƃ́A�i���S���w�҂ɂ͂悭�m���Ă���b�ł���A�ƂĂ������̌����������Ȃ��Ă��Ă���B([153])�܂��A�����I�Ȓj���p�[�g�i�[�̂��鏗�����A�p�[�g�i�[�ȊO�̒j���ƃZ�b�N�X������p�x�͔D�P�\�������܂�ƂƂ��ɍ��܂����A�����I�ȃp�[�g�i�[�Ƃ̃Z�b�N�X�p�x�͐�������ʂ��ĕς��Ȃ����A�D�P�\�����Ⴂ�����ɂނ�����傷��X�������邱�Ƃ����ꂽ�B([154])�܂��A�����ɂ͂ɂ����̌����������Ȃ�ꂽ�B�̏L�ɂ́A���̐l�̃z�������̏�Ԃ��`�I�ȓ���([155])���������B�j���z����������ӂ���Ăł���j���̊��̂ɂ��������ɑ���D�݂́A�D�P�\�������������ō����Ȃ��Ă���B([156])�܂��A�D�P�\���������Ȃ�قǁA�����͐g�̂̍��E�̑Ώ̐��������j���̑̏L���D�ނ悤�ɂȂ�([157])�B([158])
�@�����ł����ڂ��Ă������������̂́A�������A<�����͍��A�D�P�\������������A���邢�͒Ⴂ����A���̂悤�Ȑ��헪���̂낤>�A���邢�́A<�����͍��A�D�P�\������������A�j���̊��̂ɂ���������A���E�Ώ̐��������j���̑̏L�����D�ނ悤�ɂȂ낤>�Ƃ����u���R�ӎu�E���R�ȑI���Ɋ�Â��v�s��������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����_�ɐs����B
�@�ȏ�́ia�j�ib�j�ɂ��A�i�������w�E�i���S���w�Ƃ������삩��A<�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��q�g�̍s���̎��Ⴊ����>�Ƃ����_�́A���łɈ����x�Ȃ���Ă���ƍl���Ă悢�A�ƕM�ҁE�a�c�͔��f���Ă���B
�@��T�߁@��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�ɂ���ē`������铮���E�q�g�̍s��
�@�{�߂ł́A��R�߁E��S�߂Ƃ̑Δ�ŁA��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�ɂ���ē`������铮���E�q�g�̍s�������R���݂��邱�Ƃ��m�F���Ă��������B
�@��P�́E��S�߂́u��_�|�w�����x�̐V���Ȓ�`�v�̖`���̒�(57)�ɂ��f���Ă��������A���Ƃ��A�J���h�j�A�E�J���X�́A�b��Ɏ���d�グ���}��p���āA�a���Ƃ�s�����Ƃ�B�i���Ȃ݂ɁA�b��Ɏ���d�グ������̎g�p�́A�q�g�ȊO�ł́A�J���h�j�A�E�J���X�ɂ����̂��������_�܂łł͔�������Ă��Ȃ��B�j����́A�J���h�j�A�E�J���X����`�q�ŋK�肳�ꂽ�s���ł͂Ȃ��A��V�I�Ɋw�s���ł���A�ނ�́u�����v�Ƃ���������Ɛ�������Ă���B([159])
�@�ȉ��ł́A�����ɂ����āA�܂��i�P�j�œ����́u����v�s���ɂ���������T�肽���B
�@�i�P�j�����́u����v�s���ɂ��������|�`���p���W�[�ق�
�@�`���p���W�[���A�̉�Q���g���āA�̎�������A������H�ׂ�s���A([160])����т��̍s�����q�ǂ��̃`���p���W�[���ώ@���A�^��������i�����܂Ŋώ@�Ɛ^���ł���A�q�g�̂悤�ɐ��̂��q�ǂ��ɉ�����ċ�����s���ł́u�Ȃ��v���Ƃɒ��ځj�s���́A���łɕ���Ă���B([161])
�@����ɁA�V���N�����u�`���h���i�p���FSouthern Pied-Babbler �A�w���FTurdoides bicolor �A�X�Y���ځA�q�^�L�ȁj([162])�Ƃ�����̒��́A�u�����ȊO�̌̂̒��ɖ�����������v([163])�Ƃ������Ƃł���B([164])
�@�i�Q�j�����ƃq�g�ɂ�����u����v�̈ٓ��|�u�i������w�v�̎���
�@����������ł��A�q�g�ȊO�̓����ƁA�q�g�ɂ�����u����v�ɂ͈ٓ�������B����͂Ђƌ��Ō����A�q�g�́u�O���W�v�𗝉��ł��邪�A�Ⴆ�`���p���W�[�͗����ł��Ȃ��B([165])([166])�u�W�v�Ƃ́A�u�w�킽���x�Ɓw���Ȃ��x�̊Ԃ̎Љ�I�W�v�ł���B([167])����ɑ��āA�u�O���W�v�Ƃ́A�u�w�킽���|���Ȃ��|���m�x�Ƃ����O�҂��݂��ɐ[���ւ�肠���Ȃ���A�Љ�I�ȑ�����i�߂Ă����v���Ƃł���B([168])
�@�����ɂ����āA�u����̐i���I��Ձv([169])([170])��T��Ɠ����ɁA�u�i������w�v�Ƃ����V���Ȍ�������𗧂��グ���A�������N�̍���̌����ɂ����ڂ������B([171])
�@�i�R�j��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�E����ɂ���Ă��`�������q�g�̍s���i��O��j
�@�����ō�1�_�A�m�F���Ă��������B����́A�{�٘_���A�����܂ł��Ȃ��A��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�A���̒��ł����ɉ����E�����o���̌���ɂ���Ă��`�������q�g�̍s�������邱�Ƃ́A��O��Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B�{�ٍe�Ŋ��x�����������Ƃ���A�u����v�𑀂�͓̂����̒��ł��q�g�݂̂ł���A�Ƃ����̂��M�ҁE�a�c�ƁA�قƂ�ǂ̐i�������w�ҁE�i���S���w�҂̗���ł���A����ɂ���ē`�������q�g�̍s�������I�ɂ��ʓI�ɂ��c��ł���̂́A����҂��Ȃ��B
��T�́@�u�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�|��_�i�P�j
�@��P�߁@�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�E�i���w�̐ړ_
�@���āA�q�g�̌�����i��q�g�̔]�̈�̒��N�̐i����ʂ��Ă̔��B�ƁA�����E�����o���̌���ɂ���ĕ��G�Ȑl�ԍs���̋K���E�K�����\�Ƃ����@�E�@�w�̐����́A���߈ȍ~�ɋ�̓I�ɂ݂�Ƃ���A���W�ł͂��肦�Ȃ��B
�@�O�́E��T�߁i�Q�j�Ō��y�����u�i������w�v�Ƃ̊֘A�ł́A�i������w���ǂ��炩�Ƃ����ƁA����̐i���ɂ�����u���ɗv���v���𖾂��悤�ƌ������ɏd�_������̂ɑ��āA�u�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�́A<��`�q����`�q�ɂ��`����鐶���I���J�j�Y���Ƃ��Ă̔]���]�ɂ��w�߂��Ď�N�����q�g�̍s��>�Ƃ����\�}�̒��ł́A<���u���ߗv���v�ɋ߂��]�̊������A�@�Ƃ����Ɋւ���Ă��邩>���𖾂��悤�A�Ƃ�����]�ɂȂ����Ă���A�Ƃ�����B
�@��Q�߁@Oliver
Goodenough�̌���
�@���́E��T�߂ł��Љ��Gruter
Institute for Law and Behavioral Research �̃����o�[�ł�����Vermont Law School �̋����ł���Oliver Goodenough�i�I�����@�[�E�O�b�h�C�i�t�j�́A���̕���ŁA���̖@�w�ҁE�]�Ȋw�҂Ƃ����͂��A�ߔN�߂��܂����w�ۓI�Ȑ��ʂ������Ă���B
�@�i�P�j�u�@�I���v���v�l���Ă��鎞�Ɏg���Ă���]�̕��ʂɂ��Ă̌���
�@Goodenough�����́A�܂��A2001�N�̘_���A"Mapping Cortical Areas Associated with Legal Reasoning and
Moral Intuition"([172])���Ȃ킿�u�@�I�_���v�l�Ɠ����I�����Ɋ֘A�����]�玿�̈�̃}�b�s���O�i�ʒu�E�̈摪��j�v�ňȉ��̂悤�Ɍ�������F
�ÓT�I�ŁA���炩�ɋ�������ɂ���(intractable)�A�@���؎�`�Ǝ��R�@�̐M��҂̊Ԃ̘_�c�́A�l�Ԃ̏��s���f�E�]������Q�̕��f���ꂽ���_�I���\�͂̍�p�f���Ă���\��������|����m�@���؎�`�n�́A����Ɋ�b��u���������[���̉��p�ł���A��������m���R�@�n�́A���`�́A���H���R�Ƃ͂��Ă��Ȃ��A����ɂ��\���͂���Ȃ�����(unarticulated
understandings)�̉��p�ł���B���̉����́A�����̂����Ƃ��炵���咣�ɂƂǂ܂�K�v�͂Ȃ��B�@�\�I�_�o�C���[�W���O�̏��Z�p�́A�{���������������I�ȕ��@�E��i����Ă����B�]��A���I�ɃX�L������������́A�l�Ԃ̍s����]�����邽�߂ɁA�m�P�n�m�@���؎�`�Ŗ@�ƌĂԂ悤�ȁn�@�I�ȏ����[�����m�]���n�p���Ă��鎞�ƁA�m�Q�n�����I�Ȓ������m�]���n�p���Ă��鎞�A���ꂼ��̏ꍇ�ɁA����������Ă���]�̗̈�(brain regions
employed)�ɁA�L�ӂȈႢ�����邩�ǂ����𖾂����Ă����͂��ł���B���̃v���Z�X�́A���R�@�ƁA�@���؎�`�m�ł����@�n�̖��炩�ȈႢ�̐_�o�w�I�Ȋ�Ղ𗝉�����菕���ƂȂ�ł��낤�B([173])
�@�����ł�����x�A�{�e�̖`���́i�P�j�i�Q�j�i�R�j�ŏq�ׂ��A�{�e�ł̎傽��咣�A���ł����ɁA�u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���Ƃ����_�A�����āA��P���E��P�́u�@�Ƃ͉����v�A��P�߁u���R�@�v�A��Q�߁u�@���؎�`�v�A����ɑ�R�߁u�@�̐V���Ȓ�`�v�A���߁i�P�j�i�Q�j�i�R�j�ŏ��q�����A�u�q�g�̖@�v�Ɓu�����̖@�v����т��̋��ʍ��ƍ���ɂ��āA�v���N�����ė~�����BGoodenough���咣����̂́A�u���R�@�v�ƁA�u�@���؎�`�ł����@�v�A�e�X��p���Đl�̔]�����f�������Ă���ꍇ�A�]�̊������̈悪�قȂ�A�Ƃ����̂ł���B�������ɖ{�e���咣�������_��2�_����B
�@��1�́AGoodenough���u���R�@�v�Ƃ��Ĉ��p���邤���A�{�e�́u�@�̐V���Ȓ�`�v�ɓ��Ă͂܂�ł��낤�u�@�v���A���ꂪ�p������ۂɊ����������]�̈悪����Ƃ������Ƃ����A���̗̈���A���R�A�q�g�̔]���i���̉ߒ��Œ~�ς��Ă����@�\�Ȃ̂ł����āA�{�e�`���Œf�����A�u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ��邱�Ƃ��A�]�Ȋw�̑��ʂ������������̂��A�Ƃ����_�ł���B
�@��2�́A�p���Ă���ۂɔ]�̊������̈悪�قȂ�قǁA�u���R�@�v�ƁA�u�@���؎�`�ł����@�v�̑��قȂ闼�҂ł͂���AGoodenough���u���R�@�v�Ƃ��Ĉ��p���邤���A�{�e�́u�@�̐V���Ȓ�`�v�ɓ��Ă͂܂�ł��낤�u�@�v���A�i�u�@���؎�`�ł����@�v�ƕ���Łj�u�@�w�v�̑ΏۂƂ���ɑ����A�Ƃ������Ƃł���B
�@���̑�2�̓_�̑Ó����́A��q�́AGoodenough�����ۂ�fMRI�ifunctional magnetic
resonance imaging; �@�\�I���C���摜�j��p���čs�����]�̊������̈�̎������@�Ƃ��̌��ʂŁA������x���炩���ꂽ�B���Ȃ킿�A���̌�AGoodenough�́A���̘_���ŗ\��([174])�����]�̈�̑���������ʂ��܂ތ������ʂ��A2004�N�ɋ����_��"Cortical
regions associated with the sense of justice and legal rules"([175])�i�u���`�̊��o�Ɩ@�I���[���ƂɊ֘A�����]�玿�̈�v�j�Ō��������B�݂̂Ȃ炸�AGoodenough�́AKristin Prehn���Ƃ̋����́u�����I�Ȕ��f�\�͂̌l���́A�Љ�I�E�K�͓I���f�̐_�o��̑��֊W�ɉe�����y�ڂ��v�i"Individual differences in moral judgment competence influence
neural correlates of socio-normative judgments"�j�Ƃ����^�C�g���̘_��([176])���A��͂�23�l�̔팱�҂�fMRI�f�[�^����g���A���\���Ă���B
�@�i�Q�j�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw��ʂɂ��Ă̌���
�@Goodenough�����́A�ȏ�̌����ɂƂǂ܂炸�A�ߎ��A��͂葼�̖@�w�ҁE�]�_�o�Ȋw�҂�o�ϊw�ҁi�u�_�o�o�ϊw�v�Ƃ����V���ȕ�����J�Ă���([177])�j�ƂƂ��ɁA2���̒P�s�������s���āA���ڂ𗁂тĂ���B
�@���̑� 1�́APhilosophical Transactions of the Royal
Society: Biological Sciences�i�����́A���ɗp�����Ƃ���A"Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci."�j����2004�NNovember 29���ł���B����́A"Theme
Issue 'Law and the brain' compiled by S. Zeki and O. R. Goodenough"�Ɩ��ł��āA���̍��S�̂��Ȃāu�@�Ɣ]�v�̓��W��g�̂ł���B([178])�i�O�q�́ANeuroeconomics�̘_�����f�ڂ��ꂽ�̂����̓��W���ƁA��q�̒P�s���ł���B�j���̓��W�����A�P�s���Ƃ��čĊ����ꂽ�̂��A2006�N����Semir Zeki
& Oliver Goodenough (eds.), Law and the Brain([179])�ł���B
�@Goodenough�����́A����2004�N�̓��W�����́A��͂�Kristin Prehn�Ƃ�2�l�̋����_���A�u�@�Ɛ��`�Ɋւ���K�͓I���f�ւ̔]�Ȋw�I�A�v���[�`�v�i"A
neuroscientific approach to normative judgment in law and justice"�j([180])�̒��ŁAfMRI�𑽗p�����������ʂ����p���A�����ނˈȉ��̎咣���s�����F�u�N�w�A�@���A�@�w�A�S���w�A�o�ϊw�Ƃ����������̊w��̈悩��̌����́A�{�\�Ɗ���A�ӂ߂�ׂ��_�̔��f�ɂ����ĉʂ��������ƗL�p���ɂ��ĈقȂ��Ă����B�ߎ��A�F�m�S���w�Ɛ_�o�����w�́A�K�͓I�Ȕ��f�̖��ɂ��āA�V���ȓ���Ăƕ��@�_����Ă���B���Ȃ킿�A�K�͓I�Ȕ��f�́A�]�̒��ŕ����̗̈���ɗp���Ă���v���Z�X���Ƃ����R���Z���T�X�����܂����B�m�c�����c�n�@�Ɛ��`�̌����͂܂��܂����B�r��ł���B��X�́A�@�́A���܂łɌ������ꂽ�{�\�I�E�����I���������A���L�͂ő��l�ȏ�Ɓm���n�����̃v���Z�X�̏���H��p���Ă���A�Ƃ����]�ɂ�����@�̃��f�������B�m�c�㗪�c�n�v([181])
�@����ɑ�2�ɁAGoodenough�́A2009�N�ɓ����āAMichael
Freeman�Ƌ��Ғ��̒P�s��Law, Mind and
Brain([182]) �����s�����B�O����������17�͂ɂ���сA24�l�Ƃ��������̋����҂ɂ��{���́A�Y���@�A�����@�Ɩ@�N�w�̐��Ƃ̋����ł���A�����ƐӔC�ɂ��Ă̂��ǂ������ɂ��Đ_�o�Ȋw���ł�����ݐ��ɒ��ڂ��Ă���B����ɁA�@�w�Ɩ@�����́A�@�E�S�E�]("law, mind
and brain")�̊w�ۓI�����ɂ�肳��ɏ[���������̂ƂȂ邾�낤���A�{���́A�u�_�o�@�w(neurolaw)�v�Ƃ����V���ȕ���ւ̏d�v�ȍv���ɂȂ邾�낤�A�Ƃ��Ă���B����܂ł̖@�E�@�w�Ɣ]�Ȋw�����Ƃ̊W�Œ��ڂ��ׂ��_���́ADean Mobbs, Hakwan C. Lau, Owen D. Jones and Christopher D. Frith,
"Law, responsibility and the brain"([183])�m�u�@�A�ӔC�Ɣ]�v�n�ł���AfMRI�Z�p�Ƃ̊֘A�ł́A���̋Z�p�ɂ��؋��̂Ɩ@��ł̐������ɂ��Ă̘_�l�ANeal Feigenson, "Brain imaging and courtroom evidence: on the
admissibility and persuasiveness of fMRI"([184])�m�u�]�摜�Ɩ@��ł̏؋��FfMRI�̏؋��\�͐��Ɛ������ɂ��āv�n���ڂ������B����ɁA�M�ҁE�a�c�̐��̈�̈�ł���Ƒ��@�ɂ��ẮAJune Carbone and Naomi Cahn, "Examining the biological bases of
family law: lessons to be learned from the evolutionary analysis of law"([185])�m�u�Ƒ��@�̐����w�I����Ղ̌����F�@�̐i���_�I���͂���w���ׂ����v�n�ɒ��ڂ��ׂ��ł��낤�B([186])
�@��R�߁@�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ɓu�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v
�@�ߔN�A�]�_�o�Ȋw�̔��W�ɂ��A�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ƃ����V�����������삪�����オ�����B�����ɁA���̕���ł́A�i�O�߂�Goodenough�����̌������ʂƈꕔ�I�[�o�[���b�v���j�A�_�o�ϗ��w(neuroethics)�Ɩ@�E�@�w�ɂ��Ă������ɘ_�����Ă���̂ŁA�ʼn߂ł��Ȃ��V����ł���B
�@�T�^�I�Ȍ������ʂƂ��ẮA�ٌ�m�ł�����Brent Garland �i�u�����g�E�K�[�����h�j���ҏW���A�����̊w�҂ƈꏏ�ɋ������Ƃ���2004�N�Ɍ�������Neuroscience
and the Law: Brain, Mind, and the Scales of Justice�i����Ɠ����ł�|���a���A�u�����g�E�K�[�����h (�ҏW)�A�ÒJ �a�m�E�v�� �T�q(��)�w�]�Ȋw�Ɨϗ��Ɩ@�\�_�o�ϗ��w����x�j([187])����������B
�@�{���ŁA�@�w�̗��ꂩ������Ƃ����ڂ��ׂ��́AMichael S. Gazzaniga & Megan S. Steven���ɂ��_���F"Free Will in the Twenty-first Century:
A Discussion of Neuroscience and the Law"([188])�i�a��_���^�C�g���u21���I�ɂ����鎩�R�ӎu�|�_�o�Ȋw�Ɩ@���Ɋւ����l�@�v�j�ł��낤�B�{�_���́A�^�C�g���ɂ�����Ƃ���A�]�_�o�Ȋw���V���Ȕ��W�������Ă���21���I�ɂ����āA�@�������E�ٔ��i���ɌY���@�̕���j�œ����҂̐ӔC���₦��̂��A�Ƃ����V���Ȗ���_���Ă���B��̓I�ɂ́A�܂��u���R�ӎu�ɂ��Ă̓N�w��̗���(The
Philosophical Stance on Free Will)�v([189])�Ƃ����Z�N�V�����ŁA��_(Indeterminism)�E����_(Determinism)��Δ䂳���Ę_���A�����u���R�ӎu���w�������ʓI�c�_(General
Arguments Supporting Free Will)�v([190])�ȍ~�ł́ADaniel Dennett�i�_�j�G���E�f�l�b�g�j��2003�N�̘_��([191])�������Ƃ��A�u����_�I�V�X�e���̒��̎��R�ӎu(Free Will in a
Deterministic System)�v([192])�̑��݂����m�肷�邱�Ƃɂ���āA���_�Ƃ��āA�u����̐_�o�Ȋw�I�m���Ȃ�тɖ@�T�O�̑O��ɗ����A�킽�������͎��̌����E�����̗�(axiom)��������F�]�͎����I�ȁA�K���ɂ���č쓮����A����_�I�ȑ��u�ł������A�l�Ԃ͎��R�Ɏ���̌�����������Ƃ��\�ł���s�҂ł���A���̌���ɑ��Čl�Ƃ��ĐӔC���B�m�c�n�l�X�����݂ɍ�p����(interact)�ƁA�ӔC����������B�]�͌��肳�ꂽ���̂ł���F�l�X(people)�͎��R�ł���B�v([193])�ƌ���ł���B
�@�܂��A�{���́A�_�o�Ȋw�̔��W�ɔ����A�V���ɏo��������Ƃ��āi�ȉ��͓ǎ҂̕X���l���āA�����̕����I�^�C�g�����ɂ����A�a�̕����I�^�C�g�������s���m�ł����Ă��A���̂܂܂����Ă����j�A�܂�Chapter 2�̒��̏����o��"Prediction
and Social Impact"�i��1�́u�]�@�\�v���Ɖ摜���v���̏����o���u�\���ƎЉ�I�e���v�j([194])�ŁA�]�Ȋw�ɂ��s���\���Ƃ��̎Љ�I�e����_���Ă���B����ɁA�����o��"Predicting Violence"�i���u�\�̗͂\���v�j([195])�Łu���ۂɖ\�͍s�ׂɑ������O�����Ȃ��ɂ�������炸�A�����̌��ʂɂ��ƂÂ����Â�����������A�ٗp�Ɋւ��锻�f���������肷�邱�Ƃɂ́A���Ȃ�̈�a�����o�����ɂ͂����Ȃ��B�v([196])�Ƃ������_���w�E���Ă���B�����͂̒��ŁA���o��"Looking Past Words: Neuroscientific Lie Detection"�i�u���t�̌����������ʂ��|�_�o�Ȋw�ɂ�鋕�U���o�v�j([197])�ł́A�u�_�o�Ȋw�Ɋ�Â������x�ȋ��U���o��@�v([198])���͂�ޖ��Ƃ��āA�u�؋��\�͂��ٔ����ɂ���čl�����ꂽ�̂́w�]�w��x(Braing
Fingerprinting)�Ƃ������W���Ŕ���o������EEG/P300�Z�p�݂̂ł���v([199])���̂́A���u�����x�Ȍ��������p�\�ɂȂ������ɂ����ƌ��O�����v�����([200])�Ȃǂ�_���Ă���B���̂悤�ɁA�ٔ��A���ł��Y�������̍ٔ��ɂ�����_�o�Ȋw�Z�@�̉��p�́A�����̖����͂��ł���A�ʼn߂ł��Ȃ��B
�@���āA����Garland���ҏW����������Chapter 7, "Neuroscience
Developments and Law"�i�a�ł͍Ō�̑�8�͂Łu�_�o�Ȋw�̏����Ɩ@�v�Ɩ�o����Ă���j�̘_��([201])�������Ă���Laurence R. Tancredi�́A2005�N�����̎��g�̒P���AHardwired
Behavior: What Neuroscience Reveals about Morality�i�a���A���[�����X R. �^���N���f�B���w�����]�Ƃ͉��� : �j���[���T�C�G���X�ƌY���ӔC�\�́x�ł��邪�A��q�̂悤�Ɏ�̖��_������j([202])�ŁA�_�o�Ȋw�Ɠ����̖������[���_���Ă���B�a�̕��肩����@������悤�ɁA�����݂̂Ȃ炸�A�������瓱�����Y���ӔC�\�͂��\���ɔO���ɒu���Ă���Ƃ���ɁA�@�w�̊ϓ_����͒��ڂ��ׂ��ł��낤�B�܂��A�����"Hardwired Behavior"�Ƃ����̂́A����́u�i�]�Ȃǂ��j�z������Ă���v�Ƃ����Ӗ������A�v����A�u�]�̍\������ŏ�����K�肳��Ă���s���v�Ƃ��������I�ȃ^�C�g���ł���A�܂��ɂ��������s��������̂��A����͓����Ƃǂ������W�ɂ���̂��A�����ɂ����ČY���ӔC�͂ǂ�قǖ₦��̂��A�����čŏI��12 �͂́A"Creating
a Moral Brain"�i�a��́u�����]����Ă�v�j([203])�ł́A�����ɂǂ̂悤�ȉ\�����J���Ă��邩��_���Ă���B
�@����ɁA���̕���ł̒��ڂ��ׂ��������Ƃ��āA2004�N�����́ANeuroethics:
Mapping the Field, Conference Proceedings([204])�i�w�_�o�ϗ��w�F���̕���̈ʒu�E�̈摪��A�w��\�_���W�x�j�A2007�N�����́ADefining
Right and Wrong in Brain Science: Essential Readings in Neuroethics([205])����������B���Ɍ�҂́A�S405�ŁA�����҂͑O�q��Neuroscience
and the Law: Brain, Mind, and the Scales of Justice�Ƃ��d������40�l�O��́i�����Ȓ��҂��܂ށj���Ƃ��W�܂����ǂ݉����̂���ꏑ�ł���B
�@����ɂ��̐_�o�ϗ��w(neuroethics)�̕���̔��W���ے����邩�̂悤�ɁANeil Levy([206])�͒P���ŁANeuroethics: Challenges for the 21st Century([207])�i�w�_�o�ϗ��w�F21���I�ւ̒���x�j�\�����B�e�͖����ɕt���ꂽ��(Endnotes)�͎�ȗ��Ȃ��̂ł͂���A���ꗬ�̘_���Ƃ͌����܂����A�ڍׂ�"References"�i�Q�l�����j��pp. 317-336��20�łɂ킽���Ă�����ȂǁA���̕���̍Ő�[�ƁA���ꂪ�͂�ޏ������킩��₷��������悤�Ƃ���A�ǐS�I�Ȓ���ł���B
�@�����āA���̐_�o�ϗ��w�̕���̏d�v�����A����w�A�i���ݓI�Ȗ@�w�̌��n������j�������邩�Ɍ�����̂��A�@�N�w�̕���̕Ғ�([208])������Walter Sinnott-Armstrong�̕ҏW�ɂ��A�������500�őO��ɂ킽��咘3���V���[�Y��Moral Psychology ([209])([210])�m�w�����S���w�x�n�̂����̍ŏI��3���AMoral Psychology,
Volume 3: The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and
Development ([211])�m�w�����S���w
��3���F�����̐_�o�Ȋw�F����A�]��Q�Ɣ��B�x�n�ł���B�{���́A8�̎�ȏ͂ƁA����ɑ���ᔻ��R�����g�A����ɂ͂���ɑ����ȏ͂̒��҂ɂ��ēx�̃R�����g��Ĕ��_����Ȃ�A�Ƃ������ꂾ���ł������[���\���ƂȂ��Ă���B
�@���̒��ł��@�w�̊ϓ_���璍�����ׂ��́A���ɑ�3�͂̎�_���ł���B�����Kent A.
Kiehl�ɂ����̂ŁA"Without
Morals: The Cognitive Neuroscience of Criminal Psychopaths"([212])�i�u���������ɁF�Y�������̔Ɛl�ł��鐸�_�a���҂̔F�m�_�o�Ȋw�v�j�Ƒ肵�āAfMRI��pscyhopathogy�i���_�a���w�j�ɂ����鉞�p([213])�ɂ��G�ꂽ��ŁA�����ǂ���Y�������̔Ɛl�ł��鐸�_�a���҂̔F�m�_�o�Ȋw�I���͂ɂ��āA�ڍׂɘ_���Ă���B
�@�ȏ�̊w�E�̍ŐV������W�]���Ă݂�A�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ɓu�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�̕���̘A�q�́A���łɊm���������A������ڂ̗����Ȃ��������ʂ����҂����A�Ƃ������Ƃ��������蒸�����̂ł͂Ȃ����ƕM�ҁE�a�c�͍l���鎟��ł���B
��U�́@�u�@�Ɛi���ϗ��w�v�|��_�i�Q�j
�@��P�߁@�u�i�������w�v�E�u�i���S���w�v�E�u�i���ϗ��w�v�O�҂̑��݊W
�@�܂��ŏ��ɁA�u�i���ϗ��w�v���`���Ă������Ƃ��K�v�ł��낤�B���̌�������Ē��q���ꂽ�A2009�N�̓����~���w�i���ϗ��w����|�u���ȓI�v�Ȃ̂����ǁA�������x([214])�ɂ��A�u�l�ԍs���i���w�m�c�n�ł͐����i���̊ϓ_����A���̉ߒ��Ől�Ԃ������Ȃ�S�̂͂��炫��s���p�^�[���B�����Ă������A�����Ƃ��Đl�Ԃ����ʂɎ���{�I�����͂ǂ��������̂�����������Ă���B�l�Ԃ̓������͂��̒��ł��d�v�Ȍ����e�[�}�ł���A��������������́w�i���ϗ��w�x�ƌĂ�āv����A�Ƃ܂���`���A�u����1980�N��ȍ~�A�����ȋc�_���W�J����Ă���B�v�Ƃ���B���̏�ŁA�u�m�c�n�����Ɂw���v�x�Ƃ����q�ϓI�ȍ��������o���Ƃ������ƂŁA����܂ł̗ϗ��w�ł͂Ȃ��Ȃ�������������Ȃ����������������ɁA�V�����p�x������āA�Ǝ��̌��������Ƃ��낪�A�V�����w�╪��Ƃ��Ă̐i���ϗ��w�̑傫�ȓ����ł���v([215])�Ƃ��Ă���B
�@����ł͂��̒�`��O��ɁA�{�e����Ƃ��Ď��グ��i�������w�E�i���S���w�ƁA�i���ϗ��w�̑��݊W�͂ǂ̂悤�ɂȂ�̂ł��낤���B�����ŗ��ӂ��ׂ��́A�܂��A�w��̒�`�ォ��ł͂Ȃ����A�w��j��A�O��҂Ɛi���ϗ��w�́A����I�ȍ�����͂��ł��邱�Ƃł���B���Ȃ킿�A���܂ł͎�Ƃ���descriptive science�i�h�C�c��Ō���"sein" ���Ȃ킿�u�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩�v�̕`�ʂ����݂�j�ł������A�i�������w�E�i���S���w�ƁAnorm�ɏd�_��u����normative
science�i�h�C�c��Ō���"sollen"
���Ȃ킿�u�ǂ̂悤�ɂ���ׂ����v�̋K�͂̊m�������݂�Љ�Ȋw����ł���A�Ⴆ��20���I�㔼�ɓ��ɐi�W���݂��Љ�w�A�t�F�~�j�Y���_�A�W�F���_�[�_�Ȃǂ����܂ށj�ł���A2�̈قȂ�science�̉z�������i�����ɂ���j��}���A����2�����悤�Ƃ����S�I�ȕ��삪�A�i���ϗ��w�ł���B��������A�u�i�������w�v�������̌`�ԁE�s�����u�ǂ̂悤�Ɂv�i�����������������A�u�i���S���w�v�������i���̒��ł����Ƀq�g�ɏœ_���i���Ă��邱�Ƃ͎��m�̎����ł��邪�j�̐S������͂�u�ǂ̂悤�Ɂv�i�����������������悤�Ƃ���̂ɑ��āA�u�i���ϗ��w�v�́A��`��͂܂��͒P���ɁA�����i�����ł͓����Ɍ��肳���j�̗ϗ����u�ǂ̂悤�v�ɐi�����������������悤�Ƃ�����̂ł���Ȃ���A�܂��Ɂu��`��(by definition)�v�����ł́A�����i��͂�q�g�Ɏ�ɏœ_���i���Ă���̂͊m���ł���j�̗ϗ��A���Ȃ킿�u�ǂ��w����ׂ����x�v�������ɐi�����Ă������������ΏۂƂ��Ă���A�Ƃ����_�Ō���I�ɈقȂ��Ă���̂ł���B
�@�@�Љ�w�҂̑��c�����́A���̂��Ƃ��A2005�N�̒i�K�ł��łɁA���̔N�Ɋ��s�����ٕҒ��w�@�ƈ�`�w�x�̒��ŁA�u�m�c�n�ϗ���i���_�̕����Ō�邱�Ƃ͋C�̏d�����Ƃł���B�m�c�n�u�u�u�u�u�ϗ���i���_�̕����Ō�邱�Ɓv�̗ϗ����v��i���_�̕����Ō�邱�Ɓv�̗ϗ�����i���_�̕����Ō�邱�Ɓv�c�c�m�}�}�n�v�Ƃ������^�i�s�̓D���ɑ���������ꂻ��������ł���B����͐i���v���Z�X�̃A�E�g�v�b�g�����̍���̉��Ɏ��Ȃ̑n�������v���Z�X�����悤�Ȃ��̂����炩������Ȃ��B�v([216])�ƕ\�����āA�u�i���ϗ��w�v�Ƃ��������̉c���̂��������͂�݂��˂Ȃ��A�ƌx����炵�Ă���B�������A�����ٕҒ��̒��́u���_�v�ŕM�ҁE�a�c���_�����Ƃ���A���c�̌x���ɂ�����炸�A�u���c����8�͂���߂��������悤�ɁA�u�u�u�u�u�ϗ���i���_�̕����Ō�邱�Ɓv�̗ϗ����v�m�c�n�v�m�c�n�v�m�c�n�v�m�c�n�v�Ƃ������Ɠ����͔����˂Ȃ�Ȃ��B�������A�q�g�Ƃ����������i������i��������A�����c��j�ߒ��ŁA���q�E���q�E���̈�`�i�q�j���̔����Ƃ��đ̓��ɔ����Ă��������I���J�j�Y���́A�����̂Ƃ��Ẵq�g�����̍s���E�S���ɕ\�o����u�ϗ��v�Ə̂������̂����i���̊����̓����Ɠ��l�Ɂj����Ղ��Ȃ��Ă����͂��ł���B�m�c�n�@�Ɨϗ��̘A���͘_�����ċv�����B�i���Ɨϗ��͂��łɘ_�����Ă����B([217])�@�|�ϗ��|�i���|�@�|�ϗ��|�i���c�̎O�p�W���A��藧�̓I�ɑ����鎎�݂͖��d�ł͂Ȃ��낤�B�v([218])�ƍl������̂ł����āA�i���ϗ��w�Ƃ����V���Ȍ�������ɂ́A�Ǝ��ɉʂ����ׂ��g��������A�Ƃ����̂��M�ҁE�a�c�̗���ł���B
�@�Ȃ��A���߂́u�w���ƌ��v�ɓ���O�ɁA���E�̐i���ϗ��w�E���ȒP�ɓW�]���Ă��������B�p��̒���ŁA�u�i���ϗ��w�ievolutionary ethics�j�v�̌�����������̂�Ꭶ�I�ɂ����邾���ł��A�w�E�ł͂��łɂ��̕��삪�m��������邱�Ƃ�������B([219])�o�ŔN���ɁA�p��̒���𒍋L���ċ����Ă����B�Ȃ��A�w��j��`�o����A�Ƃ����ړI����A���ׂď��ł̏��Ђ��i���̏o�ŔN����Ɂj�f���Ă���B([220])
�@��Q�߁@�w���ƌ���
�@�i�P�j����P�|����y���w�i���_�Ɨϗ��x�i���E�v�z�ЁA1996�N�j([221])
�@���䋳���̖{���ł́A�u�i���ϗ��w�v�Ƃ������͎g���Ă��Ȃ��B�������A"Evolutionary ethics"�ɂ��āu�i���_�I�ϗ��w�v�Ƃ����������ĂĂ��邾���ŁA��{�I�ɖ{�e�̗p��́u�i���ϗ��w�v�ɂ��ďڍׂɘ_�����A���{��̐��I�Ɛтł���B
�@�{�e�̌���ꂽ���ʂ̒��ŁA���䋳�����{���œW�J���ꂽ�w���ƁA���̌���S�ʓI�ɍs���p�ӂ͂Ȃ��B�����A�{�����i�{�e�̗p��́j�i���ϗ��w�ɂ��Ċw��j��������N�����Ď��ɒ��J�ɘ_���A��220�Ɍf�����p��̕������A�{��������1996�N���O��1993�N��Matthew H. Nitecki and Doris V. Niteck(eds.), Evolutionary
ethics�m�w�i���ϗ��w�x�n �Ɏ��^���ꂽ���ł́A�Ⴆ��M. Ruse�̘_��"The New
Evolutionary Ethics"�i�u�V���Ȑi���ϗ��w�v�G��q�j�Ɍ��y����ȂǁA���J�ɖڔz�肪����Ă���B�i����220�́A1994�N���s��Paul Lawrence Farber�̒����A�����1995�N���s��Paul Thompson�̕ҏ��ɂ͌��y���Ȃ��B�j
�@���䋳���́A�{���́u��1���@�_�[�E�B���̓����N���_�v��1871�N���ł̃_�[�E�B���̒���w�l�Ԃ̗R���x([222])�܂ł����̂ڂ��Ę_���N�����A([223])�����̘a�̖������J�ɘ_���Ă���A([224])���̏�ŁA�_�[�E�B���ƃW�����E�X�`���A�[�g�E�~��(John Stuart
Mill)��Δ䂳���A([225])�A���t���b�h�E���b�Z���E�E�H���X(Alfred Russel
Wallace)�ɂ��_�[�E�B���ᔻ�ɂ����y����B([226])���̏�ŁA�u��2���@�\�㐢�I�̐i���_�I�ϗ��w�v([227])�ŁA���̎���̐i���ϗ��w�̐��I�_�w����Ղ��Č�A�u��3���@�Љ���w�Ɨϗ��v�ŁA�Љ���w�̊J�c�Ƃ�������E.O. Wilson�́A�u�E�B���\�����g�́A�Љ���w�̒m���ɂ��ƂÂ��ā@�ϗ��I���f���邢�͋K�͓I�Ȓɂ܂ŗ��������Ă���A�i���_�I�ϗ��m�{�e�̗p��ł͐i���ϗ��w�n�̎x���҂ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���v�Ƃ��A�T���Ƃ���1975�N���s�̒�����Wilson, Sociobiology
([228])�i�a���w�Љ���w�x�j�ɉ����āA1878�N���s��Wilson, On
Human Nature([229])�i�a���w�l�Ԃ̖{���ɂ��āx�j��������B�����ɁA�����Ōf��������~���m�Ƃ��ΏƓI�ɁARichard D. Alexander �i���䋳���́u�A���O�U���_�[�v�ƕ\�L�j�ɂ��ẮA�u�Љ���w�̂�����l�̗L�͂Ș_�҂ł���R.D. �A���O�U���_�[�́A�i���_���l�Ԃ̍s���ɂ��đ����������Ă���邱�Ƃ����������A���ꂩ��w�l�͉����Ȃ��ׂ����x�K�͗ϗ��Ɋւ��鎦���m�ȏ�}�}�n��ǂ݂Ƃ邱�Ƃ������ς�Ƌ��ۂ��Ă���A�i���_�I�ϗ��m�i���ϗ��w�n�͎x�����Ȃ��v�ƒf���A�T���Ƃ���1979�N����Alexander�̗L���Ȉꏑ�ADarwinism and Human Affairs([230])�������Ă���B
�@�����āA���䋳���́A�{���̌㔼�������āA�}�C�P���E���[�X(Michael Ruse)�́u�i���_�I�ϗ��w�m�i���ϗ��w�n����Ƃ��Ď��グ��v���Ƃ��A���̗��R�ƂƂ��ɏq�ׂĂ���B([231])�����ă��[�X�̋c�_�̏ڍׂɗ�������O�ɁA�u�܂��A�Љ���w������ǂ���Ƃ����\���I�̐i�������w�̊�{�I�Ȓm�����ȗ��Ɍ��n���Ă����v([232])�Ƃ��āA���̉c�ׂɑ�3�͂�3.2����3.5([233])�������Ă���B���ł��A���C�i�[�h�E�X�~�X(John Maynard
Smith)���u��{���f���Ƃ���w�^�J�E�n�g�Q�[���x�v�̃Q�[���̗��_�̏ڍׂɂ����������ďЉ�Ă���͍̂��ؒ��J�ł���B([234])�����āA�{�_�ł���u���[�X�̐i���_�I�ϗ��w�m�i���ϗ��w�n�v�̏ڍׂ��ARuth��1986�N���̒����ATaking Darwin Seriously([235])���傽��ΏۂƂ��Ę_���A([236])���_�Ƃ��āu�킽���̓��[�X�̐i���_�I�ϗ��w�m�i���ϗ��w�n�̂����A�o���I�Ȓm���ƃ��^�ϗ��w�I���@�̈ꕔ�͏\���ɕ]�����邪�A�������f�̐������Ɋւ��錩���ɂ��Ă͂͂�����Ɣ��ł���B�v([237])�ƌ���ł���B
�@�ȏォ�疾���Ȃ悤�ɁA���䋳����1996�N�̖{���́A�i���ϗ��w�̍őO���ɔ��낤�Ǝ��݂��A���{�̊w�E�ł̐��I�Ɛтł���B
�@�i�Q�j����Q�|�����~�w�i���ϗ��w����|�u���ȓI�v�Ȃ̂����ǁA�������x�i�����ЁA2009�N�j
�@�i�P�j�Ō��y�����A����y�������̏��_�l�����܂��Ď��M���ꂽ([238])�̂��A2009�N���̓����~���w�i���ϗ��w����|�u���ȓI�v�Ȃ̂����ǁA�������x�ł���B�M�ҁE�a�c�́A2010�N1���Ɍ��������u�����m�[�g�v�Ƃ�������������v���_���ŁA�{�����A�u�����I�ȕ��肪�t���ꂽ�{���́A�_���Ƃ����̍ق͂Ƃ��Ă��Ȃ��B�ɂ�������炸�A�{���́m�c�n��ǂɒl����B�v([239])�ƕ]���A���̍����Ƃ��āA��P�ߖ`���Ř_�����悤�ɁAdescriptive science�ł������A�i�������w�E�i���S���w�ƁAnorm�ɏd�_��u����social
science�́A2�̈قȂ�science�̉z��������}���A����2�����悤�Ƃ����S�I�Ȓ��삪�{��������ł���A�Əq�ׂ��B([240])
�@�����Ƃ��A�������m�̖{���́A���҂��ŏ�����f���Ă���悤�ɁA���发�Ƃ��Ď��M���ꂽ���̂ł���A���������T���𒍋L���邱�Ƃ����Ă��炸�A�_���̑̍ق͎���Ă��Ȃ��B�������m�̊w��I�咣�̒��j�́A�����������ɂ��A2004�N�̔ނ̖@�w���m�������_��([241])�ɉ��M�C�����ꂽ2007�N���s�́w���R��`�̐l���_�\�l�Ԃ̖{���Ɋ�Â��K�́x([242])���Ђ��Ƃ��˂Ȃ�Ȃ��B�ɂ�������炸�A�{�e�������Ŕނ́w�i���ϗ��w����x���Ƃ肠����̂́A�{�������发�ł���Ȃ���A�܂��ɑO�q�̂��Ƃ���S�I�Ȓ��삾����ł���A����̐�s�����ɂ�������炸�A�u�i���ϗ��w�v�Ƃ����L�[���[�h�������������́A���݂܂ł̏��A�a���ł͓������m�̖{��������������Ȃ��A�Ƃ������̐挩���ɂ�����B
�@�������m�͖{���̖`���ŁA�u�i���w�ł́A�m�c�n�������������Ɂw�����̈�`�q���c���x���Ƃ��w�i��j�K���x�̌���x�Ƃ������A�{���ł́A�w�K���x�x�Ȃǂ̐��p�������āw���v�x�m�Ƃ����p��n���g���v([243])�Ɠ��发�Ƃ��Ă̗p��@�𐮂�����ŁA�u��1�́@�l�͗��v�œ����悤�ɂł��Ă���v�u��2�́@�w���ȓI�x�Ȉ��v�u��4�́@�w�P�x�͓��A�w���x�͑��v�u��5�́@�w���x�̗��v�ɂȂ�w�������Љ�x�v�u�I�́@�w�����̂��߁x�̓����v�Ƃ��������o���ŁA�i���ϗ��w�ւ̓���������Ă���B
�@�{���ɂ́A���发�Ȃ�ł͂̎�_�����邱�Ƃ͍Ō�Ɏw�E���Ă��������Ǝv���B�Ꭶ����A�i�������w�҂̃��`���[�h�E�A���O�U���_�[�ɂ��u�Ԑڌb�̗��_�v��p���ē������m���ǎ҂�������悤�Ƃ���A�����ځu�]���̗��v�v�̕����ł���B([244])�����œ������m�́u�b�W�̎d�g�݁v��}�����āA([245])�u���v���u�`����v�ɗ����s�����s���āA�u�`����v���璼�ځu���v�����v���邱�Ƃ������Ƃ��A�u�a�C�b�C�c�C�d����v�Ȃǂ��͂��߂Ƃ���l�X�̊ԂŁu�w���x�͂����l���I�Ƃ����w�]���x�v���m������邱�ƂŁA���ʓI�ɂ́u�`����v�͗��v���邱�ƂɂȂ�A�ƌ��_�Â���B�������A�����܂Ŕ�ː�w�ŃA���O�U���_�[�̌������Ђ��Ƃ��Ă��Ȃ��M�ҁE�a�c�̈�ۂɂ����Ȃ����A�u�Ԑځv�b�Ƃ����p�ꂪ�����Ƃ���A�K�����������������ʂ����Ƃ͕ۏ���Ă��Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��������m�̖{���̓��e�͈̔͂ł͂����������ʂ͘_����Ă��Ȃ��Ǝv����B
�@�i�R�j����R�|�ɐ��c�N���w��������̗ϗ��w����x�i���É���w�o�ʼn�A2008�N�j([246])
�@�ɐ��c�N���E���s��w�y�����̖{���̎�ȃe�[�}�̈�́A�����̎�����̗ϗ��ł���B�������A����Ɠ������s�I�ɁA��4�͂̈�߂������āA�u4-2 �����̋N���Ɛi���_�v([247])�A����ɂ́u4-3�@�Ăѓ����̗��R�ɂ��čl����v([248])�Ƃ����e�[�}�ɂ��ď������ڂ����_���Ă���A���y���鉿�l�̂��鏑���ł���B�����Ƃ��{���́A�u�i���ϗ��w�v�Ƃ����p��͎g�p���Ă��炸�A�����܂œ����������ɐi�����Ă������A��_����ɂƂǂ܂��Ă���_�͗��ۂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@4-2�߂ł̈ɐ��c�y�����̏��_�̒��ڂ��ׂ��ӏ��́A�u4-2-3�@�����w�I�����s���v([249])�Ői�������w�̂��̗��_����������Љ����ŁA���́u4-2-4�@�Q�[�����_�Ɛi�������w�v([250])�ŁA���̕���̍ŐV�������ʂ��ȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă���B�ȏ����ՂƂ�����ŁA�ɐ��c�y�����͈��������A�u4-2-5�@���l�m�}�}�n���v����铮���v([251])�ŁA�����ɂ����铹���Ɍ��y����݂̂Ȃ炸�A4-3�߂ŁA�u4-3-1�@�����̐i�������w����l�Ԃ̐i�������w�ցv��_����̂ł���B�����ł́AE.O. �E�B���\���̎Љ���w�_���ɊȒP�ɊT��([252])������ŁA�i���S���w�̔��W�ɐG��A�u�����ɂ������S���̌������i���S���w�̏d�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B�v�Ǝw�E����B([253])�����Ė{�߂̍Ō��3�̃Z�N�V�����������āA�ɐ��c�y�����́u4-3-2�@�����̋N�����瓹���̗��R�ցv�u4-3-3�@�Q�[�����_���瓹���̗��R�ɂ��ĉ��������邩�v�u4-3-4�@���Ǔ����̌l�I���R�͂ǂ��Ȃ�̂��v([254])�ɂ����āA�u�i���ϗ��w�v�Ƃ����p�ꂱ���p���Ă��Ȃ����A�����i�ɐ��c�y�����͂����Łu�ϗ��v�Ƃ����p����p���Ă���([255])�j�������ɐi���������A�ɂ��Ę_���Ă���B
�@�u�i���ϗ��w�v�Ƃ����������t���Ă��Ȃ����̂́A�ȏ�̗��R����A�{���͒��ڂ��ׂ��ꏑ�ł���B
��V�́@�����|�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_
�@�ȏ�A��P���ł́A�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_���A�w�E�̐V�����܂��ď��q���Ă����B�����ł��̐��ʂ��������Ă��������B
�@�{�e�S�̖̂ړI�́A���̖͂`���A���́E��P�߁A����ё�P���E��P�́E��R�߂Ř_���Ă����Ƃ���F
�i�P�j�@�́u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���B
�i�Q�j�u�@���v�̋��������Ă���������葽�����A�q�g�̐i���I��Ղɋ��߂邱�Ƃ��\�ł���B
�i�R�j�q�g�̖@�́A�u�����Ƃ��Ă̓����̈��Ƃ��Ẵq�g�́A�i���Ɋ�Ղ����A�L�͈͂ŁA���������E�s��������Ȃ��A���[���E�s�K�͂ł���A�ᔽ�����ꍇ�ɉ��炩�̐��ق����́v�ƒ�`���邱�Ƃ��\�ł���B
���́i�P�j�i�Q�j��_���邱�Ƃɂ��A���̐V���Ȗ@���_���ێ����A���i�R�j�̒�`�̑Ó����𗧏��邱�Ƃł���B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A��P���E��P�́E��R�߂́i�P�j�A�u�}�P�v�̏W���`���u�m��������_�����Ă����n�@�E�@���v�ƁA�W���a���u�u�@�v�̐V���Ȓ�`�v�̐}�ɂ����āA�W���`���u�m��������_�����Ă����n�@�E�@���v�́A�]���l�����Ă������ꡂ��ɑ����̕������A�u�i���Ɋ�Ղ����v�̂ł����āA�W���a���u�u�@�v�̐V���Ȓ�`�v�Əd�Ȃ邱�ƁA���Ȃ킿�A�W���`�ƏW���a�Ƃ́u�����v�������ɋ߂�����_���邽�߂̏�����Ƃ��A���̑�P���ł������B
�@���̂��߂ɁA�܂���P�͂̑�P�E�Q�߂ł́u�@�v�̉ߋ��̒�`���ӂ�Ԃ�A��R�߂ŏ�L�́i�R�j�́u�@�v�̐V���Ȓ�`������B�Ɠ����ɁA������R�߂ł́A�쒷�ތ����̖L���Ȓ~�ςɈˋ����A�܂������ł��쒷�ނɓ����������邱�Ƃ��_���ꂽ���Ƃ܂��āA�쒷�ށi�̈ꕔ�j�ɂ́A�u�����̖@�v�ƌĂт�����̂����݂��邱�Ƃ��_�������A�ƕM�ҁE�a�c���l���邱�Ƃ�������ƂƂ��Ď������B����ɂ́A�u�����̖@�v�ƌĂт�����̂����݂��邩�ۂ��A���E����Ƃ��āA������L�x�Ȍ����̒~�ς�����~�c�o�`�����̕��������A�����w�̐��Ƃɂ��A�~�c�o�`�E�A�����܂ގЉ�����ɂ��ẮA�u�����I�ȓ��@�ł���w�ǐS�x�w�������x�ށv���Ƃ���w�E����Ă��邱�Ƃ������A����̌�����҂��āA�Љ�����ɂ��u�������v�ƌĂԂɑ�����̂�����Ƃ���A�ނ�ɂ��u�@�v�����݂��邱�Ƃ�\��������A�Ƃ����M�ҁE�a�c�̍l�����������B
�@�Ȃ��A��P�́E��S�߂ł́A�u�����ɂ��@������v���Ƃ̖T�ƂȂ��_�Ƃ��āA�V���ɒ�`���ꂽ�u�����v�ɂ��āA�u�����ɂ�����������v���Ƃ����łɘ_����Ă��邱�Ƃ��������B�����ł́A���L���A�쒷�ށi�̈ꕔ�j�Ɍ��肳�ꂸ�ɁA�N�W���A�C���J�A���ނɂ����������݂��邱�Ƃ��A�e����̐��Ƃɂ���������邱�Ƃ���Ă������B
�@�����ŕt�����Ă������A�u�i�ꕔ�́A�Љ�̍����j�����ɂ��@������v���Ƃ��_�ł���A���̂��Ǝ��̂ɂ��Ӗ������邪�A�����āA�L�j����ȑO�́A�܂����ꂪ�\���ɂ͔��B���Ă��Ȃ������q�g�ɂ��@�����������Ƃ��������������A�{�e�`���̎咣�̂悤�ɁA�u�@���v���u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ���A�u�@���v�̋��������Ă���������葽�����A�q�g�̐i���I��Ղɋ��߂邱�Ƃ��\�ƂȂ邽�߂ɂ����A�d�v�ƂȂ�̂ł���B
�@���ɁA��Q�́u�@�Ɛi�������w�v���_�ł́A��ɑ�Q�߂ɂ����āA���̉\���������Ă������B�[�I�Ɍ����A�{�͖`���Ɍf�����A��P���̖ړI�̈�ł���i�P�j�̐V���Ȗ@���_�́A�i�������w�̉��p�ɂ���ĉ\�ł��邱�ƁA�����̎�����̗�̉��ɉ\�ł��邱�Ƃ���\�����Ă������B����ɂ́A�i�������w�̉��p�ɂ��V���Ȏ���@�̉��ߘ_�̉\���ɂ����y�����B
�@���������A��R�́u�@�Ɛi���S���w�v���_�ł́A��ɑ�P�߂ŁA�ߔN���W�߂��܂����i���S���w�̕���ł�1��Ƃ��āA������u4���J�[�h���v�ɂ����Ď����ꂽ�A�i���̉ߒ��ɂ�����<�q�g�͎Љ�_������Ȃ��u����ҁv���s�q�Ɍ��m����K���@�\���S�����J�j�Y���������>�Ƃ������Ƃ��A�q�g�ɂ�����@�̐����ɂ����āA�d�v�ȕK�v�����ł��������Ƃ��������A�Ƃ������Ƃ��w�E�����B
�@���āA��S�́u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi���S���w�v�E�u�@�ƍs����`�w�v�ł́A�@�ƁA��͂�V���Ȏ��R�Ȋw�̕���ł���s����`�w�Ƃ̐ړ_�ɂ��Ę_�����B�v��A�{�͖`���́i�P�j�̖@���_�̘_�ƁA�i�R�j�̖@�̐V���Ȓ�`�̑Ó����́A�܂��͈���ŁA�u�@�Ɛi�������w�v�E�u�@�Ɛi�������w�v�̊w�ۓI��@��p���A�q�g�̍s���́u���ɗv���v�i��R�́E��P��(3)�Q�Ɓj�Ɗ֘A�����Ę_���邱�ƂɂȂ�B���̈���ŁA�s����`�w�́A�q�g��700���N�̐i���̉ߒ��ŏW�ς��Ă�����`�q�Q���A�i���Ƒ��ݍ�p�������A�n���I�Ɂj�ǂ̂悤�Ȑl�ԍs���ݏo���̂��A���́u���ߗv���v�i��͂��R�́E��P��(3)�Q�Ɓj���𖾂��悤�Ƃ�����B��������A�s����`�w�́A�u���ɗv���v��������ł���q�g�́i�@�̒�`�̈ꕔ�ł���j�s���K�͂́u���ߗv���v���𖾂���\�����߂Ă��邱�ƁA���[�I�Ɍ����A�u�@�v���x����1�̊�Ղ͈�`�q�ɂ����肤�邱�Ƃ�����B
�@���̏�ŁA���S�́E��R�߂ɂ����āA�s����`�w�ɂ����ẮA���E�̍Ő�[���s��Plomin��ƂƂ��ɁA���{�ɂ����Ă��A�������N�炪�A�o���������̎�@�ɂ��A�����Ɍ������ʂ�ςݏd�˂Ă��邱�Ƃ���A����̐��ʂ����҂ł��邱�Ƃ��������B�܂��A��S�߂ł́A����ōs����`�w���A�u�@�v�̈ꕔ�ł���s���K�͂��x����1�̊�Ղ͈�`�q�ɂ����肤�邱�ƁA���������<��`�q�i�Ɗ��j�ɂ��A�i�n���I�Ɂj���E�����A�q�g���܂ޓ����̍s��>��O���ɒu���A�قȂ��������A�u���R�ӎu�v�u���R�ȑI���v�Ɋ�Â��Ȃ��q�g�̍s�������݂��邱�Ƃ�_���Ă������B
�@����ɁA�Ċm�F�Ƃ��āA���S�́E��T�߂ł́A��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�ɂ���ē`������铮���E�q�g�̍s�������邱�Ƃ��A�����́u����v�s���ɂ��������i�`���p���W�[�A�V���N�����u�`���h���j�����p���A������Ă��邱�Ƃ��������B�����ɁA�����ƃq�g�ɂ�����u����v�̈ٓ�����������Ɣc�����A�������N�������グ���u�i������w�v�Ƃ�������ɂ����ڂ��ׂ����Ƃ�������B�����āA��`�q�ł͂Ȃ��u�����v�A���Ɍ���ɂ���Ă��`�������q�g�̍s�������邱�Ƃ��A��O��ƂȂ��Ă���A�u����v�𑀂�͓̂����̒��ł��q�g�݂̂ł��邱�Ƃ��m�F���Ă������B
�@�����ŁA��P���ł́A2�̏͂��_�Ɋ������ƂƂ����B
�@�ŏ��̕�_�́A��T�́u�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�ł���B���̕�_�́A�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_��_�����{�E��P���ɂ����ẮA���ɏd�v�ł���B�{�ٍe�S�̂̃e�[�}���A�u�@�Ɛi�������w�v�u�@�Ɛi���S���w�v�ɂ��邽�߁A�u�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�̈ʒu�Â��������܂ŕ�_�Ƃ������A���̑�T�͂̓��e�́A���ꂾ���ŗD��1�̘_���̑ΏۂƂȂ邾���̖L���Ȋw�ۓI���ʂ��܂��Ă��邱�ƂɁA�܂����ڂ��ꂽ���B���T�́E��P�߂ŏq�ׂ��Ƃ���A������i��]�̒��N�̐i����ʂ��Ă̔��B�ƁA����ɂ���ĕ��G�Ȑl�ԍs���̋K���E�K�����\�Ƃ����@�E�@�w�̐����́A���W�ł͂��肦�Ȃ��B�����āA�u�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�́A<��`�q����`�q�ɂ��`����鐶���I���J�j�Y���Ƃ��Ă̔]���]�ɂ��w�߂��Ď�N�����q�g�̍s��>�Ƃ����\�}�̒��ł́A<���u���ߗv���v�ɋ߂��]�̊������A�@�Ƃ����Ɋւ���Ă��邩>���𖾂��悤�A�Ƃ�����]�������Ă���A����Ƃ����ɖڂ̗����Ȃ������̈�Ȃ̂ł���B
�@���T�́E��Q�߂ł́AOliver
Goodenough�̌����ɒ��ڂ��A�ȉ��̏d�v�ȓ_���w�E�����FGoodenough�́u�@�I���v���v�l���Ă��鎞�Ɏg���Ă���]�̕��ʂɂ��Ă̌����́A�{�e�`���Œf�����A�u�@���v�̑傫�Ȉ�́A�u�ߋ���700���N�̃q�g�̐����Ƃ��Ă̐i���I��Ձv�ɂ��邱�Ƃ��A�]�Ȋw�̑��ʂ������������̂��A�Ƃ����_�ł���B�܂��A�ނ̌����́A2006�N����Law and
the Brain�A2009�N����Law, Mind and Brain��2�����ȂāA�܂��܂����W�����邱�Ƃɂ����ڂ��ꂽ���B
�@���T�́E��R�߂ł́A�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ɓu�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�Ƒ肵�āA�_�o�ϗ��w�Ƃ����V���Ȋw�╪�삪�����オ����邱�Ƃ�����B���̒��ł��A�����݂̂Ȃ炸�A�������瓱�����Y���ӔC�\�͂��\���ɔO���ɒu���Ă��錤���������A�@�w�̊ϓ_����͒��ڂ��ׂ��ł��邱�Ƃ��w�E�����B�܂�����ɁA�Y�������̔Ɛl�ł��鐸�_�a���҂̔F�m�_�o�Ȋw�I���͂ɂ��Ă̘_������������Ă���A�����ł�fMRI�̐��_�a���w�ɂ����鉞�p�ɂ��G����Ă���B�������Ă݂�A�u�_�o�ϗ��w(neuroethics)�v�Ɓu�@�Ɣ]�Ȋw�E�_�o�Ȋw�v�̕���̘A�q�́A���łɊm���������A��������ڂ��ׂ��������ʂ����҂����B
�@��2�̕�_�́A��U�́u�@�Ɛi���ϗ��w�v�ł���A�i���ϗ��w���̂͂����܂ł����R�Ȋw�ł͂Ȃ����߁A�u�@�Ǝ��R�Ȋw�̐V���Ȑړ_�v�Ƒ肵����P���ɂ����ẮA�����ǂ����_�ƂȂ�B�������A��U�́E��P�߂ŏq�ׂ��Ƃ���A���܂ł͎�Ƃ���descriptive science�ł������i�������w�E�i���S���w�ƁAnorm�ɏd�_��u����normative
science�ł���ϗ��w�́A2�̈قȂ�science�̉z������}���A����2�����悤�Ƃ����S�I���ʼn߂ł��Ȃ����삪�A�i���ϗ��w�ł��邽�߁A���̕�_�Ō��y���Ă������B���U�́E��Q�߂ł́u�w���ƌ��v�Ƃ��āA����y�������A�����~���m�A�ɐ��c�N���y������3�l�̒����ɐG�ꂽ�ɉ߂��Ȃ����A�Q�l�ƂȂ�K���ł���B
�m�ȏ�F�Q�O�P�O�N�W���P���܂łɏ����Ă����āA���\�\��̕����ł��B�a�c���F�n